【第62回】子どもが主役”の学びを創る、多摩第一小学校のESDの取り組み(多摩市立多摩第一小学校)
2015.07.17
校門を出ると、すぐ目の前がもう多摩川土手
6月下旬のある朝、心配された雨もちょうどこの日を避けてくれたかのように空が晴れ渡った。ここ、多摩市立多摩川第一小学校は、ちょうど多摩川とその支流の大栗川に挟まれるように立地する、川沿いの学校。校庭の裏門を抜けると、そこは多摩川土手がもうすぐ目の前にある。
この日の午前中、同校4年生の総合的な学習の時間を使った、多摩川学習が行われた。年間70時間のうち50時間を使う『わたしたちの多摩川』の学習だ。この日のフィールドは、学校から土手沿いに徒歩5分ほど、大栗川との合流地点に当たるちょっとした広場。
担任の先生の指示で整列し、この日の講師役を務める羽澄ゆり子さんに挨拶をする。
「おはようございます。今日は、鳥の専門家の羽澄さんに来てもらって、野鳥観察の仕方を教えていただきます。(全員で)よろしくお願いします! はい、そしてもう一人の先生は、多摩川のプロフェッショナル・棚橋校長先生です!」
振り返ると、麦わら帽子を被った校長の棚橋乾先生がちょうど河原からあがってくる。朝から下見のため水位を確認するとともに、草刈り機で子どもたちが河原に下りるための道を切り広げていたため、すでに汗びっしょりだ。
迎える子どもたちは全員、長靴と帽子を着用し、クリップファイルに挟んだ記録用紙と筆箱を脇に抱えて、肩からは水筒を下げて、準備万端。
これからクラスごとに、棚橋校長といっしょに河原に下りて石の観察をするグループと、土手に残って羽澄さんと野鳥の観察をするグループに分かれて、時間を区切って入れ替わる。2時間の授業時間で、石と野鳥の両方の観察体験を順番にするわけだ。


石の誕生秘話を聞き、その不思議に思いをはせる
棚橋校長といっしょに石の観察をするグループは、土手から河原に降りて、ムンムンとする草いきれの中、背丈ほどに伸びた草むらの道を分け入って、石河原へと出る。
「石って、硬いし、痛いし、石コロなんて言われていて、あんまりおもしろくもないと思うかもしれないけど、実はじっくり見ていくといろんなことがわかるんです。今日はそんな話をします。
さて、今からしばらく時間をあげるので、1人3つずつ、石を拾ってきて、この白いシートの上に持ってきてください。置くときに、似たような石は近くに置いてください。それぞれに“これだ!”と思う石を探してくるように!!」
子どもたちは、遠慮がちに広がっていきながら、足元の石を拾い始める。
「もっと遠くに行っていいぞ、見える範囲なら!」
棚橋校長の声が響く。抱えるほどの大きな石を持ち上げようとする子、誘い合わせて水の近くに石を探しにいく子…。それぞれが思い思いに散らばっていく。




「例えば、この石。触ってみると、ザラザラしているでしょう。たくさんの砂が集まっているようにも見えるよね。これ、名前があります。砂石(すないし)? …う~ん、ちょっと違う。砂の岩と書いて、砂岩(さがん)と言います。海に砂が溜まっていってできたものです。それも1mとか2mじゃない。50mも100mも溜まっていくと、ギューっと固まっちゃうんだね。
なんとこの砂岩は海の底でできたものなんだ。不思議だね。ここはどこ? そう、川だよね。なんで海の石がここにあるんだろう。ヘンだよね。でもそれが大事なんです」
子どもたちが拾ってきた石を前に、棚橋校長の話が始まる。
「さあ、ノートと鉛筆を持って、このまわりに座ってください。さて、みんなが石を選んだ時、何を基準に、どういうことで“この石がいい”って思ったのかな? …模様、そう。他には? 形ね…。みんな、メモしておいてね。音!? ああ、ぶつけたときのとかね。それから何かある? 触った感じ…、色…、大きさね。だいたいそんなところかな。実は、これらの中で、石を研究している人たちも石の見分けに使っていることがあります。1つは色。2つ目は模様。そしてさわり心地。石って、もともと石ってわけではないんだな。別のものが石になっているんです」
そう言って、シートの上から子どもたちが拾ってきた石を一つ取り上げる。
次に取り上げたのは、白いツルツルした石だ。
「この石はすごいんだよ。貝殻やサンゴ礁などの生きものが死んで、海の底に溜まっていって、またぎゅ~っポン!とできた石です。昔の生きもののミイラ石だね。この白い石の名前は、石灰岩(せっかいがん)と言います。みんな、普段から大変お世話になっているものです。多摩一小は、立派な校舎があるけど、これ、何からできているか知っている? そう、コンクリート。
この石を粉にして、熱い蒸気で焼くとセメントになる。セメントに水と砂利や石を混ぜればコンクリートだ。この石灰岩という石はセメントの原料なんだね」
もう一つ海でできた石があるという。赤い小さな石を2個、取り上げて掲げる。
「今度は赤い石。チャートって言います。こういう赤い石を探して、石同士で叩いてごらん。(石を叩いてみせて、隣の子の鼻先に近づける)どんなニオイがする? 火薬っぽいだろう。このチャートという石は、珪藻※1の堅い殻が固まってできたものなの。なぞは、ここは川なのに、なんで海の石があるのか…?」
続いて、ごま塩模様の石を手にする。
「これは、今はさわれるけど、もともとは真っ赤に焼けたマグマだった。マグマが冷えて固まって、こんなふうになったんだね。花崗岩(かこうがん)と言います。これは海ではできません。どこでできるか? 山でできるんだ。ここは山だっけ? …おかしいよね」
一呼吸置いて、子どもたち一人ひとりの表情を見渡す。
「いろんな石を探しながら、順番にパズルのようにつなげていくと、多摩川がどうやってできたのかがわかってきます。石の中に、多摩川の歴史が詰まっているんだよね。地味だけどおもしろい、石の世界です」
疑問を投げかけ、あえて答えは教えずに、子どもたちに“?”と思う気持ちを湧き起こさせたまま、この日の授業を終える。

河原にゴロゴロしている地味な“石コロ”だが、その意外な歴史に、子どもたちは次第に引き込まれていった。
1分間、目をつぶって、鳥の鳴き声を聞き分けてみる
棚橋校長が河原の石の話をしていた同じ頃、土手に残った野鳥観察のグループの子たちは、講師の羽澄さんの話に耳を傾けていた。
「みんなが“多摩川”って言うとき、どこからどこまでが多摩川になるのかな? そう、山梨の源流から東京湾まで、線のようにつながっているのが多摩川だよね。じゃあ、幅はどうかな? どこまでが多摩川? 川の水が流れているところ? じゃあここは? 大栗川は多摩川? 違うかな? そこに何か書いてあるよね。『大栗川左岸 多摩川からOkm』…0ってことは、合流しているってことだよね。ということは、この辺も多摩川なのかな? みんなが“多摩川のことを調べるよ”と言ったときに、どんなふうに考えていったらいいんだろう」
子どもたちを見渡しながら、羽澄さんは話を続ける。
「はい、今日、私は鳥のお話をしようと思うんだけど、“多摩川にいる鳥”といったときに、あそこの水のところにいる鳥だけが多摩川の鳥なのかな? ちょっと違う気もするよね。鳥たちはそれぞれ好きな場所、必要としている場所があって、飛んできます。向こう岸に見える河原から、すぐそこの崖の上までも含めて、ここにいる鳥を“多摩川の鳥”として見ていきたいと思います。
目で確認することができる鳥がいます。でもそれだけじゃないよね。他にどんな方法があるかな? そう、鳴き声。それから? 巣があるかもしれない、そうだね。他に何か思いつく? インターネットで調べる? でもそれって自分の情報じゃないよね。自分で確かめるにはどうしたらいい? そうか、エサを食べにくる鳥がいるはずだから、こんな魚がいたらこんな鳥がくるんじゃないかなと予想することができるよね。そうです、考えつく方法はいろいろあると思います。他にもあるよね。足跡っていう方法もあるかもしれない。今度、川岸に下りたときにやわらかい砂のところを探してみると、足跡が見つかるかもしれないよね。
はい、それではこれから1分間、目をつぶって、どんな音が聞こえるか、鳥の鳴き声かなと思ったら、何種類くらいの鳥の声を聞き分けられるか、チャレンジしてみましょう!」
後ろの方の森の中からは、“ホーホケキョ”という鳴き声が聞こえてくる。頭上では、“カーカーカー”とカラスが数匹、鳴きながら飛んでいく。
ヨシ原の中からは、チャッチャッチャッチャ…と短い鳴き声が響く。スズメほどの大きさのセッカという鳥だという。ギョギョギョギョギョ…と鳴いているのは、オオヨシキリ。同じくヨシ原に巣をつくっている。
ピチピチピチという、ヒバリのさえずりも聞こえてくる。
「はい、じゃあ目をあけてください。どうだった? 何種類ぐらい聞こえたかな? じゃあ、2種類の人!」
ポツポツと手があがる。「カラス!」「ホーホケキョ!」と子どもたちが口々に声を上げる。
「3種類の人! 4種類は? じゃあ、5種類! 6種類? 7種類以上の人…!」
羽澄さんの問いかけに応じて、順番に手があがる。7種類以上という声に手をあげる子も何人かいた。
この後、「鳥って何のために鳴くのかな?」「一年中いつでも鳴いている?」と子どもたちに質問を投げかけながら、鳥の鳴き声の意味などについての話を展開する。1人1つずつ渡した双眼鏡を覗き込みながら、野鳥観察の仕方を教えていった。

『大栗川左岸 多摩川からOkm』

目をつぶって集中する子どもたち


じっくりと教わる
それまで聞き流していたことが、自然と耳に入ってくる感覚を知ってほしい
授業の後、羽澄さんに鳥の鳴き声の聞き分けについての話を聞いた。
「たぶん5種類ぐらいは私も聞き分けられていましたから、耳のいい子には聞こえているのかなと思います。中には、同じ鳥が違う鳴き方をしていることもあるので、それを数えている子もいるかもしれません。
ただ、“いっぱい聞こえる!”と思うワクワク感ってあるじゃないですか。今日の授業では、“すごいね、いろんな声が聞き分けられたね”ということでいいんじゃないかと思っています。それだけ多くの鳥の声が聞こえたって思うと、それこそ今後、授業中にも教室の外から聞こえてくる鳥の声が気になることがあるかもしれません。それまで聞き流していたことが耳に入ってくるっていう、そんな感覚っておもしろいですよね。一生懸命授業をしている先生には申し訳ありませんが…。
多摩川のことも同じなんですよ。今はまだ、ただの川として何気なく見ているだけかもしれません、一年間の多摩川学習を終える頃には、すごく豊かな川なんだとか、いろんなものがあるんだなとか、一つ一つがクローズアップして見えたりして、見方が変わってくると思います。今日、棚橋先生が石の話をしていますが、のめり込むタイプの子だと、河原を歩いていて石が浮き上がって見えてくるような感覚を持つ子もいます。赤っぽいチャートの石が際立って見えちゃうような。そんな感覚がもし芽生えてきたりすると、すごいことだと思いますね。
今のうちにそんな体験をたくさんしておいてほしいんです。たぶん中学・高校に進学していくと、ゲーム機器やスマホなどの都会的な遊びに吸い寄せられていって、今しているような体験がいったんは封印されてしまうことになる。でも、人生のさらに先のいつかのタイミングで、ふっと思い出すことがあったり、何かを考える基準になったりするような、そんな原体験として残っていってくれるとうれしいですね」
羽澄さんはこの日、“鳥たちの好きな場所”という表現を意識的にしたという。双眼鏡を使った観察で、碧く輝くカワセミの姿を目にしたグループもあった。そのカワセミを保全するためには、エサ場や営巣地などをひっくるめた生息環境が全体的に保全される必要があるということもわかってほしい。ただ、4年生の子どもたちにそんな難しい表現で伝えてもわかってもらえないから、「鳥たちって好きな場所があるよね」と言って解説しているのだという。

普段は、隣の多摩市立連光寺小学校の教育連携コーディネーターとして勤務。元は調査系のコンサルタントなどをしていた。その経験と人的ネットワークを生かして、自身で子どもたちの前に立つほか、植物や昆虫、水生生物などさまざまな分野の専門家を紹介している。
子どもの自由な発想で設定するテーマを大事に
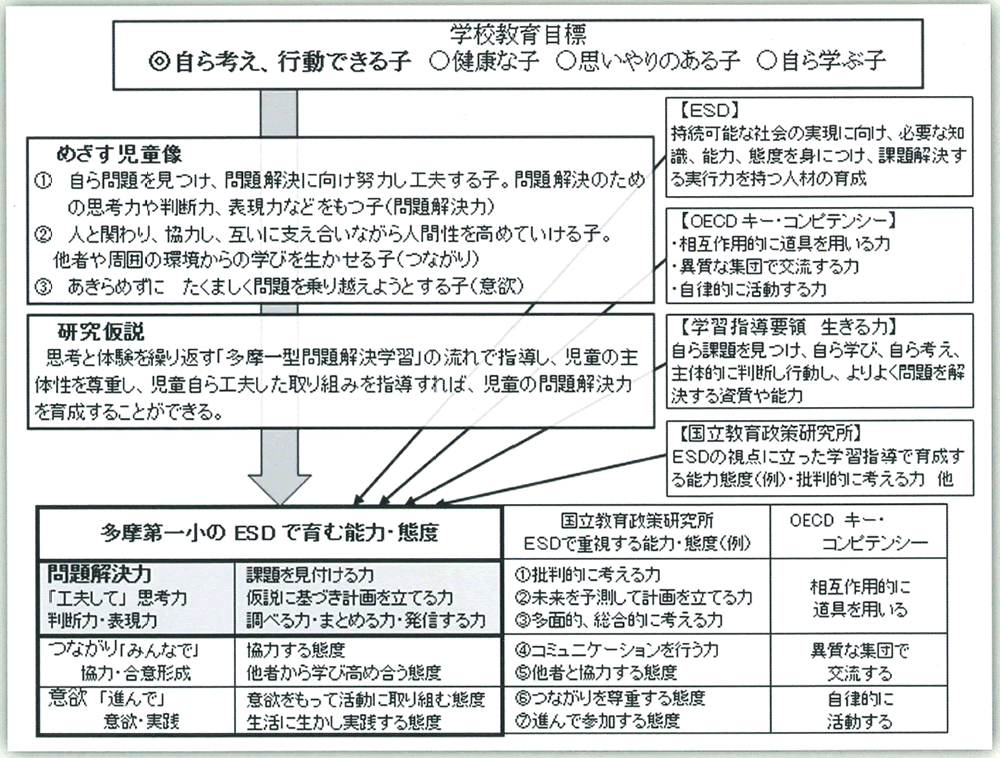
『問題解決力』『つながり』『意欲』の3つにまとめている。
※クリックで拡大表示します
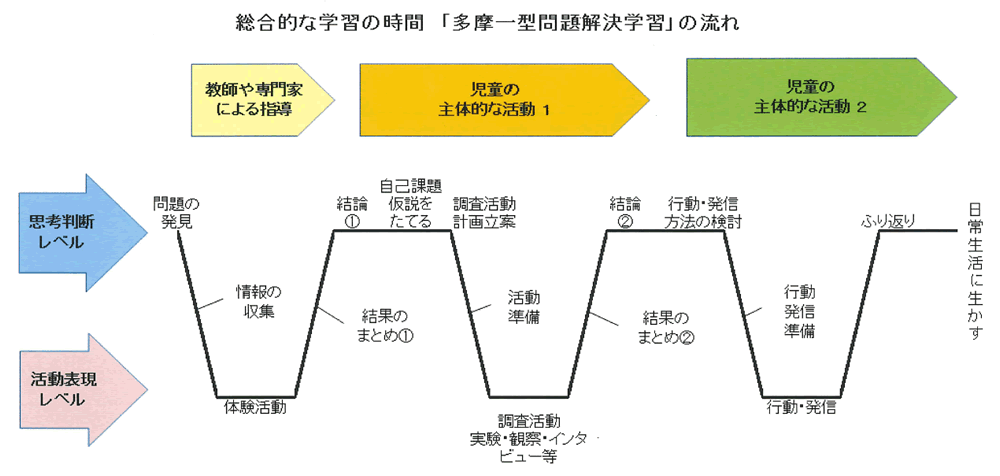
※クリックで拡大表示します
学校に戻って、棚橋校長先生から、4年生の多摩川学習の一年間の流れや、学校全体の環境教育やESD※2の取り組みについて話を聞いた。
「多摩第一小学校では、昨年度(平成25年度)と一昨年度(26年度)の2年間、国立教育政策研究所※3研究指定校として、ESDの研究に取り組んできました。OECDのキー・コンピテンシー※4や国がまとめている『ESDで重視する能力・態度』などは、実はなかなか難しくて、特に小学校ではうまく活用できていないんです。それで、多摩一小では、ESDのねらいを、『問題解決力』『つながり(協力する)』『意欲を持つ』の3つにまとめた研究をしました」
指導の仕方として、KJ法をつくった川喜田二郎さん※5が提唱する、“W型の問題解決モデル”※6を発展させた、下図のような流れを作っている。W型だけでは問題解決型学習で終わってしまうので、この先にESDならではの“行動・発信”のための課題を付けたという。
今日の授業は、4年生の総合的な学習の時間で学習する『わたしたちの多摩川』の入り口に当たる。今回は石と野鳥の話だったが、7月には水生昆虫や魚の観察、河原の植物観察などについて、それぞれ専門の講師に来てもらっての授業を予定している。こうして、まずは多摩川のいろいろなことを調べるための力や技術、見方を一通り体験するわけだ。
これらの学習を受けて、2学期になると、子どもたちがそれぞれの興味関心に応じて多摩川についてより詳しく調べるため、5~6人ほどのチームに分かれての学習を展開する。インタビューをしたり、現地で調査活動をしたり、インターネットを使って調べたりしながら、秋に予定しているまとめの発表に向けた学習が進むという。
チーム分けのテーマは、今回及び次回の授業で紹介する野鳥や石など教えたことに限らず自由に設定させることを重視している。
「テーマ決めを強制したり規制したりするとつまらないことになってしまいます。むしろ“大人が『え!?』と思うようなテーマを設定してよ”と子どもたちには話しています。昨年の子どもたちの中から出てきたテーマで特におもしろかったのが──なんでそんなふうに思ったのかわからないんですけど──、“多摩川に来ている人たちを調べたい”というチームができて、走っている人を追いかけたりしながら、『すいませ~ん、何しているんですか?』と聞き取り調査をしていました。大人にはなかなか思い付きませんよね。私もつい『誰がいた?』『何してた?』と様子を聞きにいきました」
まとめとしては、「犬の散歩が多かった」という想定内の結論になっていたものの、自由な子どもの発想が面白かったと棚橋さんは言う。

外部講師からの刺激で学習意欲に火が点いた後、子どもたちの自由な発想で取り組むことが大事
羽澄さんによる野鳥の話も、棚橋校長による石の話も、担任の先生たちだけでは教えられない専門的な知識やものの見方を外部講師等の話を通じて子どもたちに伝えてもらう。
「子どもが熱中できるようなものじゃないと、なかなか楽しくないですよね。熱中させるためにも、教科書に載っていないことだけど基本的な考え方や調べ方などを教えてもらいます。今日は羽澄さんだけでしたが、7月には他の講師もお呼びして、河原の植物を調べたり、川の中でガサガサと魚を捕まえて、1匹1匹を確認しながら、これがシマドジョウ、こっちはオイカワと、捕れた魚の名前も全部教えてもらったりします。そんなふうに水の冷たさを感じたり、ぴちぴちと跳ねる魚を目の当たりにしたりすると、子どもたちの眼の色が変わってくるのがわかります」
こうした外部講師の役割は、活動の入口として、子どもたちの学習意欲に火を点けてもらうことにある。大事なのはそれに続く活動だと、棚橋さんは強調する。
「多くの学校で、外部講師に話をしてもらって、『よかった』『ためになった』だけで終わりにしてしまい、“ありがとうございました”と感想文を書いてまとめにしていることも少なくありません。でも、それではあまりにもったいない。一連の計画の中で、子どもに火を点けてもらう最初のところを外部講師にお願いしたあと、そこから先は子どもたちの発想で自由にやらせてあげることをしないと、単なる体験学習で終わってしまいます。それでは問題解決力をつけたり、そもそもの意欲も湧いてきたりはしません。教えてもらうだけの受け身の学習では、身に付くものも限定的になってしまいます」
自分たちで考え、失敗をしながら獲得していくことこそが、本当の自分の学びにつながるわけだ。
ESDは、総合の時間でだけやればいいというわけではない
棚橋校長が多摩第一小に赴任してきて27年度で5年目を迎え、校内の共通理解も進んできたという。
「先生方は、問題解決的に教えるということの理解がだいぶ進んできました。それとともに、取り組んでいく中で、総合的な学習の時間だけでやればよいというものでもないということがはっきりしてきています。
例えば、子どもたちに予想をさせるとか、他の人の意見に対してちゃんと論理的に発言するといった授業態度や話型(話しの仕方)が重要なのです。感覚的にとか勢いだけでしゃべるのではなく、きちっと順番を踏んで構造的な話し方をするということを先生たちも指導するようになってきています。
子どもたちにそういうことをさせるような指導をするわけです。そうすると、先生自身はあまりしゃべらなくなります。子どもがいっぱいしゃべることになりますから。
そうした指導には、時間がかかります。子ども一人ひとりに応じた関わりも必要になりますから、試行錯誤しながらやるわけです。でもその分、本当に深まります。全員とは言いませんが、ほとんどの子が、総合的な学習の時間では夢中になって取り組んでいます」
棚橋さんが、子どもたちに対してよく言うのは、「主役は君たちなんだよ」ということだという。「主役がちゃんとしていない劇なんて、観ていておもしろくないだろう」と、学校教育の中での“主役”としての自覚と主体的な関わりの姿勢を促している。
朝礼の司会なども、「君たちが主役なんだから、来週からやってみてよ」などといって、どんどん子どもの関わりを増やしていく。低学年の子たちにとっては、5年生・6年生になったらあんなことまでやるんだ、できるんだという目標にもなる。
いろんな場面で、子どもたちの心の火を点火してきたのが、先生たちの役割だ。それに応えて、子どもたちの中でも徐々に大きな火へと育っていく。
「研究指定校では、成果をまとめて発表する必要があります。若い先生にも、他の学校の研究発表を見に行かせますが、先進的と言われる国立大学の付属校などの取り組みでも、それほど驚かないで帰ってきます。うちの学校でやっていることが、それほどぶれていない、根っことして同じようなことを考えていましたよと言って帰ってくるのです。そういうことが言えるくらい、若い先生たちの意識も高まってきています。ですから、子どもたちが変わっただけでなく、先生方にも大きな変化と成長が出てきています」

と話す、多摩市立多摩第一小学校・校長の棚橋乾先生。


