【第30回】異なるものが違和感なくいられるような地域社会をめざして ~コミュニティガーデン『みんな畑』の試み(野の暮らし)
2013.05.15
“恊働”の作業を通じた“居場所”づくり活動
JR南武線「谷保」駅から徒歩約5分。住宅街の一角から、古めかしい平屋の二軒長屋が立ち並ぶ細い路地を入っていくと、ちょうど道の中ほどに200坪ほどの小さな畑が見えてくる。この畑が、『野の暮らし』を主宰するすがいまゆみさんが呼びかけて実現した、コミュニティガーデン『みんな畑』だ。畑の隅には、杭につながれたヒツジが人恋しげな鳴き声を響かせる。
訪れたとき、畑はちょうど春先の端境期(はざかいき)。菜の花とノラボウ菜とレタスの収穫を終えれば、その後には夏野菜を植える。ビニールハウスの中や畑の一角で、それらの苗の準備がはじまっているという。
コミュニティガーデン『みんな畑』が開園したのは、2009年10月。いわゆる市民農園のような個人区画割の自己責任制で作物を育てるのではなく、みんなで話をしながら、“恊働”の作業をしていくための場をめざす。「恊働」は、普通は「協働」と書くが、あえて「恊」の字を当てることで、「心と力を合わせて働く」という意味を込めていると、すがいさんは言う。関わる人たちがそんな関係性を築いていけるような場への想いを込めて、この畑をコミュニティガーデンと呼んでいるわけだ。
「畑を借りる前には、アパートの一室を借りて居場所づくりの活動をしていました。『ひだまりじかん』と呼んで、朝から夕方まで部屋を開放して、一日中、いつ来て、いつ帰ってもいい、陽だまりで日向ぼっこをするように遊びにきてねという活動です。学校に行っている・行っていないにかかわらず、年齢にもかかわらず、いろんな人たちにとって居場所になるような場所をつくりたかったのです。しかもそれは生活に根差している方がよいから、いっしょにごはんを食べたりする。そのためには、小さくても古くてもよいから、庭があって、縁側があって、茶の間になるようなところもあってという、そんな家があるとよいと思って、探し始めたのが、『みんな畑』につながっていったのです」
居場所づくりの拠点になる家を探して谷保(やぼ)※1のまちを歩き回ったが、古い家の多くは、建て直しや相続が発生したときに出ていってくれないと困るからと、貸してもらえないところが多かった。


実は今、『みんな畑』の奥に『畑の家』と呼んでいる居場所活動の拠点になっている平屋の一軒家があるが、当初に話をしに行った時の反応は芳しくなく、諦めていた。その手前にあった耕作されなくなって荒れ果てた畑──現在、『みんな畑』として活動している畑──を眺めながら、ふと、家でなくても畑を活用して居場所づくりができるのではないかという思いを抱いたという。
「当時、アパートの一室を開放しながら、ごはんを食べて話をする会を催していて、どうせ食べるのならきちんとつくられたものを選びたいよねと地元の農家さんが有機農法でつくっている米や野菜を買わせていただいていました。谷保で区画整理事業が始まり、いっしょに区画整理の方法を再考してほしいと活動を始めた縁で、一週間に一度、農作業を手伝っていました」
それが、すがいさんが農作業をはじめるきっかけとなり、その体験が居場所づくりの活動と結びついて、畑を舞台にした活動を思い付いたという。続けてすがいさんは言う。
「実際に農作業をしていると、すごく気持ちがよかったんです。それと、農業って自然には勝てませんよね。天候にやきもきし、自分の意志ではどうにもならないことと折り合いをつけていかなければならない。それでも、作物は着実に育まれていく。そうやってできた収穫物をいただくことの意味を強く感じるようになって、畑の可能性を感じるようになったのだと思います」

遊びながらの作業によって、畑が蘇っていった
耕作されなくなって3年ほど経っていたこの畑は、当時、草はぼうぼう生え放題、劣化したマルチ※2などの農業資材やあまった肥料・農薬なども無造作に置かれていた。隣の敷地との境界線沿いには笹やヤブカラシなども繁茂していて、ごみも散乱していた。
貸してもらえるようになって、まず始めたのが、これらのごみの片づけだった。当時、国立市で市民団体が運営する、学校に行かない子どもたちの居場所の活動がちょうど閉鎖され、そこに通っていた子どもたちといっしょに活動することになる。小学生から高校生にあたる年齢の子どもたち6~7人が、作業半分、遊び半分、笹やぶの奥に転がっていた一輪車をひっぱり出してきて遊んだり、根を掘り起こしてできた穴に入り込んで遊んだりもしながら取り組んだ。


山のように集まったごみは、耕作していた人のご家族と相談して、市を介して撤去してもらう。徐々に、畑作業のできる環境が整い始めた。
畑を活用して居場所活動をすることになったから、イベントなどを開催したときなどには人も集まる。でも、畑には農作業以外では入ってほしくなかったから、境界線となる道を、板を埋め込み、砂利を敷いて作ることにした。
活動を始めてから1か月ほど経って、何とか作物が植えられるくらいに片付けが済んだところで、麦を蒔いた。この麦が青い穂を実らせるようになった半年後、これまでの成果報告を兼ねた『オープンデー』を開催した。子どもたちがカフェを開いて、クリの木の下でごはんを食べながら、畑を舞台にした居場所活動のお披露目をしたわけだ。


ちょうどこの頃、畑の奥にあった平屋の一軒家を居場所活動の拠点として借りられることになった。
大家さんが、遊びながら働きながら、畑がどんどん変わっていく『みんな畑』の活動の様子を見ていて、畑に向き合っていこうというメンバーたちの本気を感じ取ってくれたのか、「まだ借りる気があるなら貸そうか」と言ってくれたのだ。相続が発生したときにはすぐに明け渡すことと住居としては使わないことを条件に、貸してもらえることになった。
現在、この平屋を『畑の家』と呼んで、居場所活動の拠点にしている。畑作業がしたい人は畑に出る、のんびり過ごしたい人は『畑の家』で過ごす。畑では、年間60種類ほどの野菜を作ったり、生ごみの堆肥化に取り組んだりもしている。生ごみは近隣10世帯の協力で集めるもので、市環境保全課との“恊働”で実施している。今はスズメバチに襲われていなくなってしまったが、知り合いが持ってきてくれたニホンミツバチを育てていたこともあった。つい先日には、埼玉県熊谷市で統廃合された保育園で飼われていたヒツジを縁あってもらえることになり、畑の一角につないで飼っている。いろんな人たちが、ヒツジの餌に、と、野菜の外葉や草を差し入れてくれることもある。


たまたま生まれた子がしょうがい児だったというただそれだけのことを、受け止められない自分がいたし、受け止めてくれない社会があった
すがいさんが居場所づくりの活動を始めたそもそものきっかけは、お子さんの誕生だったという。
「一番上の子が知的しょうがいを持って生まれたんです。今は成人して働いていますが、しょうがいがある子どもが生まれたことは大きな転機になりました。子どもが生まれるってどういうことなんだろうとか、しょうがいがあることで命に何かしらの差があるのか、しょうがいを持つことは社会的に恥ずかしいことなのかとか、そういうことをいっぱい考えさせてもらいました」
どんなに重いしょうがいがあっても、意思も感情もある。しょうがいを持っているというだけで、地域の中で暮らしていくことが当たり前にならないのはなぜなのか。しょうがいのある人がいたって別にいいんじゃないか、そんなふうに思うようになっていったという。
小・中学校は普通学級に通わせていたものの、中学生になって荒れるようになったという。クラスの子に殴られたり蹴られたりして帰ってくるようになり、本人にとってもストレスが多くなっていった。でも、先生に相談しても“生徒たちに確認しましたが、誰もいじめている子はいないと言っています”と真剣に向き合ってもらえなかった。学校に通わない状況になって、子どもの居場所づくりの活動を始めるようになっていった。
子どもが成長するにしたがって、居場所だけでは事足りなくなる。しょうがいを持った子どもたちのための働く場づくりをはじめることになったのも自然な流れだった。
「子どもが18歳くらいになったとき、居場所づくりだけでなくて、“働く場”を作ろうと思うようになったのです。当時、うちの子は立川にあった放課後の余暇活動をしているところに通っていたのですが、そこの仲間たち4人が中心となって話し合いを重ねて、商店街の空き店舗を使ってカレー屋さんを作るという話を進めていました。作業所といわれる場所が、閉じられた場所ではなく、地域の中の開かれた場所にあった方がよい、だからこそ、商店街の中の空き店舗でやりたいと思いました。立川市の同意を得て、東京都もほぼ設立に同意をしてくれて、補助金も出ることになって、あとは働く人を集めればよいというところまできた、まさにそのときになって、いっしょに進めてきた3人が二の足を踏んだのです。そして、計画が頓挫することになりました」
すごくショックだったし、大きな心の傷として残ることになったとすがいさんは言葉を詰まらせる
本当にやりたいことなら、自分で決めて、はじめなければ、動き始めない
『みんな畑』でも『畑の家』でも、その活動は、本人の自由な意思で選べるようにしているという。畑仕事をしたければすればよいし、何もせずにのんびり過ごしてもよい。何かしたくなったらすればよい。
「黙って、何もしなくてもいい場所って、なかなか世間は用意してくれないですよね。やっぱり、“何かしなさい”って言うじゃないですか。居場所にいれば何かが解決するとは全然思いませんが、でも安心して悩んでいられる場所は必要だと思うんです。したくなったらすればいい。そうでなければ何もしなくてもよい。ただ、いろんな人には会っておいた方がいいと思うんです。いろんなことを体験することはしておくとよい。だから、必ず社会とつながっておくことが大事だと思うんです」


荒れていた畑を片づけていたとき、自然とコミュニケーションが生まれていった。
『みんな畑』で、畑を開墾したり、生け垣を作ったり、東屋を建てたり、ヒツジ小屋をつくったり…。時に文句を言いながら、作業に没頭する子どもたちのことを、ここに関わる多くの人たちが気にしてくれていたという。作業中に声をかけてくれたり、差し入れを持ってきてくれたりする。路地に面した畑で作業をしていることで、自然とそんなコミュニケーションが生まれていった。
居場所づくりの活動をしたいと公言するようになって、でも共感してもらえるよりも笑われることの方が多かったと、すがいさんは自嘲気味に話す。


「たとえ共感してもらえなくても、自分の中ではっきりしていることは、“決める”ということ。“自分で決め”て、はじめること。それは、いっぱい失敗してきたから、いっぱい傷ついてきたからこそ思うようになったことでした。作業所が本当に目の前で、もう立ち上がるという段階でダメになったことが今でも残っています。描いていた夢が実現するという目の前だったのに。いっしょにやっていた3人に対して、ず~っと恨み言をいっていたんですよね」
長年付き合ってきた友達が愚痴を聞いてくれていたが、その友達に言われたひとことがずしりと心に響いたという。
「その友達には、“そんなに言うんだったら、一人でやれ!”って言われたんですよ。“それだけ恨み言が言えるということは、すがいは本気だったんだろうけども、だったら一人でやればいいじゃない。でも一人でやるっていうことは、たった一人でやるわけじゃなくて、すがいが一人でやるって決めたら、必ずいっしょにやってくれる人が出てくるから、やるかやらないか決めなよ!”、そう言われたんです」
それと同時に、そのときに一人でやるって言えなかったことも指摘されて、だったら他の3人に対して恨み言をいう資格なんてないんじゃないかとも言われたという。そんなふうに言われたことはすごくしんどかった反面、一人でもやると決めろと言われたその言葉が深く浸み込んでいった。
単純に夢物語で言っているだけならいいけれど、本当にやりたいのかどうかは他人ではなく、自分自身に問いかけられてくる。だから、どんな些細なことでも──それは本当にどんな些細なことでもいいから──やろうと思ったら、やると決めればいいというわけだ。
「最初、別に『みんな畑』を作ろうって決めていたわけではないんです。でも居場所がほしいと思っていて、“そうだ、畑を居場所にすればいいんだ”と思ったときに、“畑を借りよう!”ということは誰でもなく、自分が決めることなんですよ。どうなるかわからないけど、でも“畑を貸してください”と言いに行く、本当に居場所活動をしたいと思っているんだったら。そんな感じですね。別にものすごく大層な決意をしているわけでもないんですよ。それほど気負ってやっているわけではありませんから」
居場所をつくって閉じ籠るのではなく、社会の中の一員として、より多くの人たちとともに問題解決の道を探る
そうしてやると決めて、まずは行動していったことで、『みんな畑』を借りられることになった。やろうと決意した活動に、協力してくれる仲間たちも自然と集まってきていた。『みんな畑』の活動がきっかけになって、『畑の家』も貸してもらえるようになった。
「たぶん、社会と切り結びながらやってきたからこそだと思うのです。自分たちだけの世界に閉じた活動で、自己満足のような関係性つくっているだけでは、世の中は変わっていかないじゃないですか。それこそしょうがい者など“弱い”といわれている立場の人たちが、当たり前に暮らしていける社会なんてつくれっこないですよね」
最近、すがいさんが居場所づくりの活動と並行して力を入れているのは、国立市の『農業・農地を活かしたまちづくり事業』推進協議会協議委員としての活動だ。
国立市産業振興課が担当する同事業の推進協議会は、市民に委嘱して設立したもので、市民農園を運営している人や農家さん、消費者団体の人などが参画している。市に対する提言を議論・作成するだけでなく、それを実現するための責任ある役割を果たしていこうと、具体的な活動にも取り組んでいる。
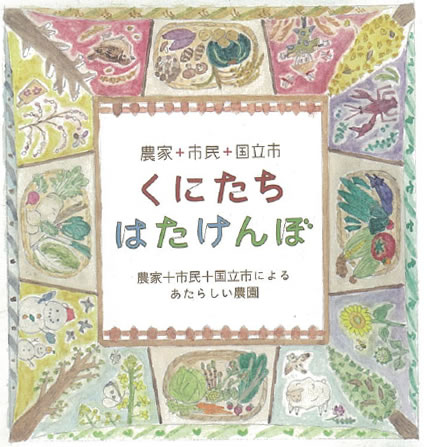
すがいさんは、区画整理の問題に関わるようになって以来の課題として、“農地を持たない市民がどうやって農地保全に関わるか”ということに関心を持ち続けてきたという。もとは違う問題意識とアプローチだったものの、『みんな畑』も市民による農地保全の一つの実践事例になっていると言える。
協議会では、例えば国立市内で市民が参加できる各地の市民農園を紹介し、それらの交流と情報交換を促進するための会を作ったり、高齢で耕作できなくなって閉鎖されることになった梨園を借りて会員制の農園『くにたち はたけんぼ』を開園したりと、少しずつ具体的な成果も生まれてきている。この『くにたち はたけんぼ』は、ハケ(崖線)のまち・国立に新しくできたモデル農園で、敷地内に畑と田んぼがあることから名付けた。個人ではなく、企業・NPO・市民サークルなどの団体に貸し出す区画があったり、農園の運営を学ぶ『農園マスター』の育成をしたり、四季折々の“畑の幸”をみんなで収穫して採れたて野菜を楽しむ農園祭を開催したりという計画だ。
農地や農業を守っていくのに、農家だけの苦労では限界があるから、農地・農業を守るための制度やアイデアをより幅広い立場で提案し、実現のために汗をかいていこうという意欲的な取り組みだ。

※クリックで拡大表示します
地域の中にある課題を、その当事者だけで解決しようとあがくのではなく、地域の中のいろんな人たちが自分たちの問題として認識し、関わっていけるように働きかけていく。それは、居場所づくりの活動でも、『農業・農地を活かしたまちづくり』でも変わらない、すがいさんの基本的なスタンスだ。



