【第02回】都心のまつりでビオトープ・ワークショップ ─まちの記憶を辿る『土地の記憶プロジェクト』の試み(青山商店会連合会)
池を掘り、植物を植えてトンボやカエルがやってくるのを待つ
「今回の作業では、池をつくりますが、その過程で、池に水がちゃんとたまるような形状にするための測量もやります。今回はワークショップですから、ただ作業を早く進めるというよりは、皆さん一人ずつが、どういう意味の作業なのかとか、自分の目で実際の測定値などを見てみながら、ぜひビオトープづくりに参加しているという実感をたくさん持ってもらえたらと思っています。何か質問、ありますか? 大丈夫ですか? じゃあ荷物をいったん置いて、作業しますよ」
ビオトープづくりの会場になっているのは、港区立青山中学校の校庭の一角。開放的なグランドとは対称的に、木々が鬱蒼と生い茂った薄暗い林の中を分け入った小さな空間に、今回つくる池の形に線が引いてある。
講師は、ビオトープ管理士の三森典彰さん(34)。参加者・スタッフを合わせて20名ほどが作業にかかる。
今年で第25回を数える青山祭の会期中、10/22(土)と23(日)の2日間に開催されたビオトープ・ワークショップでの一幕だ。日曜日の午後からはじまったこの日の作業では、深さ25~30cmほどの小さな池を掘り、水を溜めてビオトープにする計画。完成するとほどなく、トンボ──今からの季節だといわゆる赤とんぼの仲間数種類くらい──などの水生生物が産卵のためにやってくる見込だという。まずは植物を植え付けて、根付くようにするのが当面の目標になる。

(提供:青山商店会連合会)
「ビオトープ」とは、Bio(生き物、命)とtope(ギリシア語のtopos=場所や空間)をつなぎ合わせた言葉で、「生き物の場所を作る」という意味で使われる。生き物の場所をつくるには、生き物の気持ちになってつくらないとわからない。それには、生き物の視点に立って、場づくりのための視点を持つことが大事だと講師の三森さんは言う。午前中、まつり会場内のブース脇で開催された青空講義では、青山の街らしくバリスタ風の衣装に身を包み、参加者との軽妙な掛け合いによる説明があった。午後からは場所を移して、体を動かしての作業がはじまった。
参加者は、地元青山高校の生徒たちや企業のサラリーマン、教員志望の都内大学の学生など、その顔ぶれもさまざまだ。前日の大雨とは打ってかわってすっきりと晴れ渡った秋空の下で、心地よい汗をかく。


測量機械を覗き込み、

池の高低差を測る

完成した池の水面に映るビルが印象的だ
なぜ、都会のまつりでビオトープなのか
このワークショップ、実は『土地の記憶プロジェクト』と名付けられている。
青山のまちのイメージのように、どこか洗練された、でもなにやら深淵な響きを持つ。「土地の記憶」に込められた意味とは? また、なぜ都心のまつりでビオトープなのか。青山祭を主催する青山商店会連合会で、この取り組みを進める市川博一さんに話を聞いた。
市川さんは、普段は南青山にあるギャラリーを経営。“人と街と文化”をキーワードに、伝統工芸品を手がけたり、日本の素材と技術を生かしたものづくりの提案をしたりと多角的に展開している。
モダンな店舗や大規模な企業ビルが建ち並ぶ、ここ青山周辺には4つの商店会があり、青山商店会連合会はその連合組織だ。
その中心を青山通り(国道246号線)が通っている。都心とはいえ、青山周辺には、神宮外苑や東宮御所、新宿御苑、青山墓地など生き物のすみかとなる大きな緑の拠点が残り、大通りから一本入れば意外に閑静な住宅街だ。ただ、これらの緑の拠点を国道246号線が分断している。
『土地の記憶プロジェクト』は、その246を「いきものも通える道にしよう」とはじめた取り組みだという。
見せていただいた資料の中には、安藤広重・作『名所江戸百景』に掲載された一枚の浮世絵が引用されていた。青山周辺のかつての風景を描いた、「紀乃国坂赤坂溜池遠景」。ここには、アシなどが生える浅瀬の水辺が描かれている。トンボやメダカなど豊富な生物が生息できる生態系の基盤があったことが伺えるという。今、その周辺は、車が渋滞する大都会の市街地に変貌した。同じ広重の「せき口上水端はせを庵椿やま」で描かれた神田川は、今は無機質な三面張りの水路と化している。自然界がもともと持っていた浄化作用が機能しなくなり、水質汚濁を招く一因にもなったと考えられている。
ビオトープづくりは、特定の種を守っていくための活動ではない。水辺や植物があって、その中でいろんな生き物が息づいていく。それこそが、本来の生態系のあり方だ。このため、かつてあった浅瀬の水辺をつくる。このとき、植物や魚を導入することもあるが、土地在来の植物を植えることを大事にしている。幸い、青山小学校のビオトープで植物もメダカも増えてきていて、青山高校にも持っていったし、今年つくった青山中学のビオトープもここで育ったものを移植した。

「紀乃国坂赤坂溜池遠景」

「せき口上水端はせを庵椿やま」
市川さんたちの活動は、青山の土地の風土と歴史にこだわっている。それは、地域の自然環境が地域の文化をつくっていくという思いがあるからだという。
暑いところ、寒いところ、山麓の森に囲まれた土地での生活、海辺に生きる人たちの生活、それぞれその土地固有の文化が育っているし、その土地風土にあった伝統工芸が成立していった。それが本当の文化だし、自然と文化は一見関係ないように見えて、実は表裏一体のものなのだ──と。
日本人の細かなものを捉える独特の感性は、豊かな四季の移ろいがあったからこそ成り立つところがある。例えば、日が沈み、月が昇ることに“美”を感じる心。ちょっとした障子に写った影をきれいだと感じる感性。それらは日本の自然環境に育まれてできてきたのだから、そういった感性を育んでいくのに、本来の自然環境が大事になってくる。
青山は都会だが、青山の街の文化を考えていくときに、まず大事なのは、この土地での暮らし方がどういうものかということを考えることだと市川さんは言う。
洗練された都市の中にビルがどんどんできてきて、新しい会社も入ってきて、街の暮らしも昔と変わってきている。だからこそ、この土地でどうやって生きて行くのかを、いろんな企業の人たちにも入ってきてもらって考えていきたいのだという。そのときに、取って付けたようなことをするのではなく、この土地本来のあり方を模索していきたいと。


できてすぐに生き物がやってくるビオトープのおもしろさ
ビオトープづくりをはじめることになったきっかけは、3年前のこと。それ以前から緑を増やしたいという思いはあったが、その手法がわからなかったという。どうせやるならちゃんとしたことをした方がいいとアドバイスされ、紹介されたのが、『土地の記憶プロジェクト』の専門的・技術的なサポートを頼んでいる「人と自然の研究所」の野口理佐子さんだった。
“土地の記憶”というコンセプトをどうやって街に融合させようかということを考えてきたなかで、その土地に合った視点というのがビオトープだと意気投合した。「それって土地の記憶ですよね」ということで転がりはじめたという。
一昨年(2009年)の青山まつりで、青山小学校に移動式ビオトープをつくり、昨年は青山高校にビオトープを造成した。今年のまつりでは、初日に青山小学校のビオトープの観察と改修、2日目に青山中学校でのビオトープ造成が計画された。

青山小学校でのビオトープづくりは、もともと商店会とのつながりもあって、話を持っていくとトントン拍子に進んだ。つくったビオトープのメンテナンスも、学校の授業の一環として子どもたちが担うことになった。つくるだけでなく、つくった後の変化をみながら、その意味を肌で感じていくことにつながる。
継続的な観察は、株式会社リコーのボランティアが特に強力なサポートをしてくれた。リコーでは、社員対象に「環境ボランティア養成プログラム」を実施していて、野口さんが講師で関わっている。その縁で、『土地の記憶プロジェクト』にも関わりができた。
青山まつりで移動式ビオトープをつくった翌年の2月、小学校の砂場跡地にビオトープをつくることになり、リコー環境ボランティアの実践活動の一環として、ビオトープ造成をした。以来、毎週水曜日の早朝を観測日と定めて、同小のビオトープの定点観測を続けてきた。
9月には、ビオトープづくりの活動の意味を人に伝えるを学ぶ中級講座を開講。ちょうど10月に控えた青山まつりを意識して実施したこの講座の余勢を駆って、青山高校でのビオトープづくりをした昨年のまつりには、ボランティアリーダーのべ30人の参加があったという。
同社のCSR室の伏見聡子さんは、同社の環境ボランティアプログラムの活動史上、初めての“ビルの谷間での活動”になった同小でのビオトープづくりやその後の定点観測が、一つの転機になった手応えを持ったという。
「リコーの自然活動は森林保全からはじまっていて、ボランティアリーダーとして自主的な活動を始めた人たちも森林保全活動をしている人が多いんです。でもそれだと、都会に住んでいるとか都心の事務所に通っている社員なんかはやりにくい。働いている場所の近くで何かできないかというときにちょうどビオトープづくりをやっていることを知ったんですね。森での活動と違って、割とすぐに反応がある。造ってすぐに生き物がやってきて、おもしろかったですよ」
「見せ方とか伝え方が大事だなって、やればやるほど思いました。森に通う社員たちは、作業して、お疲れの乾杯をして帰っていくっていう感じです。もちろんお楽しみも大事なんですが、もう少しその活動を伝えていくとか違う方向に持っていきたいと思っています。都会の方がみんなのつながりが再生のキーとなるので、いろいろとやりやすいのかも知れませんね」



池なんかつくったら、蚊がわいてくるんじゃないの!?
市川さんが街の人たちに「ビオトープをつくろう」と言ったとき、「蚊がすごいわくんじゃないか」と誰もが言ったそうだ。
ところが、生態系がきちんと循環していれば、むしろ蚊はそれほどわいてこない。ちゃんと餌として食べていくトンボなどの昆虫がいれば、蚊ばかりが増えていくような環境にはならない。
「そういうことすら、都会に住んでいるとわからなくなってしまっているんですよ。そういうことも含めた気付きがすごく大きかったですね。だから、蚊がわくから水辺を埋めてしまえとかいった発想にはならなくなりました」
市川さんは、この取り組みの効果をそう話してくれた。
「逆に言うと、木が植わっているから自然があるということでもないという気付きもありました。森でも、植林されたスギの木ばかりではきちんとした森にならないということも、こういうことから学んだんですよ」
青山でのビオトープづくりの活動が、日本の里山のことも教えてくれたという。
今後は、この取り組みをより広く理解してもらうための仕掛けをしていきたいという。街の人たちに話しても、理解はしてもらえるようになった。
年配の人たちも、「おおいいじゃないか」「昔あったよ、こんな池」「昔はこの辺でもとんぼをいっぱい捕っていて、おれはカエルを捕っていたよ」とか、懐かしい感じで喜んでくれるようになった。
だから、それを小難しい理屈で語りたくはないという。ビオトープや生物多様性という言葉はまだまだ一般にはなじみが薄い。それをいかに感じよく捉えてもらえるか。
せっかく青山でやっていることなので、都会ならこその、野暮ったくなく、おしゃれに、美しいものにしたいんだ、と。
冒頭の疑問、「なぜ、都心のまつりでビオトープなのか」は、なるほど氷解したように感じている。
つまり、いきものの拠点となる緑地を分断する246という大きな道路が通っているここ青山だからこそ、小さなビオトープを点々とつくっていって、それらのビオトープを拠点にしていきものたちが移動できる回廊をつないでいくことが必要だということ、それによって、いずれ面として生き物が暮らせる範囲が広がっていく。それも人知れずやっていくのではなくて、「祭」という多くの人がつどってくる場で展開することを重視する。地域の人々や祭にやってきた人たちといっしょにやっていこうという手段でもあり、意思の現れでもあるのだろう。
今や人々が忘れてしまった、かつての地域の自然のありよう、でもその土地で生きてきた動植物はかつてとなんら変わることのない自然の摂理の中で生きている。だから、少し手を入れ環境を整えてやることで、わずかな日数でも思いがけず多くのいきものたちがやってくるわけだ。それこそが、土地に刻まれた“記憶”ということなのだろう。
市川さんの言葉を借りると、「ビオトープづくりとは、生き物の場所をつなげ、人と人をつなげ、地との風土や歴史と今をつなげること」だという。『土地の記憶プロジェクト』、なるほど言い得て妙な取り組みと言える。
10年後かもっと先になるのか、青山の街にかつてあった自然が少しでも回復してきて、そしてその自然とのふれあいが青山に暮らす人たちにとって新たな原風景として息づいていくことを楽しみにしたい。
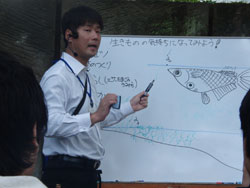
(青山まつりの会場にて)

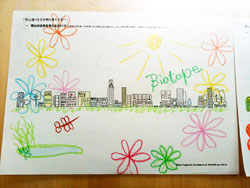
(提供:青山商店会連合会)


