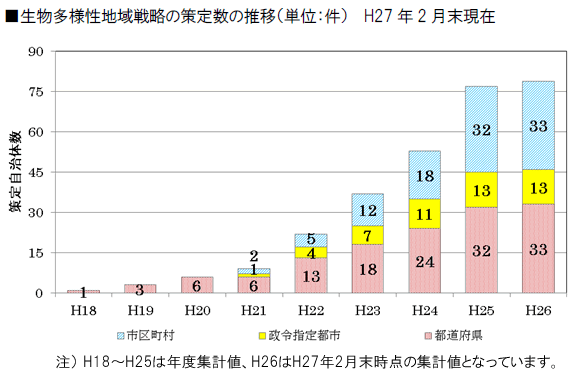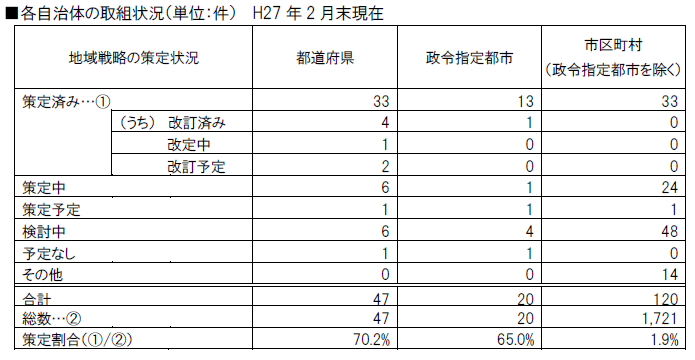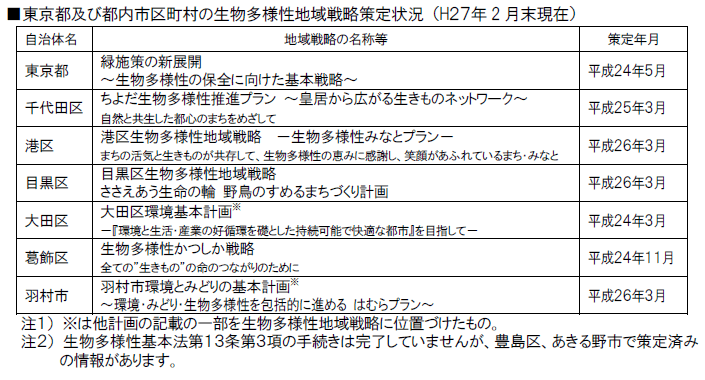【第42回】いきものの話ばかりでない…生物多様性地域戦略のお話

橋本 和彦(はしもと かずひこ)
1966年北海道生まれ。1989年帯広畜産大学卒業(野生動物管理学研究室でナキウサギの貯食調査)、1990~1992年青年海外協力隊員としてドミニカ共和国派遣(ウサギの飼育指導)、1992~1993年野外科学株式会社入社(哺乳類調査等)、1993~2014年北海道庁入庁(希少種対策、レッドデータブック作成、ヒグマ対策、国定公園管理・施設整備、エゾシカ対策)、2014年4月より環境省生物多様性地球戦略企画室。生物多様性国家戦略や地域戦略、気候変動の適応策など担当。
「生物多様性地域戦略」は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関して、都道府県や市町村が作る基本的な計画です。平成20年6月に制定された生物多様性基本法に位置づけられており、地域における取組の重要性から策定を促進していきたいところですが、「そもそも生物多様性という言葉が難しい」、「生物に関する専門職がいない」、「生物の生息状況が把握できていない」などの理由で策定できない自治体もあります。「生物多様性地域戦略」が、地域にとってどんな意味を持つのか、簡単にご説明します。
1.生物多様性について
「生物多様性」ってなんでしょう。色んな種類のいきものがいること…それもあります。ところで今日は何を食べましたか? それは一体どうやってあなたの元までやってきたのでしょう。あなたが食べたものは、ご飯、野菜や魚、肉など、「いきもの」でしたね。そのいきものの命は、それが育った場所の水、空気、土、他のいきものなどによって支えられています。そして、そのいきものは、さらに別のいきものに支えられている…このようなつながりが「生物多様性」の最も大切な本質の一つです。
土に触れることのない生活を送っているので、生物多様性は関係ない…と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような生活でも、食べたものや使った水、空気でさえ、あなたの街から離れた国内あるいは海外の生物多様性が支えています。このような生物多様性の恵みを「生態系サービス」と呼んでいます。地球という限られた惑星に生きている私たちは、どうやったら持続的に生態系サービスを受け続けられるのかを、一人一人が考えていかなければなりません。そうでなければ、知らないうちに失っているかもしれないからです。
生物多様性が貧弱だと、さびしい生活になることでしょう。例えば、魚が1種類しかいなくなってしまった時のお寿司を想像してみてください。様々な海の幸が載ったお寿司は、豊かな海のある日本ならではの食文化です。地域にはそこにしかない生物多様性があり、それが地域の食も含めた文化を育み、歴史が積み重ねられてきました。あなたの町で一番好きな場所はどこですか。遠くから友人が訪ねて来たら、何を食べさせてあげたいですか。そう考えると、ご当地の名勝や名物は、その地域の生物多様性に支えられているものが多いことに気付きます。
2.みんなで戦略を練りましょう!
豊かな水や森、すばらしい風景、きれいで豊かな海、地域の特産物、移り変わる季節など…これらの自然とその中での人々の暮らしが、地域を特徴づけています。好きな場所、おいしいものは10年後も残っているでしょうか?将来の世代も、同じように暮らしていけるでしょうか?そのことをみんなで考えることが大変重要です。「将来に向けて地域として生物多様性とどうつき合っていくか」という地域の計画が「生物多様性地域戦略」です。
生物多様性基本法では、生物多様性地域戦略が備えるべき要件が規定されていますが、大切なのは「将来に向けて地域として生物多様性とどうつき合っていくか」です。それにはまず、地域の暮らしと生物多様性との関わりを明らかにする必要があります。地元やそれ以外の地域の生物多様性からどんな恵みを受けているのか…これを紐解いていくことで自分たちがどれだけすばらしい場所で暮らしているか、あるいは他の地域に支えられているかを「知って」、そして「感じる」ことが重要です。それが次のステップである「保全や持続可能な利用」のためにどんな取組ができるか、例えば、地場産物を選んで積極的に食べるとか、とにかく自然に触れる機会を増やすなどの検討につながっていきます。
これらの過程では、行政だけでなく、住民のみなさんはもちろん、NGOやNPO、事業者、学校など、多くの関係者・機関が集まって、みんなで意見交換し、戦略を練り上げていくといった心意気が、良い結果に導いてくれるのではないでしょうか。地域が受ける自然の恵みをみなさんで話し合う作業などは、豊かな気持ちになって、きっと楽しいに違いありません。
この地域戦略を策定することで、他にも次のようなメリットがあると考えています。
(1)地域の活性化をもたらし、新たな姿を創造する。
(2)地域を構成する様々な主体のネットワークが形成される。
(3)地域だけでなく、日本や世界という広域スケールで、生物多様性に寄与できる。
(4)市民などからの信頼が向上する。
地域戦略の検討では、地域の様々な魅力や資源を掘り起こしそれらを評価していくことになります。生物多様性について考えることは、地域の自然をベースに産業やライフスタイル、歴史文化など様々なことが互いに連関していることから、全体を統合的に捉え検討を進める必要があります。さらに、検討の対象となる生物多様性は、地域に特有なものであり、その切り口から地域づくりを進めるということは、その土地ならではの独自の価値を見出し、それが地域への愛着や誇りにつながるとともに、それらの魅力を活かした新たな地域像の形成にも役立つと考えています。
このように、生物多様性の保全と持続可能な利用を地域で進めていくことは、地域社会そのものを豊かで、持続的なものにしていくことに他なりません。地域の様々な主体が関わって進められる地域戦略の検討を通じ、人口減少や高齢化が進み、都市と地方の在り様も移り変わる中で、人間の社会経済活動と自然が調和する地域づくりにつながっていくことが期待されます。
3.地域戦略策定の支援ツール
現在、環境省では、各自治体での地域戦略の策定を支援するため、策定の手引きを作って公開しています(URL)。この手引きでは、策定のプロセスや各項目の考え方のほか事例も紹介し、策定時に必要な情報を提供しています。
また、地域戦略の策定済み自治体のリストも公表し(URL)、リンクを設定して各地域戦略を紹介するウェブサイトが参照できるようにしています。
これらの支援ツールも活用しながら、まずは地域のすばらしさを、生物多様性の観点から再発見するというところから取組を始めていただけると嬉しいです。