【第58回】「地球温暖化対策計画」の閣議決定を受け、改めて私達の地球温暖化対策を考える

一方井 誠治(いっかたい せいじ)
1951年東京都生まれ。東京大学経済学部卒業後環境庁(現環境省)入庁。環境庁地球環境部企画課長、環境省大臣官房政策評価広報課長、財務省神戸税関長、京都大学経済研究所先端政策分析研究センター教授などを経て、現在、武蔵野大学大学院環境学研究科長、工学部環境システム学科教授、京都大学特任教授。京大博士(経済学)。著書として「低炭素化時代の日本の選択」岩波書店、2008年(単著)、「国民のためのエネルギー原論」日本経済新聞出版社、2011年(共著)などがある。
昨年末に、パリで京都議定書に代わる2020年からの地球温暖化対策の国際枠組みとして「パリ協定」が合意されました。その協定を受け、日本では、平成28年5月13日に、地球温暖化対策推進法に基づく「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。本稿では、この計画の概略をご紹介しつつ、改めて私達の地球温暖化対策について考えてみたいと思います。
1.地球温暖化問題は解決できるの?
本計画の「はじめに」のところに「地球温暖化の科学的知見」が記されています。そこでは、「1850~1900年平均と比較した今世紀末(2081~2100年)における世界平均気温の変化は、排出を抑制する追加的努力のないシナリオでは2℃を上回って上昇する可能性が高く、厳しい緩和シナリオでは2℃を超える可能性は低い」とされています。
さらに、その厳しいシナリオについては、「世界全体の人為起源の温室効果ガス排出量が2050年までに2010年と比べて40%から70%削減され、2100年には排出水準がほぼゼロ又はそれ以下になるという特徴がある」としています。これはきわめて厳しい数字です。
パリ協定では、2020年以降の新たな国際枠組みとして、先進国、途上国を問わずそれぞれの国が自主的に決定する温室効果ガスの削減目標を各国が示すことが対策の基礎となっています。京都議定書の場合はこの削減目標は先進国にのみ課されていましたので、一歩前進といえます。しかしながら、各国が示したこの削減目標を総計した場合、今世紀末の気温上昇を2℃以下に抑えることは不可能ではないものの、2℃目標を最小のコストで達成する経路には乗っていないこと、また、追加の削減努力が必要になることがわかっています。
結論的にいえば、現在の状況は地球温暖化問題が解決できる目途がたったとはまだ言えない厳しい状況にあるということを理解する必要があります。

2.京都議定書目標は達成したけれど
さて、ご承知のように今回のパリ協定に基づく国際枠組みの前には京都議定書に基づいた国際枠組みがありました。日本は、2002年に本議定書を受諾し、第一約束期間(2008~2012年)における温室効果ガス排出量を基準年(原則1990年)比で6%削減する約束を順守するため、地球温暖化対策推進法に基づいて京都議定書目標達成計画を策定し、官民をあげて対策を行ってきました。
今回策定された「地球温暖化対策計画」でも述べられているように、結果的にはこの削減目標は達成されました。しかしながら、この達成の内容については、少し注意して振り返っておく必要があります。まず、第一約束期間中の5カ年平均の総排出量は、12億7,800万トンCO2で、これは基準年比1.4%増となります。京都議定書の日本の削減目標は6%削減であるというイメージからはやや異なる結果ですが、これは森林吸収源による排出量の相殺と外国から排出クレジットを購入したことによる相殺を加えると、計算上、基準年比での排出量が8.7%減になるためです。もとより、この森林吸収源やクレジットの扱いについては、京都議定書の合意の過程で日本に対して公式に認められたものですので、計算上は問題ないのですが、地球温暖化問題の解決という観点からは、日本は京都議定書の約束期間を通じた温室効果ガスの総排出量は純減ではなく純増であったということは、認識しておく必要があります。
また、京都議定書の第一約束期間である2008年から2012年という時期は、ちょうどリーマンショックが起こり、日本でも経済が大きく落ち込み、エネルギー使用量も減った期間にあたります。温室効果ガスの排出はエネルギー使用量に大きく影響されます。事実、日本の温室効果ガスの総排出量は、2007年までほぼ増大の傾向にあったのですが、2008年から2012年にかけて大きく落ち込んでいます。京都議定書目標の達成は、第一約束期間に偶然起こった景気後退によるエネルギー使用量の減による影響が大きかったということも併せて認識しておく必要があります。
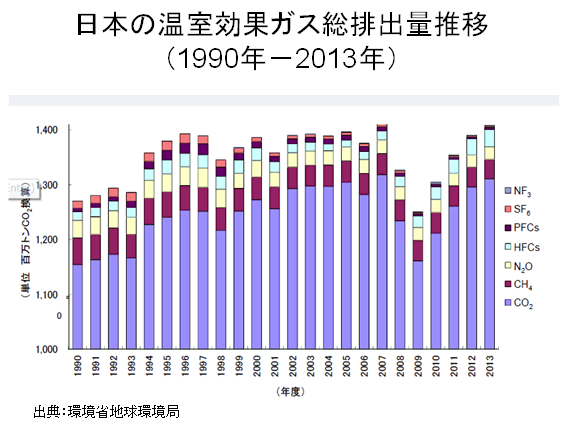
3.日本の削減目標と対策の柱を見てみよう
今回、日本が提出した温室効果ガスの中期削減目標は、2030年度において、2013年度比26.0%減です。1990年度比に直すと約18%の削減になります。また、長期目標としては、2050年までに80%の削減を目指すとしています。ちなみに、EUは2030年における削減目標は、全体として1990年比で40%減、ドイツ一国でみると、55%減となっています。
次に、対策の柱ですが、まず主体ごとに基本的な役割が示されています。
まず「国」ですが、「多様な政策手段を動員した地球温暖化対策の総合的推進」が掲げられています。具体的には、自主的手法、規制的手法、経済的手法、情報的手法、その他環境影響評価を含む多様な政策手法を動員して対策を推進するとしています。また、国民各界各層への地球温暖化防止行動の働きかけ、国際協力の推進などがあげられています。
次に、「地方公共団体」ですが、「地域の自然的社会的条件に応じた施策の推進」が掲げられており、具体的には、再生可能エネルギー等の利用促進と徹底した省エネルギーの推進、低炭素型の都市・地域づくりの推進、事業者・住民への情報提供と活動の促進などを図ることを目指すとしています。
「事業者」については、「事業内容に照らして適切で効果的・効率的な対策の実施」が第一に掲げられ、地球温暖化対策を幅広い分野において自主的かつ積極的に実施することや、省CO2型製品の開発、廃棄物の減量等、他の主体の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置についても推進することとしています。
「国民」については、「日常生活に起因する温室効果ガスの排出の抑制」がまず掲げられ、地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運動「COOL CHOICE」を推進し、低炭素建築物の選択、省エネルギー機器への買い替え、電力の排出原単位の小さい電気の選択等により低炭素ライフスタイルへの転換をすすめる、としています。
対策計画では、このあと、「地球温暖化対策・施策」として、A.産業部門の取組、B.業務その他の部門の取組、C.家庭部門の取組、D.運輸部門の取組、E.エネルギー転換部門の取組について具体的な対策・施策が述べられています。さらに分野横断的な施策として、国民運動の展開や税制のグリーン化に向けた対応及び地球温暖化対策税の有効活用、国内排出量取引制度などについても言及されています。
4.注目される対策・施策は何だろう
以上、日本の削減目標と対策の柱を概観してきましたが、冒頭、書きましたように、世界的にも、国内的にも地球温暖化問題の解決の目途がたったとは未だ言い難い状況にあります。また、京都議定書の目標達成の経緯を振り返っても、日本は、これまでにない新たな手法を含めた、今一層の対策努力を続ける必要があります。
特に、今日の気候変動対策はエネルギー対策と深くかかわっており、さらには経済そのものとの関わりが一層強くなっています。また、地球温暖化問題というと、単純に低炭素化ということが強調されるきらいがありますが、より広い人類社会の「持続可能性」という観点からの対策も必要です。
その面から、私は本計画における次のような対策・施策に注目しています。
(1)国における「経済的手法」の強化
本計画では、金融のグリーン化や国内排出量取引制度に言及しています。特に、EUではすでに2005年から導入されている排出量取引制度や、日本では2010年から導入されている東京都の排出量取引制度についてもきちんと評価検討を行い、学ぶべきところは学び、自主的な取組みや国民運動のみではない、きちんとしたキャップ(排出枠)が付いた排出量取引制度をはじめ、市場メカニズムを活用した経済合理的な気候変動対策が進むことを期待しています。今日、経済的手法は、環境保全のための手法であり経済にとってはマイナスであると解することは適当ではなく、継続的な技術革新や経済の効率化を通じた中長期的な経済発展のための有効な手法でもあるという認識をもつことが重要です。
(2)地方公共団体における「再生可能エネルギー利用の促進」や徹底した「省エネルギーの推進」の本格的展開
本計画では地方公共団体におけるこれらの取組みが期待されています。地方公共団体は、縦割り行政の色彩が強い国と違い、知事や市長のもとで分野を超えた施策を統合的に行うことが可能です。例えば、長野県では、地球温暖化政策とエネルギー政策を統合した「長野県環境エネルギー戦略」を2013年2月に策定し、県独自の目標のもとに、自然エネルギーの導入や省エネの推進を図り成果をあげてきています。ちなみに、この戦略では、環境を改善しつつ経済も伸ばすという考え方が基本となり、企業に対する丁寧な説明や支援策ともあいまって多くの県民の理解を得ています。このような動きが、他の地方公共団体にもさらに拡がっていくことを期待しています。
(3)国民における「COOL CHOICE」の活用
今回の計画では、地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運動として「クールチョイス」がうたわれています。社会経済を変えていくうえでは「価値観・意識の変革」「革新的技術の開発・普及」「社会システムの改善」の三つの要素が有機的に連動していく必要がありますが、いずれも容易なことではありません。しかしながら、国民ひとりひとりがより良い社会に向けて自らの選択をし続けることで、いつしか世の中の価値観・意識が変わり、企業等における環境にやさしい革新的技術の開発や普及を促し、国や地方自治体の政策を変えていく大きな力になることを期待します。その意味では、単に受け身の選択だけではなく、企業や行政に対する積極的な働きかけも重要です。
(4)日本における本格的な国家持続可能な発展戦略の策定
率直に言って、日本における持続可能な発展戦略は、いまだ確立していないと言っても過言ではないと私は思っています。気候変動対策の分野でもエネルギー構成をめぐっていまだ多くの議論が残されています。また、先の京都議定書目標達成計画を見ても、また、今回の地球温暖化対策計画を見ても、それぞれの分野での温室効果ガスの削減目標とその数値の積み上げは詳細に行われているのですが、それを実際に実現するための手法が、自主取組みや国民運動に委ねられているところが多く、必ずしも実効性のある手法がきちんと用意されていないというきらいがあります。また、ドイツのエコロジー税制改革に見られるような環境保全と雇用対策を同時に実現する、環境と経済との政策統合という面からも物足りなさがあります。
ドイツでは、2002年に国の上位計画として「ドイツの展望―私達の持続可能な発展に関する戦略」を策定するとともに、2010年には、環境対策と経済対策を高次に統合した長期戦略である「エネルギー・コンセプト」を策定し、きわめて抜本的なエネルギー改革を進めています。そして、それがドイツの気候変動対策と経済対策の大きな柱にもなっています。大事なことは、それにより、実際にドイツは経済を伸ばしつつ温室効果ガスの削減が実現していることであり、残念ながら同じ時期の日本の削減状況は、はかばかしくないという事実があることです。日本でも、今回の地球温暖化対策計画の基本的な方向で述べられている「長期的な目標を見据えた戦略的取組」を目指し、そのような本格的な持続可能な発展戦略の策定を期待したいと思います。
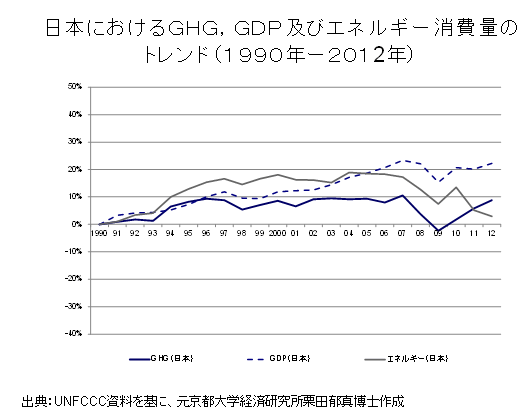
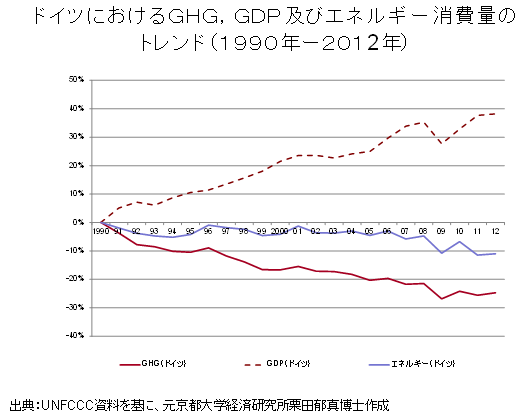
参考文献
- 政府文書、「地球温暖化対策計画」、平成28年5月13日閣議決定
- ドイツ政府資料、「Energy Concept」、2010年
- 消費者庁審議会資料、「諸外国における持続可能な発展戦略について」、2008年
- 長野県文書、「長野県環境エネルギー戦略」、2013年
- 一方井誠治、「低炭素化時代の日本の選択」岩波書店、2008年


