【第14回】森について教わったすべてを忘れ去ったあとに残るもの ~森の子コレンジャーの学びの取り組み(森林レンジャーあきる野)
2012.08.01
「小宮ふるさと自然体験学校」が森の子コレンジャーの活動のベース
夕暮れの旧あきる野市立小宮小学校跡地の校門前に、小4~中学生までの「森の子コレンジャー」25人と、「森林レンジャーあきる野」4人を含むスタッフ10人ほどが集まった。子どもたちは、ターコイズブルーが鮮やかな揃いの帽子を被り、長袖・長ズボンに身を包んで、ヘッドライトを身につけている。背中のリュックの中には、水筒や雨具の他、野帳と筆記用具も入っている。
旧小宮小学校は、明治6年に開校した歴史ある学校だったが、児童数の減少に伴って今年(平成24年)3月末に138年の歴史に幕を下ろした。大岳山を源とする養沢川のほとりに位置し、ヤマメの校内人工孵化・飼育・放流や、自生ホタルの観察会、湧き水を利用したワサビ栽培など、自然豊かな同地域の特色を生かした取り組みを行っていた。閉校後は「小宮ふるさと自然体験学校」として生まれ変わり、24年度で2期目となった森の子コレンジャーの活動のベースとなっている。

この日は、森の子コレンジャーの月に一度の活動日。普段の活動は朝9時から夕方4時までだが、夜の森の散策を組み込んだため、特別に午後2時からの開始となった。はじまりの会でこの日の作業の説明と前回のおさらいをしてから、校庭に出てのこぎりで丸太を切って自然学校の展示づくり。スライド写真を見ながら夜の森の観察会に向けた予習などをしてから、夕方5時から屋上にのぼって青空の下で腹ごしらえをしたあと、いよいよ夜の森に向けて出発する。子どもたちの期待はいやが上にも盛り上がり、ザワザワと落ち着かない。
「はい、みんな!そろそろ出発するんだけど、ちょっと聞いてください」
森林レンジャーの“かせちゃん”(加瀬澤恭子さん)が声をかけて、子どもたちの意識を集中させる。4人の森林レンジャーたちの中で、加瀬澤さんが森の子コレンジャーの主担当を務めていて、司会進行などの役割を担っている。森林レンジャーも子どもたちも、5月の第1回のときに丸太のネームプレートに呼んでほしい名前を書き込んで胸元や帽子に付けていて、そのニックネームで呼び合っている。
「昼のプログラムで、夜の森で出会いたい生き物を何人かの子があげてくれたよね。自分の会いたい生き物と会うには、どうやって森を歩いたらいいかな?」
かせちゃんの問いかけに、子どもたちが口々に反応する。
「静かに!」
「上を向いて歩く」
「うんそう、静かに。夜の森を静かに歩くということは、いろんな音が聞こえてくるから、それをぜひ感じてください。夜の森は生き物も出てきたりするから、静かに行きたいと思います。それと今、“上を向いて”って言った? いろんなところに目を光らせて、見逃さないようにしたいね。ただ上ばっかり見てたらどうなるかな? 夜の森は暗いから足元がちゃんと見えないよね。だから、足元もちゃんと見ながら、走らない、友だちを押さない──それは守ってください」
子どもたちの言葉を受けて、注意点を盛り込んでいく。
装備の確認も忘れてはならない。ヘッドライトを持っていない子には、森林レンジャーが用意したものを渡す。
「ライトの使い方で注意する点は?」
ここでも、子どもたちの反応は早い。
「点けない!」と、ある子が真っ先に声を上げる。
「そう、レンジャーが点けていいよと言うまでは、点けずに歩いてください。他には?」
「目に向けない!!」。別の子が、すかさず発言する。
「そう、人の目にも自分の目にも、光を向けないことだね。見えなくなっちゃうからね」
おしゃべりに夢中になりすぎずに自然の中を歩く感覚を大事にしてほしい、そして暗さにも目を慣らして、夜の闇と月や星の明かりを感じてほしい──そんな思いだ。
続けて、“たいちょう”(=森林レンジャー隊長の杉野二郎さん)から、夜の森の注意について話がある。
「今日、“森でヘビを見たい”と言った人がいましたけど、ヘビ、たぶんいます。みんな、マムシって知っているかな? マムシはいつ動き出す? そう、夜なんです。ごはんを探して、ウロウロしています。勝手に草むらに入ったりすると、噛みつかれるぞ! 噛みつかれると死ぬこともあるから、気をつけること、わかった? それと、雨が降ったので、滑りやすくなっているよね。だから、あまりはしゃいで走ったりすると、滑って転ぶ。転ぶだけならいいんだけど、道の端から落ちたりすると──(ふざけながらじゃれ合っている子をつかまえながら)きみら、本当に気をつけろよ!──。ともかく、足元が悪いので、本当に転ばないように、気をつけて歩いてください」

次世代に残していくために、子どもたちに今ある自然を伝えていく
活動紹介の第1回記事でも紹介した「森林レンジャーあきる野」は、あきる野市内の森林を舞台に、保全活動や森づくりと踏査・生物調査などを行うその道のプロたち。あきる野市が平成22年3月に策定した「郷土の恵みの森構想」に基づいて、全国から公募された。メンバーは、隊長の杉野さんと加瀬澤さんのほか、スペイン出身でハ虫類が特に大好きというパブロ・アパリシオ・フェルナンデスさん(パブロ)、機械の操作が得意でパンフレットやルートマップの作成も担当している佐々木優也さん(さっさー)の4人が名を連ねる。
こうしたプロ集団を持つ自治体は全国的にも珍しいが、市域の約6割が森林というあきる野市にとっては、大きな意味を持つ(→詳しくは、第1回記事を参照)。
森林レンジャーの活動は多岐にわたるが、特に子どもたちに向けたプログラムとして力を入れているのが、昨年度からはじめた「森の子コレンジャー」だ。市内の小4~中学生を対象に、森林体験&実践活動を行うもので、初年度の第1期は隔月開催の全6回に19名の子どもたちが参加した。第2期となる24年度は毎月開催に拡充し、参加人数も29名に増やした。うち、1期生から継続して参加しているのは11人だ。
「コレンジャー」の「コ」は、一つには“子どもレンジャー”を意味するが、それだけではない。Cooperation(コーペレーション)の「Co-」の意味も込めている。「協力、協同、協調」といった意味の言葉で、コレンジャーたちが、森林レンジャーや地域の人たち、そして自然や仲間たちと協力して森づくりを行っていってほしいという想いを込めた愛称だという。
第1期の23年度には拠点となる施設やフィールドがなかったこともあって、市内の菅生、養沢、乙津の各地区で、森の自然観察や体験活動をメインに進めてきたが、今年度から小宮ふるさと自然体験学校という拠点ができ、川を挟んだ対岸の森を地主さんの理解と協力で借りられることになって、実践的な森づくりを活動の柱に据えられるようになった。

5月の第1回活動日、子どもたちに認定証を授与。
森の子コレンジャーの活動は、5月の「始動式」を皮切りにして、1年間の活動を開始した。
「自然を愛するあなたをコレンジャーと認定します。仲間と絆を結び、あきる野の自然とふれあい、遊ぶことを目標に、1年間楽しく活動しましょう! そして、素晴らしい自然を発見し、学び合い、共に守っていこう」
──そんなふうに記された認定証と、コレンジャーの証である揃いの帽子と野帳が授与されたのは、5月13日(日)のこと。以降、毎月第二日曜日を定例活動日としている。
1期から引き続き参加しているという女の子に、コレンジャーの活動について話を聞いた。
「前の日はね、『え~、明日朝はやく起きなきゃいけないの~!?』って気が重くなるけど、でも、はじまると楽しい。自然といろいろふれ合えたり、いろんな人と仲よくなれるの」
野帳には、毎回の活動で見つけた生き物や森林レンジャーの話を聞いてメモしたことが書かれている他、最後のページに友だちになった子の名前が並んでいる。

森の子コレンジャーの一日
一日の流れはこんな感じだ。
毎回、朝9時の開始に合わせて、小宮ふるさと自然体験学校に集合する。交通の便がよくない場所なので、各家庭が車で送迎する。1日の活動を終える夕方には、4時の解散時間に合わせて迎えの車がやってくる。ただし7月の回だけは、夜の森の散策を組み込んだため、午後2時集合・夜8時過ぎの解散となった。
開始時間になって全員が集まったら、はじまりの会だ。部屋の中だったり、青空の下だったりする。その日のプログラムを説明し、子どもたちの様子を見る。
プログラムは、午前と午後にお昼の休憩を挟んで2時間ほどの作業を入れている。例えば、初回の午前中は木の枝を薄切りにしてヤスリで磨いて名札をつくった。午後からは山道を通って、近くの集落まで挨拶をかねての散策だ。途中の森では、倒木の上で実生(みしょう)が芽を出している様子を観察。じゃまな倒木や朽木を片付けてきれいにすることだけが“森づくり”ではないと、森の木々の世代交代についての話がある。倒木の幹の上から芽を出すため下草などに遮られることなく光に当たることができるし、朽ちていく木が土の替わりに養水分を与えてくれるというわけだ。みずみずしくスッと立ち上がる新しい命の息吹とそれを支える古木の存在から感じるものを大事にしてほしいという。
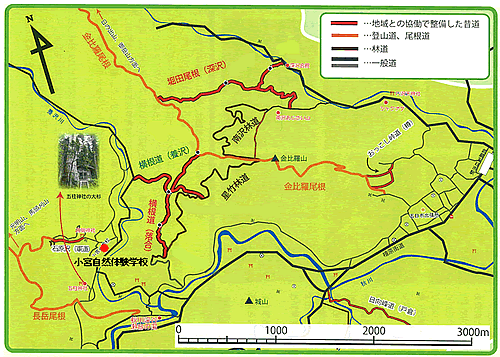
6月の第2回には、森の中のトイレ小屋づくりと、散策路の整備、檜の森の下草刈りという3グループに分かれての作業で汗を流した。グループ分けは、各作業に象徴的な道具──トイレ小屋づくりに使う大工道具「ノコギリとトンカチ」、散策路の整備に使う「カケヤとクワ」、下草刈りに使う「ノコギリとカマ」──のうちでそれぞれが使ってみたいものを選んでもらった。ちょうどよい具合に人数がばらけてくれた。
作業の途中、タカチホヘビというちょっと珍しいヘビを見つけた子がいた。1期生から参加している子で、森林レンジャーのパブロのヘビ好きに影響を受けてヘビに興味を持ったという。1期の活動のときに、躰と尻尾の境目について説明されたのを覚えていて、全長と尻尾の長さを測って、他の子たちにも教えていた。
1期から参加している子たちには「リーダーとして頑張ってね」と話をしたものの、特別な役割を与えて縛りたくはない。1期から継続して参加した子も2期からの新規参加の子も、それぞれのやりたいことや好きなことを伸ばしていってほしいという。そうして生き生きと伸びやかに過ごす姿が、まわりの子どもたちにも影響を与える。ときに開放的になりすぎて、羽目を外しすぎて怒鳴ってしまうこともあると苦笑を交えて話す加瀬澤さんだったが、子どもたちが率先してやりたいこと、やりたい方向に進んでいってほしいという。かといって、無理にやらせることもない。それぞれのペースで、その子なりに感じられるものがあるような、そんな場づくりを心がけながら、森づくりの作業やコレンジャー同士、森林レンジャーやスタッフとの関わりを通じて、森とともに子どもたちにも変わっていってほしいというのが森林レンジャーたちの願いだ。
毎回、一日の最後には、ふりかえりの時間を取っている。一日のできごとを振り返って、その時々で見つけたものや感じたことを思い出して、全体で共有しながら印象づけていく。大事なプロセスの一つだ。



何も学んでいないようでそれなりに学んでいる、そんな子どもたちの姿に勇気づけられ
年度当初に立てた年間の活動計画では、下表のように季節に応じた自然の姿を体験しながら、毎回の活動内容の関連性と継続性を考慮して、立案したという。もちろん当初の計画案だから、子どもたちの状況や天候などによっても柔軟に変えていっている。雨が降っても、よほどの荒天でない限り、今年は拠点施設となる自然学校があるから室内のプログラムで対応できる。
第1期(23年度)の活動では、あきる野市の森のいろんな自然を紹介できたことで、子どもたちも「今日はどこに行けるの?」「今日は何ができる?」と毎回を楽しみに参加していて、満足度も高かった。その反面、子どもたちは“遠足気分”が強く、遊びにきたという感覚で参加していたような傾向もあったと分析している。24年度から小宮ふるさと自然体験学校をベースに活動することになったのも、一つ所に落ち着いた“森づくり”の活動をすることで、森や自然とより深くふれあってほしいという思いがあった。
ただ、子どもたちは、森林レンジャーたちが思った以上にいろいろと感じることもあったようだし、子どもたち同士のつながりを感じていてくれたらしい。
「この活動は、参加者のみんなに“自然体”で参加してほしいと思っているので、あまり『仲よくしなよ』などと言うことはなかったんですね。友だちや兄弟で参加している子たちは一緒にいることも多いし、一人で作業や観察に没頭する子もいます。グループ作業のときは一緒に力を合わせるように言ってますけど、団体行動をさせるつもりはあまりないんです。そう思っていたんですけど、昨年度末、1期生の最後の回で子どもたちが──何を言ったわけでもない中で──、自然にみんなで遊びはじめたんですよ。何かよい感じのまとまりができていて…。そのときに、あ、これでよかったのかなと思うところもありました」
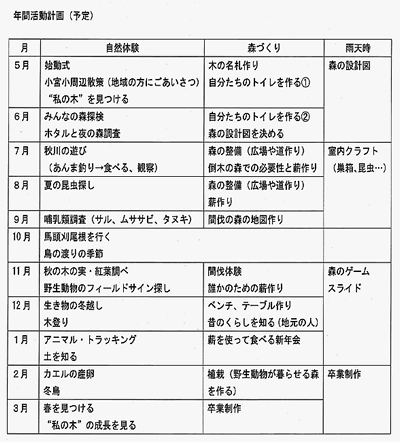
子どもたちの成長は、自然に対する視線の違いから見てとれる。1期生と2期生を見ていると、どこか違うと感じさせるところがあるという。ただ、そうしてすぐに目に見えてくるものだけでなく、将来的な芽として子どもたちの心の中に育つものがあるとよいと願っている。
「森づくりの作業では、子どもたちにやらせることも重要だと考えています。今やっている作業がどんな意味を持っているのか、十分に理解できているのかどうか、正直なところよくわかりません。でも、例えば大人になって、『あのときの作業はこういうことだったんだ』と感じるものがあればよいんじゃないかって。頭で理解することよりもまずは体験して、その結果として、すぐにではなくても腑に落ちるものがあればよいと思うんです。それが子どもたちにとってよい体験になると思っています」
森の木を切ることをきちんと理解させることはなかなか難しい。適度に伐ることで森の中に光が差し込み、残った木や下草にとってよいと説明されてもどこか釈然としない思いを持つ人も少なくはない。きちんとわかって作業してもらいたいけど、簡単にわかった気になるよりは、心に残る違和感を大事にする方がより深い理解を与えることもある。
「森づくりではそんなに木を切ることはないんですけど、去年も間伐の体験をしました。そのときに、木が倒れていくときの自分の心のざわめきのようなものを感じる気持ちを大事にしてほしいと思っています。それとともに、切った木は、ただ切るだけでなく、切った後に材として利用するところまで意識を持ってもらいたいと思って、薪づくりをしたり、自分たちの使う丸太ベンチをつくったりしました」


いろんな人たちとの関わり(コーペレーション)が、コレンジャーの体験を豊かにする
森の子コレンジャーの活動では、森林レンジャー4人だけが子どもたちと関わるわけではない。子どもたちから“しのき”と呼ばれる、小宮ふるさと自然体験学校の校長の篠木眞さんは、各地の里山で子どもたちと自然体験活動を実践してきた人だ。名刺の肩書には「写真を撮る人・子どもと遊ぶ人」と記され、あくまで子ども目線に徹している。長年の経験と知識と人間性で強力なサポートを得ていると、加瀬澤さんも頼りにしている。
市の職員も、全体の安全管理を担う“かちょう”(環境政策課の課長・吉澤桂一さん)をはじめ、緊急車両の手配など裏方作業を担当する“ジョージ”(環境の森推進係の大久保丈治さん)、コウモリセンサーなどの機器を駆使して生き物をとらえる“さくちゃん”(環境の森推進係の櫻澤さん)の3人が毎回の活動に出てきて、子どもたちとも直接関わる。
自然学校の向かいの森の所有者の大須賀さんも、都合がつく限り顔を出してくれている。もともと自分の子や近所の子に自然を体験させたいと森を買ったという。山の上の方に行くのに森を通らせてほしいとお願いに行くと、「だったら自由に使って構わない、一緒にやりましょう」と言っていただいた。
旧小宮小学校の周辺の人たちも、閉校して子どもたちの姿が見られなくなって寂しいと、森の子コレンジャーの活動に協力的だ。地域の整備などでお手伝いできることがあれば、森の子コレンジャーの活動でうまく関わりを持てるとよい。
「森の中で作業をしたり、生き物を見つけて観察したりということも大事ですけど、森と共に生きる人たちの暮らしにも触れてほしいと思っています。森林レンジャーとして地域の人たちと関わってきて私たちが学んだことを、子どもたちにも届けたいと思っています。森林レンジャーが伝えられることと、地域の人たちが伝えられることとはまた違ったものがあると思います。そういう場もつくっていきたいですね」
森の散策では、時に昔道を通る。炭焼き窯の跡地など、森と人との関わりの痕跡、今も現役で使っている人の暮らしの断片を見て、そうした暮らしとの関わりを、今後みんなで考えていく森づくりのヒントにしてほしいと、加瀬澤さんは言う。



昼と夜の境目を感じてもらいたい
冒頭で紹介した7月の「夜の森の散策」は、夕方6時に小宮ふるさと自然体験学校を出発、森林レンジャーのパブロを先頭に、養沢川の右岸沿いの道を歩く。子どもたちの間に森林レンジャーや職員が入る。時折車が通るから、道の左側を一列になって歩くようにと指示がある。
途中、石垣の排水パイプの中に隠れているカエルを発見する。
「こういう隙間にいろんな生き物がいるんだ。昼間だったらヘビなんかも入り込んでいる」
そんな説明に、パイプの中を一つひとつのぞいていく子どもたち。
「カブトムシの死骸があった!」「ガがいたよ」と、いろんな発見がある。


川を挟んだ対岸の森の木の枝に、大きなアオサギが止まっているのが見える。しばし立ちどまって、対岸を眺める。子どもたちは、少し進んでは立ち止まってのぞき込んだり眺めたりと、好奇心の赴くままに行動するから、列は縦に長く伸び、最後尾と先頭は大きく離れてしまう。
森の中では、普段、森林レンジャーが定点観測しているムササビの巣穴がある木を眺めて話を聞いたり、タヌキの溜め糞場を見たりする。草笛の吹き方や草鉄砲遊びも習ったし、大きなホウの葉のお面の作り方も教えてもらって、さっそく被ってみる。
峠を越えて林道に出てから、全員が集まる。“さくちゃん”がコウモリセンサーを取り出してきて、人の耳には聞こえないコウモリの超音波を捕捉してみせる。
「コウモリの種類によって声の高さが違うんだ。今みんなが聞いたのは、20kHzだから…町によくいるコウモリじゃないんだけど、実は、コウモリは、シャッターの間とか屋根の中とか、そういう隙間が大好きなんだ」


すっかり暗くなった中で、ライトを消して静寂の時間を感じる時間を取る。予定では1人ずつ離れてしゃがみ、3分間じっくりと静かに過ごす時間を取るつもりだったが、少し時間が遅くなったため、1分間に短縮する。
子どもたちを集めて、しのき(自然学校長の篠木さん)が話をする。
「みんな、腰掛けられるかな? うん、しゃがんで見て。ライト消してくれる? はい、ライト消して! ご協力、お願いします」
しのきが、本のページを開いて、子どもたちに見えるように掲げる。翼をひろげたフクロウが巣で待つ雛のもとにネズミをくわえて戻ってきた瞬間を大きく写した、写真絵本だ。
「本を持ってきました。フクロウがネズミを捕まえて、子どものところに運んできたところです。これ、しのきが写しました。フクロウは、夜にエサを採って、夜活動する生き物でしょ。それなので、この写真を撮るために、ちょうど今のみんなと同じように、静かに音を立てないようにして一人で暗い森の中にいました。」
撮影の準備を終えたのが夕方の6時。それから写真を撮った11時45分までの約6時間、物音一つ立てずに、じっとフクロウを待ったという。
「音を出したり懐中電灯を照らしたりしていると、フクロウに気が付かれます。一切、音を出さないで待っていました。(小声になって)そうして待っていると、巣の近くの止まり木に、エサを持ち返った親のフクロウがス~ッと飛んできて、『フイッ、フイッ』(そちらは大丈夫ですか?)って声を出すのが聞こえたんです。そしたら、木のうろの中の子どものフクロウも、『フイッ、フイッ』(大丈夫ですよ)って合図を返したんです」
両方の音が消えて、一瞬静寂に包まれた。フワッと、まったく音のしない状態で、親鳥がうろの中に入り込んでいったという。
「今日は、その練習をします。1分間、な~んの音も出さないで、静かにしてみてください。はじめるよ。もう、音の出ない姿勢にしてください。ガサゴソいうようなのはダメですよ」
スタートとつぶやくしのきの声が静かに響く。子どもたちは皆、声を押し殺してうずくまる。
「30秒…(シーン)…51、52…。(ささやくように)はい、60秒間、ありがとうございました。こういう状態で、5~6時間待っているんです。今日は時間があまりないので、詳しい話はまた今度しますね」
皆立ち上がり、ヘッドライトを点けて、出発準備をする。
林道を歩きながら、つい今しがたの1分間について話を聞いてみる。
「あのときね、音を出しそうになって、ぐっと(息を止めて)ガマンしたの。時計があったから見てたら、あと10秒だったから、何とか堪えて、プハーッって、ちょうど1分の時に出して、大丈夫だった」
そう言って、息を止めるように話をしてくれる。

夜の森散策のクライマックスは、沢床に降りて見るホタルの舞だ。
ザーザーと沢の水音が響く中、対岸をふわりと飛ぶ緑色の光が見える。
「あ、あそこにもいた!」
「こっちにもいるよ」
「すっご~い。初めてだ、こんなの!」
点滅しながら飛んでいるホタルがそこかしこに見られる。
加瀬澤さんは、今回の「夜の森の散策」のねらいをこう話す。
「夜の森をずっと歩くわけではなくて、昼間と夜の境、その中での山道や森を感じてもらいたいんです。肝試しみたいな感じで子どもたちは盛り上がっていたし、あまりじっくりと感じられるような人数ではなかったですけど、でも夜の森を歩くという体験自体が彼らにとってよい経験になったと思っています。何かを学ぶというよりも、やったということで感じてもらうのでよいのかなと思っています。もちろん、こっちの気持ちとしては、夜の音を体感してほしいとかあるんですけどね。まあそれぞれに感じてもらえることがあればと思っています」
夜の森での体験も、一年間の森の子コレンジャーの体験も、すぐに子どもたちの身になるものばかりではない。むしろ、大きくなっていった時に、原体験として何か残るものがあればよい、そんな思いだろう。
野帳にメモした生き物の名前や森林レンジャーに教わったことの多くを忘れてしまったとしても、あきる野の森でコレンジャーの仲間たちと過ごした日々のことを忘れることは決してないのだろう。

本日のプログラムはすべて終了!



