【第15回】日本のビジネスの中心地から環境行動の新たなモデルを発信 ~「みなと環境にやさしい事業者会議」の取り組み(みなと環境にやさしい事業者会議)
2012.08.15
みなと区民の森から生まれた大きな木のハコ
浜松町駅から徒歩5分ほど、壁・天井・床や家具に間伐材をふんだんに使った「港区エコプラザ」(浜松町1-13-1)は、木の香りに満ちあふれ、高い天井が開放感たっぷりの空間を作り出している。港区のこの環境学習拠点は、かつて虎ノ門3丁目にあった前エコプラザを2008年6月に移転して開設した、人呼んで“大きな木のハコ”。旧神明小学校の跡地を利用した施設で、内装材には、あきる野市にある「みなと区民の森」(あきる野市戸倉字刈寄谷)から伐り出した間伐材を使用している。
普段は、ライブラリーのある「サーチング・ルーム」、ワークショップや体験学習などに使われる「ワーキング・ルーム」、セミナーなどが開催される「ラーニング・ルーム」という3つの“ハコ”に仕切られている1階スペースは、仕切りを取り外せば350人収容のオープンスペースになり、大イベントの会場にもなる。3つの“ハコ”をまたがって大きな棚が大空間を貫き、そこにも合計200個近い数の大小の木のハコが積み重なっている。自然界にない四角いハコを人の手と知恵の象徴ととらえ、人の力で環境を取り戻していくというこの施設のコンセプトを具現化しているという。
この港区の環境学習拠点で、毎年5月に「みなと環境にやさしい事業者会議」(以下、「mecc」とする)の年次総会が開催されている。港区の呼びかけで2006年にスタートしてから、今年(2012年)5月の総会で7年目を迎えた。
事務局を請け負うNPO法人アースデイマネー・アソシエーションの嵯峨生馬さんと、同区担当の若杉健次さんと北野澤由香さんに話を伺った。

港区の特性を生かして、区民の環境行動を促進
2006年5月に29の事業者の参加を得てスタートしたmecc(みなと環境にやさしい事業者会議)は、2012年6月末現在で会員数67事業者にまで広がりをみせている。港区に本社や事業所がある企業などが名を連ねるほか、大学機関や業界団体の支部なども参加している。港区も会員事業者の一つだ。会員一覧を眺めると、港区ならではの特性を生かしたmeccの特徴が浮かび上がってくる。
港区は、国内でももっとも多くの企業が本社を構える地の一つで、いわば日本のビジネスの中心地といえる。新橋駅前のSL広場から中継されるサラリーマンの街頭インタビューで知られるように、新橋・虎ノ門・芝周辺は特に経済活動が活発なオフィス街だ。青山・赤坂などの商業エリアや汐留・芝浦・港南・台場などの大規模開発区域もある。
そんな港区ならではの特性を生かして、区民の環境活動・行動の促進につなげていこうというのが、meccのそもそものねらいだという。つまり、区民が環境行動を選んだり、環境イベントに参加したりするときにメリットを得られるような仕組みをつくること、そのメリット提示の場面で企業の協力を得ると同時に、それが企業の環境情報の発信へとつながるような仕組みをつくっていく、そんな発想だ。
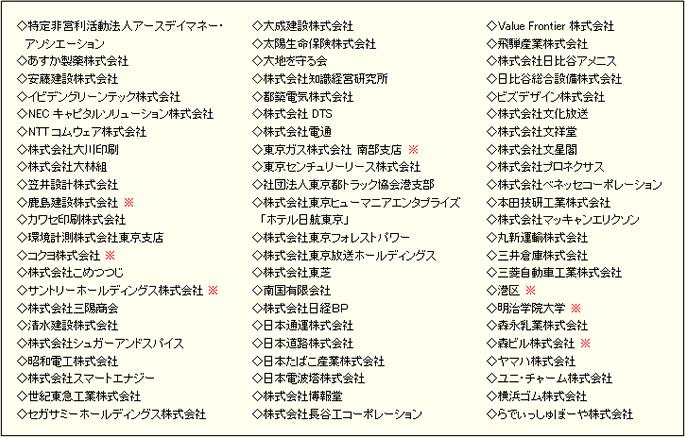
立ち上げに当たって、会員への参加を呼びかけるため、区内の事業者を個別訪問して協力要請をしたという。区単位の自治体として、中小企業振興などを通した中小企業・団体との関わりはそれまであったものの、ナショナルおよびグローバルな規模で事業展開する大手企業との環境分野での連携は経験がなかったし、いっしょに何かしようという発想自体もあまりなかったという。区内の企業をまわり、説明会を開催して、発足に漕ぎつけていった。
一方、企業側にとっても、業界内で環境について考えることはあっても、地域のつながりの中でさまざまな業界の企業が集まって環境のことを考える場は、あまり他に類を見ないと口を揃える。
本社や事業所が“港区にある”という縁でつながっているのが、meccの枠組みだが、企業──特に大企業──にとって、首都・東京に立地しているという意識はあっても、それが“港区にある”という発想にはそれまであまりなっていなかったという。meccに参加して“港区にある企業”という立ち位置ができたことで、地域の中の企業としての存在が認識できるようになってきたという効果もある。
港区環境リサイクル支援部環境課地球環境係長の若杉健次さんは、こうした企業とのつながりが港区にとってかけがえのない場になっていると話す。
「港区が呼びかけて設置されている任意団体ですが、これだけの事業者さんが集まって、しかも自発的な活動を継続していくというのは、非常に希少な場だと認識しています。meccのつながりを通じて、会員事業者の皆さんが地域に入り込んで地域社会との連携を保っていけるような仕組みづくりが大事です。それとともに、企業間の交流・連携なども──二次的なものではあるのですが──、大きな可能性が見出せます。結果的にそれで区内の環境活動が活性化していますから、meccの存在意義はとても大きいですね」


「みなとモデル」の創出へ
現在、meccでもっとも力を入れているのが、毎年秋に開催している「企業と環境展」だ。会員事業者による区内外での環境への取り組みを幅広く発信する場として、2006年の発足以来、毎年開催してきたもので、2010年からはそれまで港区エコプラザで開催されていた展示中心の内容を、セミナーやワークショップを中心により活性化したイベントへと衣替えしてきている。会場も、人通りが多く、賑わいのある六本木ヒルズを借りての開催となった。会員事業者の一つでもある森ビルの協力によるものだ。


「企業と環境展」(会場:六本木ヒルズ)の様子。


来場者には、meccの活動の一環として育てた有機無農薬の「mecc米」をプレゼント。
4日間の会期では、初日にオープニングセッションとなるリレートークやパネルディスカッションが開催され、その後も連日のワークショップや小規模セミナーが数多く企画されている。常設展示では会員事業者が環境に配慮してつくっている製品の模型を展示したり、会員企業が発行する環境報告書・CSR報告書を展示したりする他、2011年には国産材を使った木質オフィスのモデルルームを展示する「森のオフィス」の提案もしている。
この「森のオフィス」の提案は、2011年10月1日からスタートした、国産材利用推進事業「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」の推進につなげるために企画されたものだ。港区内の施設で国産材の利活用を進めることが二酸化炭素の固定に寄与するのと同時に、国産木材を使ったフローリングや家具、壁材で自然に溶け込むような心落ち着くオフィスが実現する──そんな一粒で二度おいしい取り組みを、モデルルームとして目に見える形で示そうというものだ。


「企業と環境展2011」の会場内に展示された「森のオフィス」。フローリング、家具、壁材に飛騨の杉を使っている。
meccが設立当初から掲げる目標(目指すべきところ)の一つに、「CO2削減に向けた 全国に先駆ける『みなとモデル』の創出」がある。事業者と区民と区が連携して新しい協働の場を確立することで、これまでにない環境保全活動の取り組みとなる「みなとモデル」を全国に向けて発信することができる、そんな可能性を秘めたネットワークとしてmeccを育てていこうというわけだ。

2011年10月に始まった「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」は、meccの枠組みで進める事業ではないが、meccのつながりやmeccでの検討が背景にあって実現した仕組みといえる。
その内容は、港区内で床面積5,000m2以上の建築を計画する場合に、一定割合の国産木材使用を義務付けるというもの。国内の森林がきちんと整備され、二酸化炭素を吸収・固定する健全な森として維持されるためには、森林に関する経済がまわっていくことが必要不可欠。大消費地である都心の港区における木材消費を促進することで、経済の環をつなげる役割を担おうというものだ。
mecc事務局長の嵯峨生馬さんは、「みなとモデル」について、次のように説明する。
「港区には、木材産地となる森林はありませんが、“港区らしい木材の使い方”=国産木材の消費を促進することで、産地となる国内の森林を支えていくような仕組みをつくっていけるんじゃないかという発想です。制度自体は一種の規制なんですけど、前向きに捉えれば、この港区エコプラザのように国産木材を活用した、雰囲気のよい建物ができるわけです。これはmeccの事業としてやっているわけではありませんが、meccでの発想が制度の一つのきっかけにもなって、実現したといえるんじゃないかと思っています。そんな新しい仕組みを今後もどんどん生み出していけるような場にしていきたいですね。もっとも、2006年に打ち出して、実際に制度として動き出したのが2011年ですから、時間もかかり、簡単にできることではありません」
きっかけの一つだったエコポイント ~今後のmeccに向けて
meccが立ち上がった当初、区民の環境行動に対するインセンティブを与える仕組みとして導入されたのは、「みんなとエコポイント制度」だった。現在は、2012年3月末をもって休止し、新規の事業を立ち上げた。
同制度は、「テレビ画面は明るすぎないよう設定した?」「お湯を沸かすときはナベやヤカンにフタをした?」「食事は残さず食べた?」「ゴミは正しく分別した?」といったエコチェックの項目を設定して、日々の行動を通じた環境への影響を見直していくというもの。港区立エコプラザの受付で「みんなとエコポイントカード」を発行すれば誰でも参加でき、記入済みのエコチェックカードを見せれば、回答に見合ったエコポイントがカードに加算される仕組みだ。パソコンや携帯電話を通じたオンラインのシステムも提供されていた。
この「みんなとエコポイント」は、前述の通り2012年3月末で休止し、meccの事業としては終了したが、貯めたエコポイントを使える場として設定されていたのが、年に4~5回ほど開催してきた「エコバザー」だ。
5月の環境啓発イベント「エコライフ・フェアMINATO」では、会場の中央でエコバザーを実施するのが恒例となっている。バザーへの出品は、mecc会員事業者の協力によって集められている。例えば、社員向けの頒布品の余剰在庫や、サンプル品や販促グッズの文具やおもちゃ、食器などが並ぶ。中でも人気なのは、会員制食品宅配サービス業のらでぃっしゅぼーやが供出する有機野菜セット。アパレル会社から提供のあった端切れ布も事前の心配をよそに大きな人気を呼んだ。これらの商品を目当てに、毎回多くの人々が集まり、大盛況を呈している。
エコバザーの売上(2011年度は198,870円)は、全額が環境保全に寄付される予定。


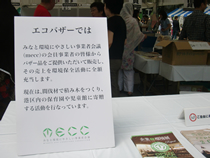
「エコライフ・フェアMINATO2011」内で、毎年恒例の「エコバザー in エコライフ・フェア」を開催(2011年5月21日、有栖川宮記念公園にて)
区民の環境行動促進を目指したmeccにとって、エコポイントは設立のきっかけになったものの、実際に動き出してからは必ずしも中心的な取り組みではなかったという。むしろ、企業間連携と区民に対する直接的な働きかけ──一企業としてはなかなか取り組みづらいことも、meccの枠組みでできることもある──などが中心となって、「企業と環境展」などの形で実施してきている。
今後、区民の環境行動をどう盛り上げていくか、更なる活動の柱について検討している段階だ。
会員事業者も、このところ横ばい傾向にあるものの、区内を見渡せば、まだまだ参加してもらえていない事業者は数多くある。現在は、「企業と環境展」などの機会を通じてmeccに興味を持ってもらったところ、環境に関わる事業で区といっしょに進める機会のあったところなどから地道に広げていっているというが、裾野の広がりはまだまだ見込めるという。
一方で、具体的にどういう活動をして、参加事業者に対してどんな価値を与えていけるかというところの工夫も必要になってくる。
今後のmeccの方向性について、嵯峨さんは次のように話す。
「企業側のニーズや社会的要請が変わってきている中で、地域社会と企業とをつなぐというところで、どういう形が適切なのか。meccが発足した2006年頃の環境活動は普及啓発を主流として意義のあるものになっていましたが、時代も変わって──東日本大震災もありましたし──そうした普及啓発にとどまらない、より実効性のあることをしていかないとならないことを感じています。meccの活動内容も年々変化していくものだと思います。そうした辺りが、これから求められるものになってきていると感じています」
設立から7年目を迎えて、一定の成果も課題も見えてきた。meccの新たな局面に向けた挑戦が、今またはじまっている。




