【第20回】家のすぐ横を流れる川を、遊べて泳げる身近な川にするために ~『目黒川で泳ぎ隊』の挑戦(目黒川で泳ぎ隊)
2012.11.01
大人対象には、「子どもの安全のための指導者養成」と呼びかけて
「目黒川(めぐろがわ)」は、世田谷区三宿を河川管理上の起点とする。本来の源流は武蔵野台地から発する湧水だが、支流の北沢川と烏山川が合流して目黒川となる。世田谷区から目黒区、品川区を通り抜け、品川区八潮の天王洲アイル駅付近で東京湾に注ぐ、総延長8km・流域面積45.8km2の二級河川だ。起点からしばらくは暗渠で、その後もコンクリ三面張りの典型的な都市河川。品川区内の下流域は川幅も広く、両岸には高層ビルが建ち並ぶ。
水質は、下水道の整備などに伴って有機汚濁指標のBODなどは改善傾向にあるものの、水の流れが緩慢なため河床に汚泥が堆積しやすく、水質悪化の原因となっている。また、大雨時には下水道管から雨水で希釈された未処理汚水が流入する場合もある。河口から5.5kmの区間は水位が潮の干満の影響を受けて変化する「感潮河川(かんちょうかせん)」のため、大潮などで潮位変動が大きくなると順流・逆流が発生して川底に溜まった堆積泥が攪乱され、水質の悪化を招く。
都の清流復活事業によって、1995年から新宿区にある都下水道局落合水再生センターから下水道高度処理水が導水されるようになったり、目黒川沿川にある荏原地下調節池内に取り入れた浸出水(地下水)が放流されたりと水質改善の取り組みがされている他、流域3区の共同事業で2008年から高濃度酸素溶解水の注入による浄化実験も実施されてきた。

そんな目黒川で清掃活動などをしている市民団体は、流域の3区内それぞれにいくつかあるが、『目黒川を泳ぎ隊』は品川区を舞台に川の清掃・水質浄化やまちの活性化をめざした活動を実践している。
同会の副隊長を務める原一宏さんは、活動の主旨と目標について次のように話す。
「目黒川は、晴れているときは下水処理場できれいにした水を流していますが、上流で数ミリの雨が降ると未処理の汚水も流入してきます。合流式下水道の問題点ですね。ただ、ハード整備で何とかしてくれと陳情しても、完成するのは数十年先と時間もかかります。だったら、それらの問題を理解した上で、私たちにできることを私たちなりの方法でやっていこうというのがこの活動の主旨です。雨の日にあふれるわけですから、雨の日にはお風呂の水を流さないようにしたり洗濯をちょっとがまんしたりと、みんなが使う水の量を減らしていければ大きく改善できるはずなんですよね。そんな呼びかけもしながら、きれいになった川で、将来子どもたちが安全に泳げるような遊び場をつくりたい。かつてこの川で泳いだり遊んだりするのが当たり前だった頃のようにしていくことが目標です」
意味のある楽しい活動を、子どもたちといっしょに
『目黒川で泳ぎ隊』の実際の活動は、主に子どもたちといっしょに川のまわりのゴミを拾うこと。ただゴミを集めるだけでなく楽しみながらできる活動にしたいと、ボート乗り体験をしたりハゼ釣りや生きもの探しなどをしたりと工夫を凝らす。今の子どもたちは、釣りを経験したことがない子も少なくない。ゴミ拾いをしながら、釣りをしたりボートに乗ったりといろんな体験をしてもらい、身近な川が“遊びの場”になることを肌身に感じてもらうことがねらいだ。もちろん、集めたゴミについても、どんなゴミがどれだけあったのか詳しく調べて、楽しみながらも意味ある活動としてやっていくことをめざす。当初から品川区の協力を得て、集めたゴミはすべて回収してもらっている。
そもそも『目黒川で泳ぎ隊』が発足したのは、今から3年半前の2009年3月のこと。隊長として会を引っ張る大竹幸義さんが、『旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会』の水辺部会長になったのが一つのきっかけになった。
東海道五十三次の宿場として知られる品川宿は、品川区内の京急北品川駅から青物横丁駅周辺にかけて広がっていた。中山道の板橋宿、甲州街道の内藤新宿、日光街道・奥州街道の千住宿と並んで「江戸四宿」と呼ばれた交通の要衝の地として発達してきた。今も祭りが生活の中心になっているこの地域は、歴史と文化に彩られた人情厚いまちだ。
その品川宿独特の環境を後世に残し、東海道の歴史性を生かしたまちづくりを進めることを目的として、1988年に周辺の町会や商店街などが協力して設立したのが『旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会』だ。




現在の会長は、地元でスーパーを経営する堀江新三さん。中世以来の港町・品川湊は、かつて漁師まちとしてアサリを捕って生活していた。昭和30年代の光景だ。現役の漁師だった人たちは、今や70代以上になるが、60代になる堀江さんもその頃の暮らしの情景を記憶にとどめている。品川宿のまちづくりを進めながら、古きよき時代のいろんなことが忘れ去られていく寂しさとともに、今の子どもたちが川から離れていることを残念に思っていたという。
堀江会長から、目黒川で何かしたいと今は副隊長を務める原一宏さんに相談があったのは、5年ほど前に溯る。
実は原さん、NPO水と緑の環境ネットワークの会の副代表理事として、地域外からのサポーターの立場で『目黒川を泳ぎ隊』の活動に関わっている。まちづくりのつながりで堀江さんから相談を受けて、活動の主旨には共感した原さんだったが、イベントを開催してきっかけづくりにはできても、地域の中から思いのある人たちが集まってこないと根付いていかない。
ちょうどそんな頃に、堀江さんに紹介されたのが大竹幸義さんだった。
本業はカレー屋さん社長の大竹さんには小さいお子さんがいるが、家のすぐそばを流れている川には入れない。学校でも「川には近寄らないこと」と指導していたという。なんとかしたいという思いが、互いに響き合った。
当時、流域3区の共同事業で川に酸素を入れる浄化実験をしていたことは地域の人にも知られていたが、他にどんな取り組みがあるのかわからなかった。川の水は、夏になると臭くなるし、水の色も緑っぽかったり白っぽかったりと変化していた。雨が降った後には三面張の川に降りる管理梯子に紙のようなものが張り付いていた。わがまちの川に起こっていることを調べることから始めてみようというのが、最初のとっかかりになった。
地元の人たちと活動をつくっていくに当たって、どんな活動をしたいかと話をする。もともと、学校とまちづくりがうまく連動してきた地域だったから、川に子どもたちを連れてきて、楽しいことをしたいという話が出る。でも、ただ楽しむだけでなく、清掃活動などもしながら、意味ある楽しいことにしたい。そうして、今の活動の方向性が定まっていった。
ボートは、同じ品川区内にポートで活動する「勝島運河クラブ」という団体があって、そこから協力してもらい目黒川に浮かべることになった。使っているボートは「Eボート」と呼ばれ、気軽に遊べる水辺の交流ツールとして開発された天然素材のゴム製の10人乗り手漕ぎボートだ。勝島運河クラブは、普段は立会川の河口にある勝島運河で活動をしているが、インフレータブル(空気注入式)のため、輸送や組み立ても容易だ。
隊員たちは、安全かつ楽しいイベントにするため、座学と実技のEボート指導者講習会も受講している
こうした活動の成果もあって、徐々に「目黒川でも遊べるんだ」と思ってくれる保護者も増えてきているという。
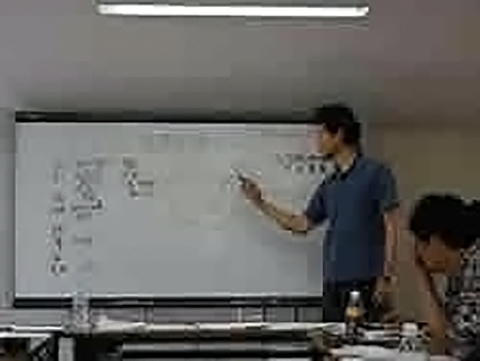



Eボート指導者講習会の様子。午前中の座学では、開発コンセプトと歴史、利用法や乗船の仕方、安全に楽しむための諸注意などをNPO法人地域交流センターの中村俊彦さんを招いて勉強した。指導者講習会の午後の部は、組み立て・収納など取り扱い方とメンテナンス方法、操船練習など空気穴は3ヶ所あり、左右それぞれの側面と船底に対して空気が送り込まれる左右の空気が半分くらいまで入れられたところでイスを設置する。
大人対象には、「子どもの安全のための指導者養成」と呼びかけて
この地域には、小学校が3つあり、地域の人たちは普段から仲のよい付き合いをしてきた。イベントのチラシも、全校生徒に配布してくれるから、3,000枚くらいすぐに配れる。イベントに参加する子どもたちは、ボート体験や魚釣りなど楽しい企画のある日には100人以上集まるときもある。もっとも清掃だけの日になると20人だったりと、なかなか現金な反応だ。
一方、大人の参加者たち対象には、がっつり勉強してもらう。
「例えば、目黒区にあった川の資料館──今年3月に閉鎖になっちゃったんですけど──に行って、目黒川全体のいろんな施設の勉強などもしました。なんで三面張りになっているのかとか、もともと玉川上水とつながっていた歴史を紐解いたり。目黒川は、ちょうど武蔵野台地の末端に位置するんです。武蔵野台地が終わるところにあって、玉川上水の方から世田谷の烏山寺町の方につなげると、もともと水が流れていた旧川に沿って、ちょうどすり鉢状に土地が窪んでいる。江戸時代の後期には、このすり鉢状のところに水が集まってきて、そこに田んぼができていた。なるほど合理的なんだねと、一同、納得しました」
と原さん。こうした内容は、“大人対象のイベント”というと人が集まらないから、“子どもの安全のために必要な指導者養成”という位置づけにしているという。ボートの講習もやるし、心肺蘇生法の講習もある。目黒川の歴史・文化についても勉強する。
こうしたイベントと指導者講習会を月に1度ほどのペースで実施してきた。
「ただ、この活動は、基本的に手弁当でやっているものですから、活動資金を確保するのが大変です。昨年度は助成金が取れていたから、子ども向けのイベントか指導者講習会かを月1回は実施してきましたが、今年は助成金もなく、厳しい状況です」
毎回のイベントは参加費を取っていないし、現在は会費もない。そのねらいについて、原さんはこう説明する。
「品川だけじゃなく、目黒区や世田谷区の人たちともいっしょにできるといろんな知恵も出てきますよね。そんな枠組みができるまでは、会費などが足枷になってしまわないように、うちのNPOの方で工面したりしながら、何とかやり繰りしています」
もともとまちづくりの視点からはじまったものだったから、商圏という捉え方での活動の展開も検討している。
「目黒川の場合、流域に数多くの商店街や企業の本社が身近にあるんです。イベントのときにも来てもらっていますし、準備にも関わってもらっています。これらの商圏の下支えになるような活動が展開していけると、可能性も広がると思うんですよ。そのときに、品川だけでなく、目黒の人たちが参加してくれれば今までのノウハウもたくさん持っていますし、住民の多い世田谷にも参加してもらいたい。経済とうまく絡んだ形で展開できるとよいなと思っています」 これは、最初に堀江さんと話したときにも出てきた話だったという。
具体的には、例えば“流域マップづくり”が一例だ。目黒川の上流から下流までつながったマップがあれば、源流を見てみようとか、河口に行ってみようという人も出てくるかも知れない。このとき、流域の各地にある商店街が紹介されていれば、ついでに寄ってくれる人もいるだろう。お店を紹介するのではなく、商店街を目標物として捉える。それらの商店街をつなぐようにスタンプラリーを仕掛けてみたりと、そんな取り組みが新しい経済の動きを生み出す可能性があると、原さんは言う。
「今の時代、品川もどこも商店街は厳しい状況にありますよね。イベントに来てくれる住民たちは、商店街で買い物をしていて、その商店街がなくなったら困るんですけど、どこかピンと来ていない現実もあります。商店街に足を運んでもらい、少しでも買い物をしていく人が増えるきっかけになれば…。そうしたところで連携しながらうまく絡めていけるとおもしろいんじゃないかと思っています」



年に一度、目黒川を泳ぐ!
目黒川の活動で、一番最初に注目されたのは“泳ぎ隊”という名前の通り、この目黒川で泳ごうというイベントだった。年に一度、毎年8月に実施していて、今年(2012年)で3度目を数える。最初の年は、警察や消防がずらりとやってきたし、マスコミにも取り上げられた。
きれいになってきたとはいえ、底にはヘドロが溜まっているし、底にどんなゴミが引っかかっているかわからない。都市河川独特のニオイもする。大方の見方は、「こんなところ、泳げるの!?」と
これまでのところ子どもたちには泳がせず、隊員の中から志願のあった精鋭メンバー6~8名ほどがライフジャケットを着用して、事前の安全講習を受けて臨んでいる。安全講習では川の泳ぎ方や流されたときの対処方法や溺れたときの救助の仕方なども習う。上下流の両側には地元船宿も協力してくれて万が一の事故等に備える。泳いだあとは身体をきれいに洗い流して、1週間ほど毎日体温を測って体調変化の兆しをとらえるという念の入れようだ。
最初の年は、JR五反田駅近くから河口付近までの3.2kmを泳いだが、1時間半以上かかったため、2年目以降は約500mに短縮した。それでも1時間弱かけてゆっくりと、隊員を中心に6~8人ほどが川の流れに身を任せて漂う。両岸では子どもたちがゴミを拾いながら、川流れの様子を見守る。
「今年の夏は、まとまった雨がそれほど降らなかったから、泳ぐには比較的よい条件でした。両岸の子どもたちといっしょに、水中部隊も川の中のゴミを拾いながら進むんですが、今年は区の職員の方もいっしょに水に入ってくれたんですよ」
まわりの反応──特にマスコミなどでの扱い──は、「こんな川で泳ぐの!?」と奇特な眼差しだが、本人たちは至極まじめに、楽しみながら取り組んでいる。“今泳がないと、誰も注目してくれなくなっちゃう”という危機感もあるが、むしろ泳いでみることで見えてくることもあるだろうと前向きで自然体な様子が伺える。



川の中のゴミを拾いながら進む。

泳いだことを報道されたのがきっかけで、学校の協力が進んだ
目黒川を泳いだことは、地元の人たちに対しても一つの転機になった。 「3校の学校は、今は本当に協力してくれています。1年目はそうでもなかったと思うんですけど、そのひとつのきっかけが、泳いだことを報道されたことだったと思います。それもプラスのイメージではなく報道されたことが。『こんな汚い川で泳いでいるよ』って言われて、何くそという地元意識があったんじゃないですかね」
今年の6月17日(日)、アサリを使った東京湾の水質浄化大作戦に向けた実験を開催した。ビン容器の中に、塩水と海の汚れに見立てた米粉を入れ、片方にアサリを入れて、時間とともに変わっていく様子を比較観察するという内容だ。アサリの放流を前に、その理由を多くの人たちと共有するために企画した。
この話を学校にしに行くと、全校生徒にチラシを配ってくれただけでなく、「これ、おもしろそうだから参加してみたら」と先生が言ってくれるようになった。これはそれまでにないことだったという。
11月には港湾局の許可をもらって、千葉産のアサリ200kgを子どもたちに撒いてもらう予定だ。
アサリを撒くというのが、この地域の親たちにとっては好印象を持ってもらえた一つの理由だったという。


「今の小学生の親世代は、皆、この地域でかつてアサリを採っていたという事実をよく知っています。実際に見ていたわけではありません、生まれたときにはすでに埋め立てがはじまっていましたから。その下の世代になると、そうした事実そのものもしらないようになってしまうのかも知れません。それと、現役で携わっていた方も生存していて、お話ししていただけるという方もいらっしゃいます。その意味で、今が大事なんだろうと思っています」
今を大事に、これからの目黒川に期待しながら、楽しく活動していきたいと話す原さんたち『目黒川で泳ぎ隊』の活動は、一歩ずつ着実なステップを踏んでいっているようだった。



