【第37回】“モニタリング調査”と“保全活動”を一体として、横沢入の湿地生態系を守る(横沢入里山管理市民協議会)
2013.09.02
毎朝、ボランティアが箱ワナを見廻って、外来種による生態系への影響を防ぐ
2013年7月19日(金)、あきる野市の横沢入里山保全地域で、特定外来生物※1に指定されるアライグマ捕獲のための箱ワナの稼動と毎朝の見廻り調査が始まった。同保全地域は、都の「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づいて2006年に初の里山保全地域として指定されたもの※2で、三方を標高300メートルほどの五日市丘陵に囲まれたすり鉢状の谷戸地形にある、流域面積約60ヘクタールの里山。東京西多摩地域のあきる野市中央部に位置し、都心からは電車を乗り継いで1時間ほど、JR五日市線の終点武蔵五日市駅とその一駅手前にある武蔵増戸駅のほぼ中間点から北側に広がっている。駅からは、ともに徒歩約20分の道のりだ。
このアライグマ対策事業は、7月19日(金)から23日(火)までと27日(土)から30(火)までの延べ1週間ほどを稼働期間として、保全地域を管理する東京都環境局多摩環境事務所の事業として実施したもの。ただ、毎朝の見廻りによる捕獲個体の確認やエサ補充等の作業は、横沢入をフィールドに活動している市民団体のメンバーを中心とするボランティアが担当している。同事業の特徴的な点だ。
あきる野市では、アライグマが木造建築の柱をよじ登って建物に侵入した際の爪痕が、市内112軒の寺社等のうち86軒で確認され、市内全域にすみ付いていると推定されている。横沢入でも2010年春からカエル類やトウキョウサンショウウオへの食害が目立つようになった。
横沢入をフィールドに活動する複数の市民団体が参加する「横沢入里山管理市民協議会」の共同代表の一人で、毎朝の見廻り作業を精力的にこなす内山孝男さんは、見廻り作業の様子や意義について、次のように話す。
「センサーカメラを見ると、アライグマは週に1度くらいの間隔で横沢入に入ってきていて、横沢入内で定着・繁殖はしていないようです。この侵入のタイミングとワナの稼動期間が一致しないと捕獲はできません。加えて、エサ取りの上手なタヌキがエサを抜き取ったり、錯誤捕獲でワナにかかったりしたら、ワナの有効な稼動ができなくなってしまいます。地道な作業ですが、毎朝の見廻り時にはその時々の生き物たちとの出会いがあり、目的プラスαの発見や気づきを得ることもできます。なにより、アカガエルやトウキョウサンショウウオなど湿地を生息環境にする両生類の壊滅的な被害を防ぐためにも大事な役割なのです」

ワナ18基の稼働を開始。閉鎖してある
侵入口を開け、エサを撒いてセットする。

部分を踏み込むと、扉が閉まる仕組み。

さっそくかかったタヌキの幼獣。

エサだけ抜き取られているワナも見られた。
同市民協議会は、1989年に発表された五日市町(当時)の長期総合計画による住宅開発計画がきっかけとなり、2001年に発足した市民ボランティア団体だ。開発計画はバブルの崩壊によって採算性の見込みが立たなくなったため2000年に中止が決定したが、耕作放棄された水田跡地は植生が遷移して乾燥化し、湿地生態系に大きな影響を及ぼしていた。90年代後半から、いくつかの市民団体が湿地環境保全の取り組みを始めていたが、各団体がバラバラに活動しているのでは適切な保全活動ができないと、それぞれの保全活動の調整を目的に組織された。同地区が2005年3月に東京都へ無償譲渡されると、翌2006年1月に都で初めての「里山保全地域」として指定されることになった。市民協議会は、横沢入里山保全地域をフィールドに活動する緑地保全登録団体の一つであり、すべての緑地保全登録団体が加盟する協議会でもある。


春先の定期調査で見つかった、カエル類やトウキョウサンショウウオの死骸 ~アライグマによる捕食の影響
横沢入でアライグマ対策事業が始まったのは、2010年9月に遡る。横沢入では、季節の折々にさまざまな生物調査等を実施していて、湿地を中心とする地域内自然生態系の状況の把握と保全のための取り組みをしている。春先には、毎年アカガエルやトウキョウサンショウウオの産卵状況調査を実施しているが、2010年の春先は、ある異常な光景が見られたという。湿地のあちらこちらで、水辺に産卵に訪れたアカガエルやトウキョウサンショウウオの死骸が発見されたのだ。現場の状況等から、アライグマによる捕食と推定され、市民団体の連名による都環境局に対する緊急要望書が提出された。これに呼応する形で都が委託した業者によるアライグマ捕獲のための対策事業が始まることになったのが2010年9月。この年の秋に3基、翌春には8基に増やした箱ワナを合計32日間稼動させ、アライグマの成獣3個体を捕獲した。翌2011年度は、最大13地点26個の箱ワナを7月から翌3月までの毎月1週間ずつ仕掛けて、アライグマの成獣5個体とハクビシンの成獣2個体を捕獲している。
2012年度には、限られた予算を最大限生かして継続的に展開できる方法を試行するため、都が箱ワナ20基を購入し、横沢入をフィールドに活動する団体がボランティアとして見廻り作業等を担当し、捕獲を確認した際に獣医資格を持つ専門家を呼んで殺処分等するという新たな連携体制での事業を開始した。同年度の実施日数は68日間、稼動した箱ワナ18基によって、アライグマ7個体とハクビシン2個体を捕獲した。2013年度は6月から開始し(6/18~6/26)、すでにアライグマ2個体を捕獲している。さらに今回7月の稼動(2013年度の第2回)では、延べ37人のボランティアが毎日の見廻り作業に参加して、アライグマ4個体(すべてオスの成獣1および幼獣3)を捕獲している。
域内のアライグマの侵入状況は、センサーカメラや湿地に残る足跡によってボランティアたちが日常的に把握しているから、効率的な捕獲につながっている。タヌキやアナグマなどの錯誤捕獲も生じるが、これらはその場でリリースしている。
1回の連続稼動日数は約1週間。夜行性の動物たちだから、毎朝なるべく早いタイミングでワナの状態を確認してやる必要がある。稼動時期や期間は、捕獲後の個体の殺処分ができる獣医等が対応できる日程の中で調整している。ボランティアが毎朝の見廻り、捕獲した場合の殺処分を獣医が担当するという役割分担によって、限られた予算で最大限の効果を上げようという体制を組むわけだ。季節を変えながら、どの時期にワナを稼動させればより効率的な捕獲や効果的な個体数削減が実現するか、モニタリングを兼ねた対策事業となっている。


を見つけることはできなかった。


調整したり、稼動期間を検討したりしている。
横沢入の湿地に依存する動植物の生態
横沢入で季節の折々に実施している生物調査は、カエル類やトウキョウサンショウウオなどの両生類を始め、ヤマトセンブリ、トンボ、チョウ、ホタルなどの昆虫類、カヤネズミなどの哺乳類など、広範にわたる。どれも、横沢入という湿地生態系にとって重要な指標種※3であり、これらの生物調査がベースとなって、湿地復元やヨシ刈り払いといった保全活動が計画・実施される。
トウキョウサンショウウオ調査では、春先に湿地の水溜まりに産卵された卵嚢(らんのう)の数をカウントして、地図上に位置をプロットする。市民協議会の構成団体でもある西多摩自然フォーラムが1994年から実施しているこの調査では、毎年800個ほどの卵嚢が確認されているが、2010年には約500個に激減。先にも紹介した通り、アライグマによる捕食と推定されたカエル類やトウキョウサンショウウオの死骸が多数確認された年だった。その後、アライグマ捕獲が功を奏したのに加え、湿地復元による生息環境の拡大などによって、トウキョウサンショウウオの生息数も回復してきているという。
日本の国蝶でもあるオオムラサキは、文字通り紫色をした大型のチョウ。里山の明るく開けた雑木林を好んで生息しているが、近年は開発等によって生息適地が減っている。特に都市近郊では見られなくなった地域も少なくはない。幼虫はエノキの葉を食べて成長し、冬には木の根元の枯葉の裏で越冬するから、冬に越冬している幼虫を数えている。横沢入には、径10cm以上のエノキが約70本確認されているが、長年の調査から、毎年幼虫が発生する木と、年によって発生個体数の変動が大きい木、そして発生しない木に分類できることがわかってきた。ある年に30頭の幼虫が発生した木が、その翌年にはまったく見られないということもあった。単年もしくは短期の調査では、結果の考察を見誤る可能性もあるが、経年調査の結果を見れば、すぐに慌てなくても済む。主な発生木を中心に、毎年20~40本のエノキを調査して、100~200頭の越冬幼虫が確認されている。
ホタル調査は、保全地域内の湿性地を中心とした区域に複数の調査ルートを設定して、それぞれ時速1㎞ほどのゆっくりとしたペースで歩きながら目撃したホタルの個体数と確認状況(飛翔、交尾等)を地図上に記録するもの。日が落ちてホタルの飛翔が始まる19時半前後から歩き出し、ルートを往復して行き帰りのそれぞれ2回ずつ記録を取っている。2006年1月に都の保全地域に指定されて以降、田んぼの復元・整備と草刈り、畔の補修等には積極的な手入れがされてきたが、ヨシ原などを含む湿性地の手入れ作業にはなかなか手が回っていないという。ホタルの発生時期や分布密度などをプロットして、湿地の状態や植生管理のための判断材料を得ようというのが目的だ。
カヤネズミは、大人の親指ほどの体長で、500円玉ほどの重さしかない、日本のネズミで最小の一種。イネ科の植物などの葉を丸めて特徴的な球状の巣をつくって子育てする。横沢入では、オギやヨシ、ススキの群落、背丈の低いスゲなどに巣をつくっているのが観察できる。2007年以降、カヤネズミの子育てが終わった秋口から初冬にかけて、巣跡の個数と位置、巣材の種類などを調査して、毎年百数十個の巣跡を発見している。この結果から、巣づくりの状況と環境変化との関係などを考察し、その後の保全活動を計画するための検討材料にするわけだ。



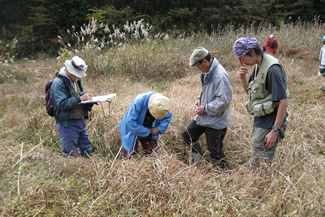
“モニタリング調査”と“保全活動”が一体となって守られている、横沢入の湿地生態系
こうしたモニタリング調査は、湿地の保全活動を計画・実行する上で欠かせないデータとなる。
保全活動は、例えば湿地の復元作業がある。かつて棚田がつくられていた谷戸も、長年放棄されてきたことで、乾燥化して陸地化が進行している。畔が崩れて、水が溜められなくなって、植生が遷移しているのだ。そこで、水田跡に積もった土砂をスコップでかき出し周囲に積んで畔を復元する。水の流出が押しとどめられると、たちまち水がたまって、湿地性の動植物の生息・生育環境ができる。
保全地域内を流れる横沢川本流の河床保護のため、大雨時の雨水と土砂を引き入れる遊砂地の定期的な浚渫(しゅんせつ)作業も毎年冬の恒例作業になっている。
草刈り作業はさまざまなところで実施している。乾燥化してきた湿地帯に繁茂する植物を刈り払って陸地化の進行を抑制したり、外来植物を根っこから抜き取って駆除したり、水路や沢を覆うように伸びてくる草を刈りトンボやホタルなど水面を好む生物の生息環境を整えたりしている。7月の共同作業日には、水路を覆うように繁茂しているヨシなどの草を刈り取って、水面を露出させる作業に勤しんだ。エンジン付き刈り払い機や鎌で草を伐って、レーキやフォークで寄せ集めてひとところにまとめる。草が伸びる夏の日の作業だから、体力も消耗する。作業は午前中で終わらせて、午後は鎌砥ぎなど道具の手入れに当てている。




| 日付 | 午前の活動 | 午後の活動 |
|---|---|---|
| 2012.4.20 | 中央南側湿地ヨシ抜き | セイヨウタンポポ・セリバヒエンソウの駆除 |
| 2013.5.18 | 下の川のヨシ抜き | セリバヒエンソウ等の駆除 |
| 2013.6.9 | ホタル調査ルートの草刈り | ─ |
| 2013.6.15 | オオブタクサ抜き取り | カナムグラの根抜き駆除 |
| 2013.7.20 | 下流部横断水路の草刈り | 鎌、ノコギリ手入れ |
| 2013.8.17 | オオブタクサ刈り取り | 猛暑のため午後はなし |
| 2013.9.21 | 中央南側湿地草刈り | 水生生物調査とザリガニ駆除 |
| 2013.10.19 | 下の川湿地草刈り | カヤネズミ調査のための研修 |
| 2013.11.16 | カヤネズミ調査 | 午後も調査継続 |
| 2013.12.21 | 遊砂地の草刈り | (未定) |
| 2014.1.18 | 宮田西沢奥の倒木整理 | (未定) |
| 2014.2.15 | 遊砂地の浚渫 | (未定) |
| 2014.3.14 | 本流・下の沢合流点周辺の草刈り・ヤブ払い | (未定) |
毎月第3土曜日、午後10時に集合して作業を開始する。横沢入里山管理市民協議会は、横沢入で活動する緑地保全登録団体の一つでもあり、同時にすべての緑地保全登録団体が加盟する協議会でもある。
こうしたモニタリング調査と保全作業の一体的な計画・実施をしていくことで、湿地生態系の状態を常に把握し、作業の影響と効果を測っていくことができる。計画の進捗状況の点検と見直しを行いながら、保全活動を進めていく、このような管理手法を「順応的管理」※4と呼ぶ。
作業が自己目的化してしまうと、身体を動かしてよい汗をかいても、当人の健康管理に役立つだけで、自己満足にしかならない。藪を刈り払ってすっきりしたと満足したのが、実はある生物にとって重要な生息環境を破壊してしまっている可能性もある。まわりに似たような環境がたくさん残っていれば影響も少ないかもしれないが、横沢入はまわりが開発されていった中で残された貴重な湿地生態系が残る、いわば“最後の聖地”といえるから、そこで消えることは東京からの絶滅につながる可能性もある。
そんな責任と覚悟を負いながら、横沢入を舞台にした湿地生態系保全の取り組みは今日もまた続く。


