【第64回】地域の太陽光発電事業から生み出される収益を、地域に還元(一般社団法人調布未来(あす)のエネルギー協議会)
2015.10.01
調布市内の34箇所に分散するメガワット発電所
2011年3月11日の東日本大震災を契機に、再生可能エネルギーへの関心と期待が高まっている。中でも太陽光発電の伸びは目覚ましく、2000年に33万kWだった国内累計導入量は、2013年には1766万kWと大きく伸展した。都心部では地上設置のための土地確保が難しいため、屋根の上などに設置するのが一般的で、広い面積が確保できる公共施設の屋根は格好な設置場所として注目を集める。各地の地方自治体等でも、普及拡大や分散型電源の確保、行政財産の有効活用などを目的に屋根貸し太陽光発電事業の公募も全国的な広がりを見せている。
調布市では、公共施設の屋根34箇所で総出力約1MWのメガソーラー事業が2014年6月より稼働している。賃料無料でこれらの屋根を借りて事業を実施しているのが、調布まちなか発電非営利型株式会社。地域主導の再生可能エネルギー活用事業を進めるとともに、20年間の発電事業で生まれる収益は、すべて地域貢献事業として還元する計画だ。この調布まちなか発電非営利型株式会社の母体となっている一般社団法人調布未来のエネルギー協議会代表理事の小峯充史さんと事務局の稲田恵美さんに話を聞いた。

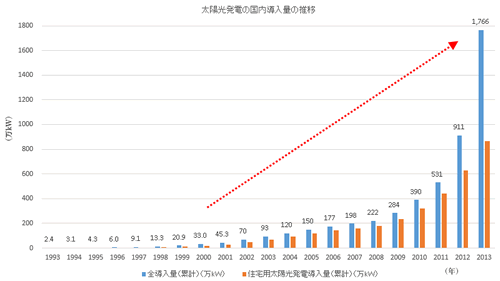
「東日本大震災が一つの契機になって、エネルギーや環境に対する専門的な知識と関心が世の中に顕在化してきたことを感じています。私自身も、それまでは地域のボランティア活動の一環として、枯渇性エネルギー※1 の大切さを訴えてきましたが、そうではなくて、社会全体が再生可能エネルギーにシフトしていかなくてはならないと思うようになりました。2012年4月には地域活動をしてきた仲間たちとともに『持続可能な地域を創出する会』という任意の勉強会を立ち上げました。再生可能エネルギーへの関心と見識を深めていく中で、全国のエネルギー事業者とのネットワークもできてきました。ちょうどその年の7月からスタートすることになったFIT※2を受けて、調布市内での再生可能エネルギー事業の実施に向けて市役所と協議を始めました。この事業を、地域の市民の人たちといっしょに運営していくための体制を作ろうというのが、一般社団法人調布未来(あす)のエネルギー協議会設立の目的です」
協議会設立までの経緯について、小峯さんはそう話す。
小峯さん自身も、2012年7月にそれまで勤めていた会社を辞めて、環境・エネルギーコンサルティング会社である株式会社エコロミを立ち上げて独立している。この会社を受け皿にして、当時環境省が公募した「平成24年度地域主導型再生可能エネルギー事業化検討委託業務」※3の採択事業の一つに選定されたことで、調布の中でできる再生可能エネルギー事業を検討する枠組みができるようになった。




公共施設の屋根を借りた太陽光発電事業と、生み出された収益の地域還元の仕組みづくり ~非営利型株式会社と一般社団法人
調布未来のエネルギー協議会の取り組みで特徴的な点の一つに、協議会とは別に非営利型株式会社による発電事業会社を立ち上げていることがあげられる。
「協議会は、事業化の検討をしたり、啓発活動をしたりする、市民の方々が集まる協議体、つまり会議の場なのです。実際の事業に対して協議会が責任を持つのは荷が重いため、発電事業は調布まちなか発電非営利型株式会社という、調布市内の公共施設の屋根を借りて実施する太陽光発電事業に特化した別会社を2013年5月に設立しました」
小峯さんの会社エコロミでも太陽光発電事業を実施しているが、地域貢献を目的とした非営利事業として実施するために、あえて別会社である調布まちなか発電の事業として切り分けて、公平性・透明性の担保につなげることにしたという。非営利型株式会社というのは、通常の株式会社が経済的利益を最大限追及して出資者(株主)に配当するのが目的の一つになっているのに対して、地域の活性化など社会的利益を生み出す事業へ参画することを目的として謳ったもの。定款上で、配当可能な剰余金の全額を社会貢献積立金として活用することを定めている。
「この会社の資本金は1千万円ですが、そのうち990万円を数人の株主の出資で集め、残りの10万円分を一般社団法人調布未来のエネルギー協議会が出資しました。ただ、990万円を出した数人がNOと言っても、10万円を出した協議会がYESと言えばYESに決まるという仕組みにしています。つまり、株主のうち、990万円を出した数人は単にお金を出すだけで、10万円分の株式を持つ協議会の意見によって、社会貢献積立金の使途などを決定するわけです」
出資者は、多い人で1人当たり400万円ほど出資している。配当は付かないが、地域が潤うことで、出資した人自身にとっても住みよい環境づくりにつながればという思いが込められている。

エネルギーに対する興味や関心を高めて、住みよい地域にしていくのが目的
公共施設の屋根に設置したパネルは順次稼働をはじめて、2014年6月からフル稼働している。月別の発電量は、協議会のホームページにも掲載されている。
当初の構想では、最初の1年で1MWの設備を立て、さらに2年目・3年目でそれぞれ1.5MWの設備を立てる3年計画を立てていた。1年目は順調に事が進んだが、2年目以降は、FITの買い取り価格が下がり、経営の安定化と、最終的な地域貢献のための収益確保のため、現在の約1MW以上の設備開発はしないことが決定された。
「以前は、公共施設の屋根を借りて設置する太陽光発電所を毎年少しずつ増やしていく構想がありました。市内のエネルギーを少しでも自給的にまかなっていこうというビジョンです。1年目は計画通りに進みましたが、2年目以降の計画はFITによる買取価格が下がったことでとん挫した形になりました。ただ、いずれにしても発電事業だけで終わりにするつもりはなく、あくまでも発電事業は手段の一つに過ぎません。今後はエネルギーに対する興味と関心を醸成することで、住みよい地域づくりへとつなげていくことに力を入れていきたいと思っています」
地域還元として、まず計画しているのは、公共施設における電力消費の見える化事業だと小峯さんは話す。
「太陽光パネルを設置した施設の半分は市営住宅ですが、残りの半分は、公民館や図書館などの公共施設や保育園や児童館をはじめとする社会福祉施設などです。これらの施設で、電力の見える化事業を実施することを計画しています。つまり各施設でどれだけの電力を使っていて、どんなところで無駄があったり節約できる余地があったりするのかというのを検討しながらフィードバックするのです。さらにそうして検討した結果から、省エネ施策の一環として設備を交換する際には私たちの基金を使って実際に取り入れることもできますし、設備交換によるコスト削減が大きな効果を生んだ場合には、ESCO事業※4 のように浮いたお金の一部から設備交換にかかった費用を戻してもらうことも考えられます。いずれにしても、最初の計測と見える化の事業については、発電事業の収益を活用して実施する予定です」
太陽光発電事業は、開始当初は支出が嵩(かさ)むものの、10数年かけて借金を返済し終えると利益が出る仕組みになっている。34か所の発電設備の導入には3億円ほどの設備投資を要した。運用開始後にも利子の返済や日々の管理費、メンテナンス費用などの支出が発生する。ただ、ちょうど15年で返済を終える計画になっているから、その後は諸経費を差し引いた利益のすべてを地域に還元することができる。
「最初の15年間は借金返済に充てなくてはなりませんが、その後は毎年1千万円ほど、調布市のエネルギー改善のための調査や事業実施に使える予定です。それと、調布市は意外に緑が残っているんですよ。市域の3分の1ほどは田んぼや雑木林、畑が残っていて、それらの緑を守るために市でも基金の積み立てをしています。その基金にも、収益が出てから年間約500万円ずつ、計2千万円くらいの寄付を予定しています。公共施設という公共の資産を使わせてもらって、そこで地域の人たちが発電事業を実施して、そこから生み出されたお金で、また地域の環境を保全していったり、地域のエネルギー事情の改善に役立てたりしていこうというのが、ここ調布のやり方なんです」
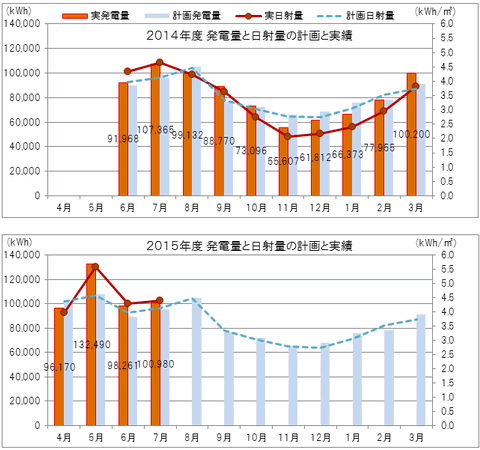
調布市内公共施設発電実績レポート。(最大出力合計925kW)
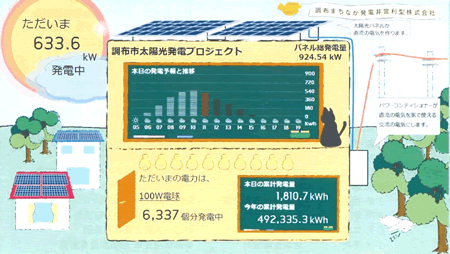
調布市内の学校で、出前授業を
各施設のエネルギー消費量の見える化事業とともに当面の事業として計画しているのが、市内の小学校への出前授業をはじめとする環境・エネルギー学習の取り組みだ。
「今年力を入れているのが、調布市内の小学5年生を対象にした、出前授業です。まだ実際には動き出していませんが、夏休み前の7月の校長会で企画提案書をお配りしました。今年度はすでに各学校の年間計画も決まっていて実現できるかわかりませんが、来年度以降の実現も視野に入れて、実施のための教材もほぼ完成しています」
出前授業の講師役は、協議会のメンバーに担当してもらう計画だ。経費や講師謝金は、発電事業の収益から用意するため学校側の費用負担はない。調布市には市立小学校が20校あって、それぞれ2~3クラスあるから、5年生のクラスが50~60ほどある。まずはそのうちの20クラスでの実施をめざしていきたいと小峯さんは話す。
テーマは、電気と温暖化。自転車発電による電力量を、家電1つや家1軒・1日分の電力などに換算して感覚的に理解してもらうことを導入とする。その上で、学校の中の電力使用量や省エネなどの取り組みについて調べ、それぞれがまとめて発表する。最後に協議会の取り組みを紹介し、ごく身近で再生可能エネルギーの発電の取り組みがあることを知ってもらう。総合的な学習の時間の授業2コマで終わるように設計したプログラムだ。
学校への出前事業はこれからの構想だが、親子教室やセミナー、屋上施設の見学会などはすでに何度か実施している。
「私たちの活動の根本にあるのは、震災があった時に電気が使えなかった経験や脱原発への思いだったりするところは間違いありません。ただ、あまりそれを表に出してしまうと、会員の幅が狭まってしまいます。より多くの人にエネルギーに関心を持ってもらうには、なるべく敷居を下げなくてはいけませんし、子育て団体の方たちなどとのタイアップも必要だと思います。自分たちの生活の中でエネルギーって結構大切だよねということをわかってもらえるくらいになれば、私たち協議会としての目標は達成しているかなと思ってやっています」
小峯さんはそう話す。事務局の稲田さんも、これまでの実感から次のように補足する。
「子どもたちを呼んだセミナーなどを開催すると、すごく楽しそうに説明を聞いてくれますし、お母さん方・お父さん方にも本当に喜んでもらえますから、それはいつも本当にうれしく思います。ただ、もうひと工夫できないかと思うところもあります。ただ“すごいね~!”だけで終わってしまうのではなくて、何か普段の生活に持ち帰れるものがあってくれるとうれしいですね」



長期展望の中で独自財源を持った活動ができることの強み
啓発事業を企画するのとともに、エネルギーに関する相談窓口の設置も考えていきたいと小峯さんは言う。
「太陽光発電だけでなくて、太陽熱温水器の設置やHEMSの導入なども含めて、再生可能エネルギーの導入や省エネなど、総合的な対策等について相談のできる窓口が、身近にいつも開いているようにできたらいいよねと話しています。発電事業の収益で運営していくのも一つですが、ちゃんと対価としてお金をもらえるような形で、そこに働く人の雇用にもつながるようにできたらっと考えています。つまり、窓口の開設は発電事業の収益から用意しますが、人件費くらいは時給1000円~1200円でも支払えるようにできないかと思うんです。都道府県単位では地球温暖化防止活動推進センター※5がありますが、例えば調布市に住んでいて、わざわざ都庁の16階にまで出かけて行って相談するということができるかと考えると、なかなか足が向かないと思うんです。身近な地域にこそ、気軽に戸を叩ける相談窓口を設けるというのも、地域還元の方法の一つです」
協議会のホームページで発電量を公開しているのも、自分の家の発電設備とどれだけ違うのかというのを比較してもらうためだ。発電がうまくいっているならよいが、不安だったりする場合、比較のためのデータがあれば安心できる。地域での継続的な運用によって蓄積されるデータは、地域の財産にもなる。
「調布まちなか発電は、事業に必要なお金を借りたり、専属スタッフを雇ったりするために作った会社ですが、事業を通じて生まれた利益は、会社や株主のために使うのではなく、協議会で検討して使い道を考えています。事業の目的そのものが地域貢献というCSR活動※6になっているんですね。その還元の方法については、すごくお金をかけて効果的なものが生まれるということもある一方で、あまりお金をかけなくても、継続的にやっていくことで意味のあることもあると思うのです。FITのおかげなんですが、20年間の売り上げ予想と収支計画が、ある程度は明確にわかって、継続的に取り組んでいけるのは、独自の事業をやっていることの強みだと思うのです。どれだけ収益を生み出せるかということも大事ですが、金額の多い少ないだけではなく、継続した事業ができることに大きな意味があると思うのです」
そんな地域に根づいた活動を継続的に行っていくことが、調布未来のエネルギー協議会のめざすところだと小峯さんと稲田さんは言う。



