【第71回】活動の担い手を求める地域の保全団体と、ボランティアに関心のある人たちをマッチング ─(認定NPO法人自然環境復元協会「レンジャーズ・プロジェクト」)
2016.03.28
都心部最大級の公園で、みどりに触れ、みどりを守る週末の朝を過ごす
3月初旬の土曜日の朝、JR原宿駅表参道口を出てすぐの神宮橋たもとには、首にカメラをかけた外国人観光客や短パンとランニングシューズに身を固めたランナー、ウォーキングステッキを抱えた妙齢の人たちなどが通り過ぎていく。誰かと待ち合わせでもしているのか、髪を派手に染め上げた若者数人がたむろしている。天気晴朗、まさにお出かけ日和の一日だ。
朝9時半、ここ原宿駅神宮橋のたもとに集まってきたのは、認定NPO法人自然環境復元協会が主催する「レンジャーズ・プロジェクト」に参加するボランティアたち約10名。目印となるのは、蛍光緑の鮮やかな色が映えるビブスを着用したコーディネーターの伊藤博隆さんだ。
集合場所に迷って遅刻してくる人や急な仕事の都合で参加できなくなったという人たちと携帯電話で連絡を取りながら、参加予定者全員の動向を確認すると、いよいよこの日のフィールド、都立代々木公園(渋谷区代々木神園町)に移動する。
駅から公園入口の一つ、原宿門まではゆっくり歩いて10分ほど。園内は散歩をする人たちや芝生で輪になって集う人たちなど、ことのほか多くの人たちでにぎわっている。そんな様子を横目で眺めながら、園内を横切ってさらに10分ほど歩くと、今回の活動拠点となる花壇脇の倉庫に到着する。今回の受け入れ団体となる代々木公園ガーデニングクラブのメンバーがすでに集まってきて、道具や資材の準備を始めていた。
「今回のミッションは、公園内の花壇整備をしている代々木公園ガーデニングクラブの皆さんの活動サポートです。公園内の落ち葉溜めから熟成した堆肥を運んできて花壇の土の中にすき込みます。まずは、毎回恒例の準備体操から始めましょう!」
伊藤さんの掛け声で、木々に囲まれた広場にレンジャーズ隊員たちが広がって輪を作る。講師役のガーデニングクラブの面々も混ざって、一通りストレッチをした後は、大きく広がった輪を狭めて、全員での自己紹介。ここ代々木公園での活動はレンジャーズ・プロジェクトとしても初の試み、参加者たちも今回が初のミッション出動という人を含めて、全員が1人で参加してきているから、まだお互いの名前も知らない。
ちなみに、レンジャーズ・プロジェクトでは、作業に参加するボランティアのことを「レンジャーズ隊員」、毎回の活動を「ミッション」と呼んで、ミッションの内容と日程が決まると登録隊員全員に案内メールを送って参加を要請する(呼びかける)。そして、呼びかけに応えてミッションに参加することを「出動」と呼ぶ。ちょっとした遊び心といえるが、そんな工夫にボランティア活動の基本となる主体性と使命感を持ってもらいたいという思いが込められている。


自己紹介と合わせて、代々木公園ガーデニングクラブ代表の牧野ふみよさんから、会の活動の経緯と概要について説明がある。
「代々木公園には、かつて今そこに見えるフェンスの内側にもう1列フェンスがある二重フェンス構造になっていましたが、その間が結構広かったため、ブルーシートのテントが立ち並んでいました。都では、対応の一環として、内側のフェンスを撤去して、ここに花壇を造りました。ただ、もともとこの代々木公園は森林公園という位置づけだったため、花壇整備のための予算がありません。造成工事はなんとかかき集めた予算を工面したものの、その後の維持管理の予算がないため、ボランティアで何とかしましょうということでスタートを切ったのが始まりでした。2002年2月にはじめてここにきて、以来、ちょうど14年目になりました」
2年間にわたって、概ね30~50m2の花壇を50か所、総面積1500m2ほどが整備され、そのうちの一部を代々木公園ガーデニングクラブで管理している。
この日は、作業の段取りや目的についてレンジャーズ隊員たちに説明するため牧野さんを含めて5名のメンバーが講師役として集まった。

受け入れ団体の抱える課題解決をめざして、レンジャーズ隊員が出動
レンジャーズ・プロジェクトは、みどりに関わる活動をしている首都圏各地の団体の活動フィールドに、週末の午前中3時間ほどのボランティア作業のため出動してくるレンジャーズ隊員たちがお邪魔して、いっしょに活動をするという取り組み。これによってメンバーの高齢化や人手不足などさまざまな課題を抱える現地の活動団体と、一方でボランティアをしたいと願う隊員たち双方のニーズを満たすのがねらいだ。
今回の受け入れ団体・代々木公園ガーデニングクラブは、活動当初は都が開催する花壇ボランティア講座の受講生の参加もあって人数も多く活発な活動が続いたが、活動開始から14年が経って、徐々に人数が減ってくると同時に、これまで活動を支えてきたメンバーもそれだけ歳を重ねることになった。現在は常時活動に参加できている5~6名ほどのメンバーが細々と活動を続けているような状況で、平均年齢も四捨五入すると70歳になるという。「代々木(よよぎ)公園」に語呂を合せて、毎月4の付く日(4日、14日、24日)の平日を定例の活動日に定めて、当日集まったメンバーがその時々にできる作業をしているが、つい最近、長年コアメンバーとして活動を担ってきた人がこられなくなってしまったと牧野さんは話す。
「初期からともに活動してきた仲間が入院してしまって、今休んでいます。メンバーも皆、いい年になってきたんですね。でも、“退院したらまたやるから”と言われてしまうと、その人が戻ってくるまではやめられませんよね。それと、14年も経つと、いったん離れていった人がまた戻ってくることもあります。子どもの出産と子育てで活動に参加できなくなった人が、子どもも小学生になって時間が取れるようになったからと来てくれたりします。ボランティアの“来る者拒まず、去る者追わず、戻る者には温かく”みたいな、そんな活動場所に今なっていて、ゆるゆるとした活動を続けています。でも、そんなゆるやかさがあるからこそ続いているのかなとも思います」
活動を始めた最初の頃に掲げた目標は「無理をしないこと」だった。広大な代々木公園での活動だからこそ、作業自体もさることながら、休憩時間を大事にして、のんびり・ゆったりとした活動を心掛けている。ただそれでもだんだん人数が減っていくにしたがって、一部のメンバーに負担が集中してきてしまっている現状がある。何とかしたいと思っていたところに、今回のレンジャーズ・プロジェクトのようなサポートの話がいくつか入ってきて助かっていると話す牧野さんだ。


レンジャーズ・プロジェクトのめざすところは、まさにこうした各地の団体が抱える課題の解決にある。代々木公園ガーデニングクラブに限らず、各地で自然環境保全を担ってきた団体では、会の創成期から関わってきた主要メンバーの精力的で力強い活動が大きな推進力となってきた反面、その活動を引き継いでいく次世代の担い手がなかなか育っていかないという共通の課題を抱えている。
一方、ボランティアとして参加する隊員たちにとっても、いきなり見も知らない団体の門戸をたたいて所属しようというのは敷居も高いし、定例活動日に合わせて予定を調整するだけの覚悟が十分に持てるかといった不安もある。
結果として、森や自然に関わりたいという思いは強いものの、はじめの一歩を踏み出せずに逡巡する人たちが多いのが現状だ。
レンジャーズ・プロジェクトは、そんな受け入れ団体と作業の担い手双方の問題を解決することで、新たな里山保全の仕組みを作ろうと構想されたものだ。この日のミッションも、クラブのメンバーだけだと普段はなかなかできない作業を、レンジャーズ隊員たちが加わって一気にやってしまおうというわけだ。
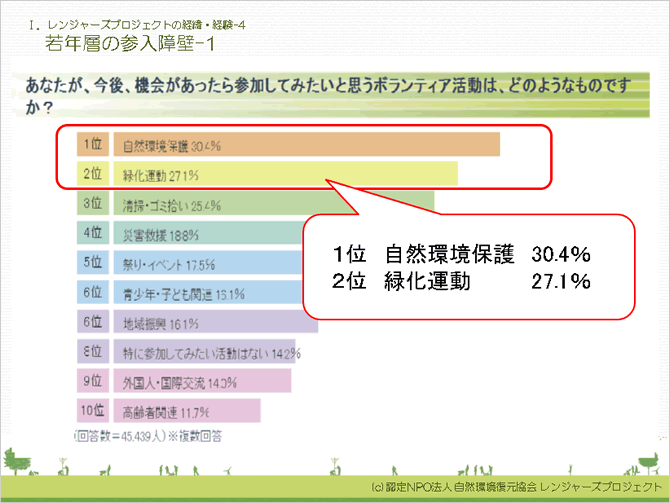
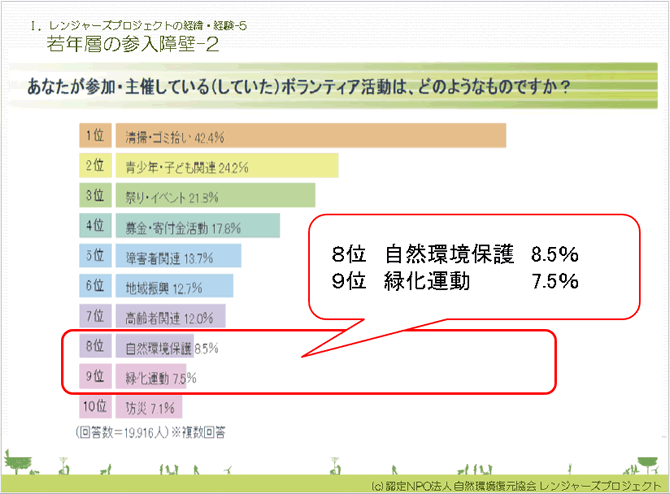
参加してみたいボランティア活動と、参加したことのあるボランティア活動。自然環境保護や緑化運動へのニーズが高い(1・2位)わりに、実際にはなかなかできていない(8・9位)ことがわかる。
(レンジャーズ・プロジェクト事務局提供)
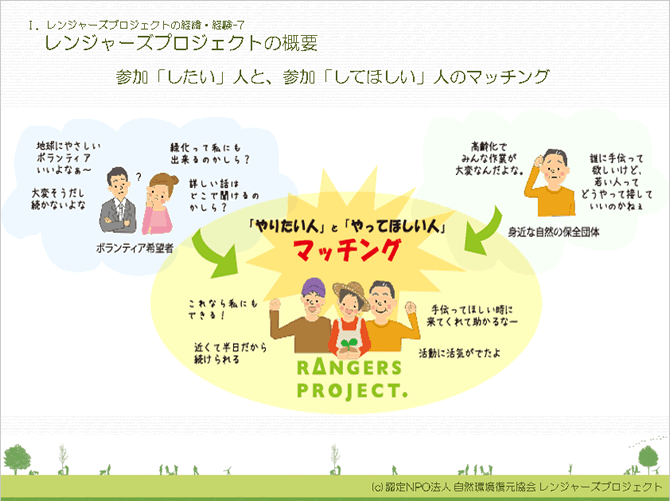
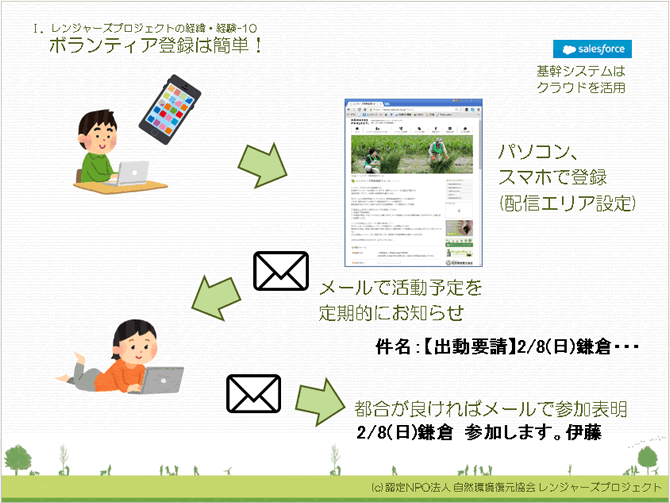
レンジャーズ・プロジェクトの仕組みとねらい。(レンジャーズ・プロジェクト事務局提供)
植えっぱなしにしたままでも育つが、何年かに一度、土を変えてあげると、リフレッシュされて状態がよくなる
再び、取材当日のレンジャーズ隊員たちのミッション遂行の様子を見ていきたい。
この日の作業は大きく分けて2つあるため、2班に分かれて作業をする。一方の班は、リヤカーを引いて落ち葉溜めに向かい、落ち葉堆肥を袋に詰めて運んでくるのがその役割。他方、残りの人たちは花壇に直行して、枯れて茎がしおれた花の株を根っこごと掘り起こして、運んでくる堆肥をすき込むための準備をする。



堆肥班が公園奥の落ち葉溜め場に向かった後、花壇作業班は、まずは花壇の中の落ち葉を掃きならして、どこに何が植わっているのか確認できるようにする。花壇の手前には背の高いスイセンがスッと立ち、その奥にちょうど新芽を出しているへメロカリスの株がパッチ状に点在しているのが見える。このヘメロカリスの株を根っこごと掘り起こしていくわけだ。
へメロカリスという名前は初めて聞いたが、ツンツンと伸びる葉っぱは特徴的で、他の雑草などとの区別は明確だ。広がって張り出す根を切らないように、広めの範囲にスコップを差し入れながら掘り起こすと、根っこの先にややオレンジ味がかった楕円形の塊がいくつもつながっている。宿根と呼ばれるこの器官に栄養を蓄えることで、地上部が枯れても土の中で生き続ける。ユリの仲間の多年草で、初夏にオレンジ色の花を咲かせる。野生種では、ニッコウキスゲやノカンゾウ、ユウスゲなどが近い仲間として知られる。
掘り起こしたヘメロカリスは、花壇の外にまとめて置いて、あとで植え戻すという。
「緑色の新しいのが今年の新芽です。去年咲いた花も白っぽく枯れて残っているのがわかると思います。根っこごと掘り起こしてください。ヘメロカリスは、毎年花を咲かせてくれて、立派なんですよ。でも何年かに一度くらいこうやって土を変えてあげると、リフレッシュされて状態がよくなります。こうした機会にお願いしている作業です」





掘り返していると、ところどころ、へメロカリスとは雰囲気も葉っぱの形も違う草が生えているのに気づく。
「チューリップですね。背の低い、原種系の品種です。背の高い園芸用のチューリップは日本の気候だと球根が根腐れしちゃうので、1年草として植え替えますが、この品種は強いから年を越えて新しい花芽を出します。ほら、そこに赤味がかったつぼみが見えるでしょう。もうすぐ花が開くんじゃないですかね」
そう、ガーデニングクラブのメンバーが解説してくれる。おしゃべりしながら作業をしていると、ガーデニングクラブの人たちが花々を慈しみながら世話している様子が伺えるようだ。
土を掘り返していくと、ツンとした刺激臭がほんのりと香ってくる。土の中には、ちょうどBB弾ほどの真っ白で小さな球状の塊が見え隠れしている。開けた野原などに自生する野草のノビルだ。白い球根は、小ぶりながら、味噌をつけて食べると酸味と辛味が刺激的で意外にうまいという。
白くひょろっと伸びた根が出てくると、ドクダミの独特なニオイが漂う。地上の株は枯れてそれほどニオわないが、白い根からは思いがけずはっきりとしたドクダミ臭が感じられる。ノビルもドクダミも花壇の中では雑草だから小石などとともに抜き取って花壇の外に投げ捨てていく。


へメロカリスの掘り起こしが完了すると、全体を20~30㎝ほど掘り起こしていく。こうして土を耕したところに腐葉土などを撒いて、花壇の外に仮置きしたヘメロカリスを植え戻すというのが、今回の作業の内容だ。

“作業開始前は落ち葉に埋もれて花壇っぽくなかったのが、どんどんきれいになっていった”
落ち葉溜めから堆肥班の人たちが土嚢袋に詰めた落ち葉堆肥を運んで戻ってくると、さっそくその堆肥を肥料や土壌改良剤とともに撒いてすき込んでいく。さっとならしてきれいになった花壇に、全員で手分けしてへメロカリスの株を植え戻していく。花壇の手前にスッと立つスイセンを境に、その後ろにヘメロカリスを植え、併せてスイセンの手前に、公園の近所にある球根輸入代理店から寄付してもらったクロッカスとチューリップの球根を植えていく。
「球根は、冬の寒さに当てないと開花しないので、今の時期だとギリギリのタイミングなんですが、土に入れてあげればあっという間に花が咲きます。球根の大きさの3倍くらいの深さの穴を掘って埋めてください。大きい球根は地上に出てくる茎も高く生長するため、支えるためにも根を深く張り出していくことが必要なんです」
大量の球根を何袋ももらっているから、溝を掘って、その中に並べて植えていくような感じでどんどん植えていく。通常のガーデニングではそんな乱暴な植え方はしないというが、ここでは、これくらいどんどん埋めていかないと作業が終わらないまま植え時を逃してしまうことになる。
一方、スイセンの奥の花壇一面に植え戻すヘメロカリスは、まずは全体のバランスを見ながら配置していくところからはじめる。置くときに、まっすぐ一列に置くのではなく、ジグザグに置いていくときれいに見えるという。
「スコップがある人は、スコップの方が楽だと思います。今置いたところに、穴を掘っていきます。掘るときに、スコップの肩のところにぐっと体重を乗せて力を入れると、普段重たくていやだなという体重も、役に立ってくれますよ」
冗談も交えながら、軽妙なトークでクラブのメンバーが植え方の説明をする。
土は一度掘り起こしているからフカフカで、穴を掘るのもそれほど力を要しない。ヘメロカリスを入れてちょうど地面が平らになるくらいの穴をあけ、土をかけ戻していく。
「植えるときに、斜めにならないよう茎をまっすぐ立ててください。まわりの土を平らにしたら、最後ギュッと押さえてあげると、土と苗が活着※1して安定しますから、押さえて平らにしておしまいにしてくださいね」
手前から植えると踏みやすいため、花壇の内側から外側に向かって植えていくと、踏まずに植えていくことができる。そんなアドバイスに沿って、レンジャーズ隊員たちも黙々と作業をこなしていく。




堆肥班の人たちが袋に詰めた落ち葉堆肥を抱えて戻ってくる。花壇班が花壇の掘り起こしをしている間、堆肥班の人たちは公園の端の落ち葉溜めへ向かい、土嚢袋に落ち葉堆肥を詰める作業を行った。成熟したよい土になっていないところもあって、選びながら詰めていくのが大変だったという。
(レンジャーズ・プロジェクト事務局提供)




掘り起こした花壇に堆肥を撒いて土づくり。レーキや熊手、スコップなどでならしていく。堆肥をすき込んでならした後、ヘメロカリスの株を植え戻していく。壇手前で一列に並ぶスイセンの根元には、クロッカスとチューリップの球根を埋めていく。やや時期遅れだが、1週間ほどもすると花が咲くという。
ミッションを終え、クールダウンのストレッチで体をほぐした後、隊員及び講師陣全員が輪になって、まとめの会で一言ずつ感想を言う。
レンジャーズ隊員の一人から、「作業開始前は落ち葉に埋もれて花壇っぽくなかったのが、どんどんきれいになっていったのがうれしかった」という正直な感想もあった。確かに、花壇というよりは落ち葉の吹き溜まった雑木林の林床という雰囲気だったといえる。

公園外周のフェンス沿いに整備されたこの花壇は、「花の小径(こみち)」と呼ばれて整備されている。水やりもせず雨水だけで育つが、まわりを囲うようにケヤキが伸びているため、春から秋にかけて木々が葉を茂らす季節になると日当たりが悪くなり、必ずしも条件のよい花壇とはいえない。とはいえ、初夏の頃に花が咲くと、雑木林の中の自然な感じがよい雰囲気を醸し出す。この日の作業で植え戻したヘメロカリスも、7月~8月にかけて開花するだろうという。花の時期にはぜひ訪ねてみたいと、隊員たちも口々に話す。
今回集めてきた落ち葉堆肥は、合計22袋分になった。そのうち、この日花壇に撒いたのは3袋分。残りは、今後、クラブが管理する他の花壇も含めて季節ごとの植え替え時期に土に混ぜて使っていく。22袋分でほぼ一年分はもちそうだというから、今回のミッションはまさにレンジャーズの面目躍如といえるだろう。


レンジャーズ・プロジェクトの持続的な活動に向けて
レンジャーズ・プロジェクトの登録者数は、2016年2月現在で2,350人にのぼる。毎年400~600人ほど増えていることになる(下表参照)。登録してすぐ毎週のように出動してくる人もいれば、長年登録したまま地元開催の今回を期にようやく初出動を果たしたという人もいるなど、参加の仕方は人それぞれだ。
それでも、年間のミッション要請回数と人数は、2010年度の19回・146人から、2011年度には44回・489人、2012年度は62回・688人、2013年度に56回・688人と推移してきて、昨2014年度は52回・649人となった。ほぼ毎週のように開催していることになる。
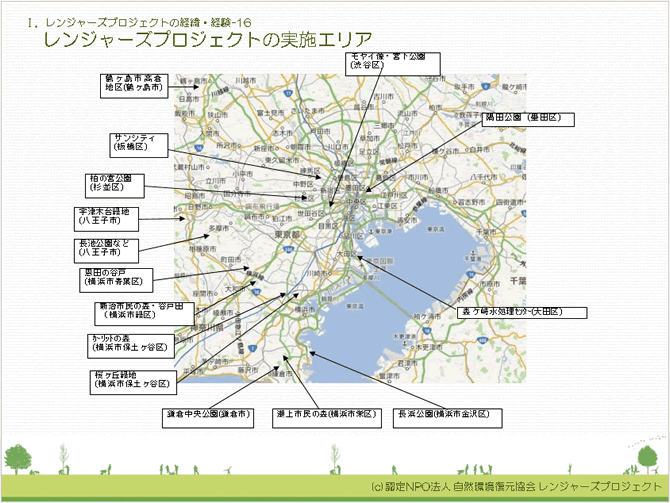
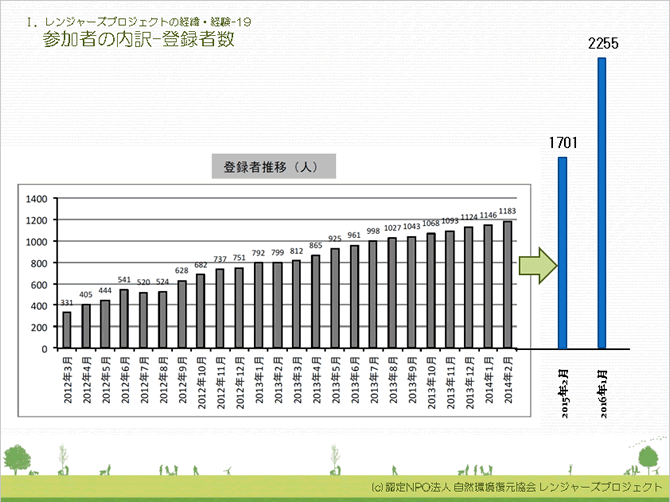
順調に発展し続けるレンジャーズ・プロジェクト。今後の課題は、保全活動の現場の需要と、実働部隊としてサポートするレンジャーズ隊員側の供給とをバランスしながら、いかに広げていくかというところにありそうだ。
登録人数が増えて、活発に活動に参加する隊員が増えていけば、保全現場の抱える課題の解決もより多くこなすことができることになる。その反面、各団体との連絡調整や隊員たちへの出動要請と事後の報告など事務作業も増えていく。現在はスタッフ2人と現場リーダー5人という体制でまわしているというが、年間60日の出動を維持するだけでギリギリの状況だというのも頷ける。
立ち上げ当初は地球環境基金を活用してプロジェクトの基盤づくりを行ってきたが、今後、持続的な活動にするための資金調達も大きな課題となるだろう。
活路の一つとして、ここのところ増えてきているのが、企業の社会貢献事業とのタイアップだ。レンジャーズ・プロジェクトのネットワークを生かして、社員が参加するオリジナルのプログラムを提供する。
他方、個人が参加するレンジャーズ・プロジェクトについては、担い手不足の解消と同時に普段なかなかみどりとかかわる機会のないオフィスワーカーを大量に抱える首都圏ならではの新しく・効果的なボランティアニーズの掘り起こしと受け皿提供として意義深い。こうした公益的な活動に理解を示す行政機関との協働・協力は一つの方向性になり得るだろう。実は、今回の代々木公園でのサポート事業は、渋谷区からの委託事業として、オール東京62市区町村共同事業の助成金を活用して実施している。レンジャーズ・プロジェクトと連動した緑の保全事業としては、代々木公園ガーデニングクラブの活動の他、渋谷駅前のモヤイ像花壇で活動するシブハナの活動サポートとして花ガラとごみ拾い及び花壇保護のための柵の取り付け作業を行ったりと合計4回の活動を実施してきた。この他、NPO法人渋谷川ルネッサンスの協力で唱歌「春の小川」の舞台・渋谷川を歩いてビルピットからの下水臭の調査なども行っている。
都市近郊の自然は特に人の手が入ることで維持されてきた自然だ。保全のためには人の手を入れていく必要がある。伊藤さんは、このプロジェクトを通じて「住民総レンジャーズ化」をめざしたいと意気込む。そこまではいかずとも、地域で担い手不足に悩む保全団体の活動の社会的意義やその魅力をアピールしつつ、レンジャーズ隊員のサポートにより活動を支えていこうというレンジャーズ・プロジェクトの可能性と期待は決して小さくはないといえよう。



