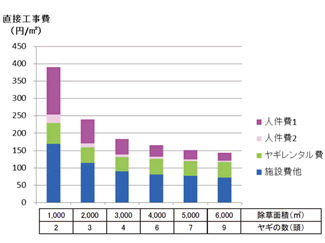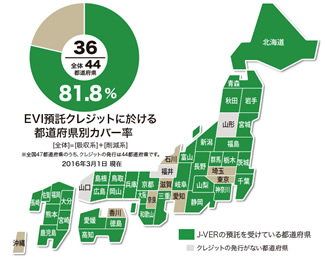【第78回】町田山崎団地におけるヤギ除草の取り組み ~団地の草をはむヤギがもたらす効果を探る(UR都市機構&URコミュニティ)
2016.12.05
約2か月にわたって草を食べ続けた2頭のヤギたちとの“お別れ会”
11月初旬のある土曜日の朝、晴れ渡った青空のもと、町田山崎団地(町田市山崎町)のほぼ中央を東西に横断する都市計画道路予定地に架かる「三の橋」と呼ばれる陸橋の上に、団地住民や近隣の保育園の子どもたちが集まってきた。この日これから橋の下の草地で開催される「ヤギお別れ会」の開始を今や遅しと待つ人たちだ。
町田山崎団地は多摩丘陵の丘の上に位置し、広大な敷地の中には、図書館や郵便局、商店街のほか、保育園・幼稚園や小学校もあって、さながら一つの街を形成している。昭和43年に入居を開始した公団賃貸住宅には、全116棟、合計3,920戸が暮らしている。谷筋に伸びる道路予定地を境に団地は南北に分かれ、センターバス停や商店街、図書館や郵便局などが集まる南側は終日人々の賑わいが絶えない。一方、団地北側は起伏に富んだ地形で、木々が生い茂ったり、調節池があったりとバラエティ豊かな風景が楽しめる静かな地区だ。道路予定地付近の団地中央部には、南北のエリアをつなぐ広場スペースが整備されるとともに、幼稚園や保育園もあって、日中は子どもたちの声が響き渡る。


そんな町田山崎団地にヤギが初めてやってきたのは、平成25年9月のこと。以来、毎年、草が枯れる冬までの期間、三の橋たもとの草地で日がな一日草を食むヤギの姿が見られてきた。目的は、「ヤギを活用した除草工法(ヤギ除草)」の実証実験として、橋下エリアの除草の役割を担うこと。今年も9月12日から約2か月間にわたって滞在してきたヤギたちも、冬になって食べる草もなくなることからお役御免となる。団地住民をはじめ、近隣の保育園の子どもたちなどにも呼びかけて、ヤギたちとの最後の交流の機会を設け、送り出そうというのが、この日開催された「ヤギお別れ会」の趣旨だった。


ヤギの好物の葛の葉を手に、ヤギとの別れの交流を惜しむ
陸橋の上から急な階段を下って、橋の下の草地に降りる。電気柵に囲われた中でヒモに繋がれたヤギ2頭を、お別れ会の来場者が静かに見守る。
主催者及び来賓の挨拶に引き続いて、2か月間ヤギの水やりや小屋の清掃など世話をしてきた担当者から、ヤギ交流に当たっての諸注意についてアナウンスがある。
「皆さんにはこれからヤギと交流していただきますが、いくつかお願いがあります。ヤギが嫌がることはしないでください。追いかけまわしたり、大声を出したりしないようにお願いします。また、柵に入る前には、最初に靴底と手の消毒をしてください。すでにお入りいただいている方もいますが、これから入る方もよろしくお願いします。エサをあげたりヤギに触れ合ったりしたあとも、同じように消毒して、お家に帰ってからもよく手を洗ってください」


こうして始まったヤギお別れ会、まずは近所の保育園児たちが歌を披露して場を盛り上げる。“♪き、き、きのこ…”という歌い始めは緊張もあって消え細りそうだった子どもたちの声も、2曲目になると調子が上がり、元気いっぱい、声のトーンも一気にマックス状態となった。
歌の後は、いよいよヤギとのふれあいタイム。バケツやダンボールに用意されたヤギの好物の葛の葉を1掴みずつ持って、三角屋根のテント小屋の近くにつながれたヤギたちのもとへと向かった。
物怖じせず向かう子、先生の後ろに隠れて恐る恐る覗く子などさまざまだったが、差し出した葛の葉を無心に食べ続けるヤギの姿は子どもたちにとっても何か心に残るものになったに違いない。さらに近づいて行ってお腹をなでさすったりと、満足げな表情を見せる子どもたち。しばしの交流の時間を過ごし、「楽しかった~!」と満足げに帰っていった。
新たな取り組みとして始まった「ヤギ除草」実証実験
町田山崎団地でヤギ除草の取り組みが始まったのは、前述のとおり、平成25年に遡る。実施機関は、同団地を管理する独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)。27年度まで3年間の実証実験を重ねて、さまざまなデータが得られてきた。これまでの経緯と今年度新たにURコミュニティの事業として始めた取り組みについて、同機構の技術・コスト管理部技術調査チームの楠元美苗さんにご紹介いただいた。
「ヤギ除草とは、人が機械で草を刈る代わりに、ヤギに草を食べてもらい、きれいにするという除草工法です。エンジン式の草刈り機などと違って、化石燃料由来のCO2排出や機械による騒音がなく、また、刈り取った草の処分や搬出も不要となります。27年度までの3年間の実証実験によって安全面やコスト面の検証を行ってきました」
ヤギ除草の効果の一つとして明確になったことの一つに、雑草の抑制による草地景観の維持効果がある。町田山崎団地における3年間のヤギ除草の結果、ヤギがいる期間中は、草の高さが最大で40cmほどに抑えられ、除草面積に対して必要なヤギの頭数やそれにかかるコスト試算などのデータも得られてきた。
「仕上がりや費用的な面では、通常の機械による除草と比べると難しい面もあります。除草する期間が長くなればそれだけ費用もかかってきます。ヤギのレンタル費のほか、雨除け・日除けのためのテント小屋や逃走防止の電気柵といった施設の設置費用、さらにヤギの世話として、飲料水の交換やテントの掃除、健康チェックと電気柵の点検など日常のメンテナンスにも手間とコストがかかります。除草エリアの条件等によって一概にヤギ除草と機械除草のどちらが高い・安いとは言えませんが、2か月間で除草面積が3千m2~4千m2になると機械除草とかなり近い費用感で導入できることもわかってきました」


仕上がりの精度も、機械で刈れば地際まできれいになるが、ヤギ除草で同じような仕上がりを期待するのは難しい。
「生き物が食べるものですから、好き嫌いなんかもあったりしますし、硬い茎は食べ残していますから、機械で刈るような均一な仕上がりは期待できません。茎だけ伸びた草が残ってしまうんですね」
こうしたヤギ除草の特性を知ったうえで、導入について判断する必要があるわけだ。

もともとヤギ除草を始めたきっかけは、UR都市機構の若手職員を対象に新たな取り組みの募集の中にヤギ除草の提案があったからだ。同機構では団地や事業用地など多くの土地を管理しており、定期的な除草などを必要とするところも少なくない。通常はエンジン付きの草刈り機を使っているが、ヤギを連れてくれば、環境にやさしい除草になるというアイデアだ。そこで、実際の除草の効果がどのくらいあるのか、団地の中などで安全にできるかなど検証するための実証実験として、25年度にまずは八王子にある技術研究所(当時。現在は組織改編で名称が変わり、技術管理分室)の中での試行を踏まえて、同年9月から町田山崎団地での実証実験を開始した。
初年度は周辺住民の理解を得るため、近隣の保育園・幼稚園にも呼びかけた見学会などのイベントも数多く企画するとともに、『まちにやさしいヤギ除草』というパンフレットなどの資料もつくって配布した。『ヤギ除草のここが知りたい』は、アンケートなどを通じて寄せられた質問・意見をもとに、居住者にヤギのことを知ってもらう目的で作ったものだ。ヤギの性格や寿命、角とひげや、ヤギの食べ物とうんちや鳴き声など、動物としてのヤギについての質問、雨風や台風の時のヤギの対応・避難の必要などヤギを心配する声への回答、またヤギ除草と機械除草の違いなどさまざまな疑問と意見を質疑応答形式でまとめ、子どもでも読めるようにフリガナを振って、イラストもふんだんに入れて構成した。
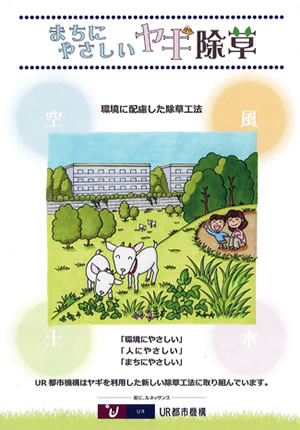
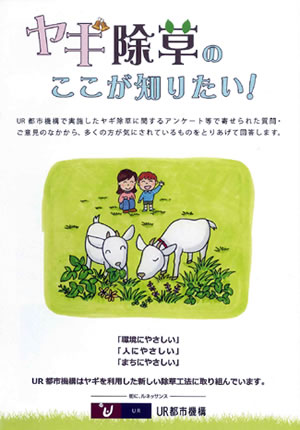
臨床心理学の視点から、ヤギのコミュニティ形成効果を検証
除草の効果とともに明らかになってきたのが、コミュニティ形成の効果だった。
「ヤギの管理方法やヤギ除草のコスト試算などのデータが集まっていくと同時に、住民の皆さんにお願いしたアンケートなどを通じて、実はヤギが身近にいることの効果が小さくはないことがわかってきました。ヤギの存在が団地住民の方々に癒しや安らぎを与え、ヤギを介した地域のコミュニティ形成に寄与する効果が予想以上に高いようなのです」
このヤギの癒し効果やコミュニティ形成支援効果に着目したのが、UR関連会社のURコミュニティである。
URコミュニティでは、町田山崎団地とつながりの深い桜美林大学に呼びかけ、これらの効果の検証や増進方法の検討を目的に、平成28年度から新たな視点でヤギ除草調査を企画・実施している。
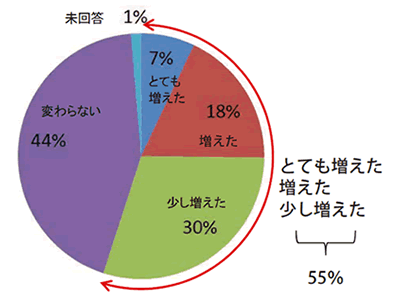
子どもたちがヤギにエサをやって交流している間、橋の上では、桜美林大学教授の種市康太郎さんが学生さんやURコミュニティの調査担当者とともに通りがかる人や橋の上から眺めている人たち、またエサやりを終えて引き揚げてくる親子などを中心にヤギの存在に対する意識などについての聞き取り調査の協力を呼び掛け、走り回っていた。
町田市常盤町にある同大学の町田キャンパスは、山崎団地からも近いため、地域のイベントに大学の学生や教職員が関わるなど、普段からつながりがある。
「私の専門は臨床心理学で、普段は、働く人のストレスに関する調査やカウンセリングなどをしています。ヤギの除草については、草刈り機で刈っていくのに比べてコスト面では必ずしも有利になるわけではないと言われていますが、ヤギが入ることによって、ヤギと触れ合う住民の方や、ヤギに対して癒しを感じる方が多いという声も一方では聞かれますので、それらについて科学的に検証しようというのが今回の調査の目的です」

調査は、橋の上の通行量及び行動実態の把握と、全戸アンケートによる意識等調査で構成される。URコミュニティからの調査委託を受けたコンサルに桜美林大学が分析等で協力する形で関わっているという。
「ヤギが来る前、来てから、そして去った後の3期に分けて通行量の違いをカウントして比較します。ヤギを見に来る方は、橋を通過する方だけでなく、橋まで来て帰っていったり、橋の上で滞在したりと明らかに行動の変化が起きていますし、1人で見ているところに別の人が寄ってきて会話が始まったりということもあります。高齢者の方もヤギを見に来ることによって行動の範囲が広がったり、散歩をするようになったりもしているようです。団地の地理的な位置による心理的な愛着の違いも興味があるところです。全戸アンケートのお願いをしていますから、橋の近くと橋から離れたところでの違い、また橋の南側に住んでいる方は通勤や買い物で橋を渡る必要がないので、そうした立地の違いによるヤギに寄せる思いの違いについても分析していきます。中には、普段は別の道を通っているけど、ヤギが来ている間は少し遠回りをしてでもこの道を通るという方もいらっしゃるので、そうした地域的な特性も出てくることが期待できます」
ヤギが入ることでコミュニティの中に一つのよい効果を創り出していることは確かだと種市さんは話す。ただ、ヤギだけでなく、地域の中でさまざまなイベントが実施されたり、団地以外の──例えば大学との──連携があったりすることで生まれるさまざまなつながりこそが、団地を暮らしやすくすることにつながる。ヤギはその一つのきっかけとして大きな効果をもたらしているといえる。

身近にヤギがいる光景
かつて、地域によってはヤギが普通に飼われていたこともあったが、近年は犬や猫ほど身近な動物として見慣れているわけではない。ヤギの性格や行動を知らない人も多く、珍しさからいたずらされることも懸念される。
「ここ町田山崎団地の場合は、橋の上と下で、はっきりと地形的にも分かれています。防犯カメラもつけていますが、ヤギがいるところを橋の上からご覧になることもできるので、そうした人目があることでいたずらの抑止にもなります。眼下のヤギを見守りやすい一方で、人とヤギの生活空間が物理的に分けられているので、お互いにとって適度な距離感が保て、導入しやすい条件が整っているといえます」
楠元さんはそう指摘する。
ヤギ除草を実施するための条件としては、この他にも土地の乾燥状態が挙げられる。もともと乾燥地を生息地にしているヤギにとってジメジメしたところは苦手だから、雨が降った後に水が溜まるような環境は不適となる。本来野生の動物だから雨風に耐える能力はあるものの、湿気を避けるため、小屋は高床式のものを用意している。
「もちろん、一番大事な条件は、住民の方々が“ヤギさんが来てもいいですよ”と理解してくださることです。そうした条件が合うところであれば、広がっていってくれるのかなと思います」

ヤギの体重・体格によって、草を食べる量も変わってくる。体重・体格によってレンタル料が変わるわけではないから、除草のことだけを考えれば大きい方が食べる量も増えて効率的になる。ただ一方で、住民との触れ合い──特に保育園・幼稚園児など小さい子たちとも直接的な触れ合い──を重視するなら、あまり大きいヤギでない方がよい。この日のお別れ会でも、草のエサをやろうとする子どもたちがこわごわとヤギに近づいていく様子も見られた。
そんな子どもたちの様子を橋の上から楽し気に眺めていたご婦人2人連れがいた。階段を降りて怪我をすると困るからと、エサやりの交流には参加していないというが、4年目となるヤギがいる生活にもすっかり馴染んでいるといって笑顔を見せる。
「昭和44年入居だから、もう50年近いね。ヤギはさ、やっぱりほら、癒されるのよね。楽しいわよ。こっちの南側が商店街でよく通っているから、そのたびに見ているの。商店街もだいぶ閉まっちゃって、だんだん淋しくなってね。もうヤギくらいでしか楽しみがないから。こういうイベントでもなければ、久しぶりに会うという人もいるからね」
そんなふうに住民たちも楽しんでいた、ヤギお別れ会の一日だった。