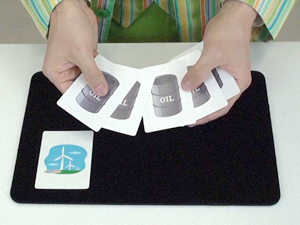【第81回】ぼうぼうに荒れた森に毎月通って、1本ずつノコギリで木を伐っていく。そんな地道な、でも本格的な山仕事を中学校の部活として取り組むことの意義(三鷹市立第二中学校「地球環境部」)
2017.02.28
『マスターソード』ってなんだ!?
JR三鷹駅または隣の武蔵境駅から路線バスに乗って10数分ほど、バス通りから閑静な住宅街の中を抜けていくと、三鷹市立第二中学校の正門が見えてくる。ある火曜日の放課後、校舎北棟の2階の端にある理科室に案内されると、地球環境部のメンバーたちが集まっていた。
「なんとですね、今日は地球環境部テストの第二弾、『林業技術編』を持ってきました。林業技術の観点で、ごくごく基本的な技術や知識について解説してあります。一部空欄があるので、まずは各自で埋めてみようか」
顧問教諭の宮村連理(みやむられんり)さんが生徒たちに声をかけながら、冊子に綴じられた『地球環境部テスト(林業技術編)』を配っていく。表紙には、“地球環境部の部員として最低限知らねばならない知識”と書かれている。手にしたテストを開いた生徒たちは、一様に戸惑いの表情を浮かべる。
「これ、無理でしょ!」
開いてすぐにあきらめ顔の子もいる。
「でも、ここに書いてある通り、この中の知識がないのに山の現場に出て行っても恥かくだけだからね。さあ、やってみて、わからないところは飛ばしてもいいから!」
宮村先生が励ますように声をかけていく。


テストを覗き込むと、中学生用としては、なかなか本格的な内容だ。
まずは、天然林と人工林の違い、なかでも木材生産を目的とするスギ・ヒノキ林と、里山とも呼ばれて日々の暮らしに活用されてきた薪炭林との違いから始まり、戦後の木材需要の増加によって植え替えが進んだこと、ところがその後は、需要低下や輸入材による価格の低迷によって放置されるようになっていった森の歴史がひも解かれていく。そんな背景を受けて、高機能林業機械の導入や効率的な作業道の敷設と製材・製品化による林業の復興・再生の取り組みが進むとともに、都市住民による森林ボランティアの活動のはじまりについて解説し、地球環境部が参加する森林ボランティアの活動へとつなげていく。後半部は、まさに林業技術そのもので、間伐・造材の目的や選木の仕方、受け口と追い口を刻んで伐倒方向を制御する方法について空欄を埋めていったり、間伐時や枝打ちの際にどの位置で見ているか(立っていてはいけない場所はどこか)を図に記入したりする問題もある。間伐データの収集では、胸高直径と木1本1本に付けてあるナンバリングを確認したり、照度や空隙率を求めて間伐作業の結果を評価したりする作業方法についても解説する。
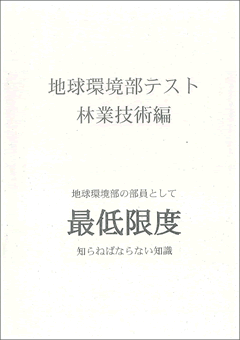
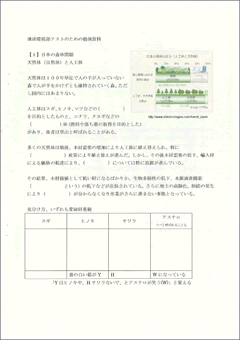
『地球環境部テスト』。中学生の部活レベルとは思えない、本格的な内容だ。ちなみに、第一弾は生態系編。学校ビオトープづくりと管理に際して押さえておくべき基礎知識をおさらいする。
しばらくそれぞれで考える時間を取った後、答えあわせを兼ねて全員で読み通していく。
「じゃあ、ちょっと見ていこうか。マジメに○付けしようとしたら1時間・2時間じゃ無理なので、ざっと見ていこうか。これね、どこかでちゃんとじっくり話そうと思っていたんだけど、天然林と人工林があるというのは知っていました? 君たち、人工林にしか行かないから、天然林を見たことがないでしょう」
天然林と聞いて、生徒たちが、“白神山地!”、“知床!”などと思い思いにあげていく。
「そう! …屋久島はちょっとあやしいけど、まあいいか。一方で、薪炭林というのがあるよね。里山といった方がわかりやすいかな。この辺にある武蔵野の雑木林というのは、里山のことです。あれはほとんど人間が植えた木なんですね」
かつて武蔵野の雑木林に覆われていた三鷹市内も、宅地化の進行とともに、残念ながらかつての面影はもはやそれほど残っていない。
「ぼくらが通っている相模湖の森は、ほとんどがスギ・ヒノキの人工林だけど、お寺の裏山の森の木は広葉樹ですね。落葉広葉樹。クヌギ、コナラ、ケヤキが多いかな、あそこは」
“テスト”で復習する机上の知識と、現場での体験をつなげながら、宮村先生が話を進めていく。“お寺の裏山”というのは、地球環境部でフィールドにしている森の一つ。地主が代替わりしたばかりの住職さんなので、通称「お寺の森」と呼ばれている。
「はい、じゃあ次行きますね。『多くの天然林は戦後、木材需要の増加により人工林に植え替えられました』。まあ、戦争に負けてですね、日本中が焼け野原になったので、家が必要になったわけですね。当時は木造の住宅しかなかったから、山の木をみんな切っちゃった。そこで、裸になった山にスギ・ヒノキを植え直したんだね。だから日本中至るところにスギ・ヒノキが植えられているわけなんです」
「そして花粉症が…」
すかさず、部員の一人が口を挟む。
「そういうことですね! 本当はもっとちゃんと手入れをしてやれば、スギ・ヒノキもあんなに花粉を出さないんだけど、子孫を残そうと思って花粉をいっぱい出すわけだな。ちょっと! 一番大事なところ、わかった? スギ・ヒノキはなんで花粉を出すの? たぶん必要以上に出していると思うよ」
生徒たちに問いかけながら、知識の定着を図っていく。
「…スギ・ヒノキは、子孫を残すために花粉をいっぱい出す…」
「だからそれはなんで? (…しばらく答えを待った後)全然わかっていない! はい、じゃあ先輩から正解をお願いします!」
「ええと、森の木が密植されているため、その木たちが生命の危機を感じて、もっと子孫を残さなきゃということで花粉を多く出しているんです」
春に入部して1年に満たない1年生たちにとってはあやふやな知識も、2年目になる先輩たちは現地での実体験をベースに、確かな知識として身につけているようだ。
「そうですね。生命の危機に瀕していると思っているんじゃないのかな。だってこれだけ混んでひょろっとした木になっちゃうと、明日枯れるかもしれないし、明日折れるかもしれないというわけです。はい、じゃあ次行きます」
「拡大造林という政策で、スギ・ヒノキを植えなさいと。昔は、苗を植えたらお金がもらえたらしいよ」
「ああ! 儲けられたのに!!」
「昔の話ね。うちらは、今、森の木が手入れされてなくて困っているじゃないですか。昔、戦後の頃は木がめちゃ高い値段で売られたわけよ。みんな切っちゃって、なくなっていたから。木を3本切って市場に出せば、1か月は遊んで暮らせたなんていう地主さんの話を聞いたことがあるよ。そういう時代があったわけ」
「え~! すげえ!」
「しかも植えたらお金がもらえたわけでしょ。だから、今やどこに行ってもスギ・ヒノキが植わっている。なんでこんなところに植えたんだろうというところにも生えているよね。無理して植えたんです。がんばって。ぼくら世代ではいないけど、50代~60代以上の人で、子どもの頃に親に連れて行かれて山に木を植えたっていう人はいます。で、その人たちが大人になったら、相続しても森がわからないということになっちゃっている。ぼくらが森を借りているお寺の住職さんも、相続したけど、全然わからないって言っているよね。どこが自分の森かわからないからってことで、みんなで測量したわけです」
林業技術の作業行程についての解説では、“マスターソード”という聞き慣れない言葉が出てきていた。
「これ、森でいつも使っているあのでっかいノコギリをみんなはマスターソードなんて呼んでいるけど、そもそもなんていう正式名称なのよ?」
宮村先生の問いかけに、生徒たちからはそっけない答えが返ってくる。
「正式名称なんて使いません!」
「使わなくてもいいけど、知っておいてほしいんだ。君らはマスターソードなんて言っているけど、森のおじさんたちに『マスターソード、どこですか?』なんて聞いても通じないよ。君たちだけです、そんな言い方してわかるのは。だから、ちゃんとした正式名称も知っておかないといっしょに活動していられないじゃない」
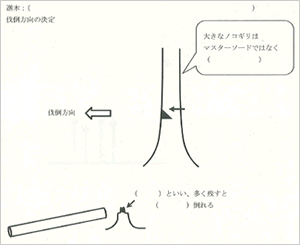

地球環境部事始め
ここ三鷹市立第二中学校で地球環境部の活動が始まったのは、宮村先生が赴任してきた2年前にさかのぼる。
「もともと園芸部があって、畑仕事や芝生管理をしていたんですけど、その先生がちょうど異動して、代わりの理科の教員としてぼくが赴任することになって、そのままやってくださいよという話になりました。わかりました、でも名前を変えていいですかということで、二中の『地球環境部』が始まったのが27年度のことでした。前の赴任先の杉並区立高井戸中学校でも『地球環境部』をずっとやっていましたから、その続きという形ですね」
実は宮村先生、本業の中学教諭の傍ら、学生時代からかかわってきた森林ボランティアNPOの副代表理事を務めている。神奈川県相模原市緑区相模湖周辺の民有林等の森林をフィールドに、自分自身が汗を流して活動するとともに、学校の部活を立ち上げて、生徒たちといっしょに活動しているわけだ。『地球環境部テスト』の答え合わせで出てきた“お寺の森”というのも、NPOが管理しているフィールドの一つ。嵐山と呼ばれるスギ・ヒノキ林とともに、現在のメインフィールドになっている。
二中の地球環境部は、ちょうど2年目が終わるところだが、かつての学校の活動も入れると、2003年頃から始めて、すでに13年目になるという。
前任校で地球環境部に所属していた生徒たちは、卒業後も継続的なかかわりがあり、週末には相模湖のフィールドに通ってきている。高校生・大学生になった、“地球環境部”の先輩たちと、現役中学生の地球環境部のメンバーたちとの、地域や年齢を越えたつながりもできている。
「子どもたちは森でいっしょに作業しているので、結構仲良くなっています。部活として引退して終わりじゃなくて、森に行けば同じようなことをずっと続けているので、卒業しても気軽に来て参加できるのもこの活動の特徴です。卒業生はそれなりにスキルも高いので、ちょっとこのチームの面倒を見てくれよという感じで面倒見てもらったりできるんですよ。かなり重宝しています」


週末・日曜日の“木こり作業” ──NPO法人緑のダム北相模のフィールドにて
地球環境部の活動は、平日は月火木の週3日間、放課後の16~18時に行っている。ただ、メインの活動は、毎月第一・第三日曜日に通っている、神奈川県相模原市緑区相模湖周辺の森での“きこり作業”だ。宮村先生が所属するNPOのフィールドの一部を責任もって担当する。
いわゆる森林ボランティア【1】の活動をしているわけで、中学生の部活とはいえ、単なる体験活動にとどまらない。ぼうぼうに荒れはてた山の中に連れて行き、木を伐りながら自分たちの手で森の環境を変えていく。そんな経験こそが、森と関わることだし、そうして変わっていく森の姿を目の当たりにできることが中学生たちにとっても大きな手ごたえになっている。
NPOで管理している森は、昨年(2015年)まで10年間にわたって国際森林管理認証であるFSCのFM認証【2】をボランティア団体として世界で初めて取得してきた。今も10年間取り組んできた実績に基づく本格的な施業を行っているのが、同会の活動の特徴の一つにもなっている。
「FSC認証を取っていたレベルの森の管理の一端を、中学生が担っているのです。自分たちが責任もって管理しなきゃいけない区画というのが1haとか2haあって、そこに毎月毎月通って、山仕事の作業をする。これらの区画は、すべて地図上で地番に分けられていて、そのうちの何番と何番の地番をぼくら地球環境部が担当するといった感じで決めてあります。植わっている木の本数も全部数えてあって、524本ある木のすべてに番号を振ってあり、今日は何番と何番を切ったなどと記録していきます。当初の本数の3割ほどを切る計画なので、残りあと何本切るのかデータで管理していますし、切った木も、樹高や直径を測って、森の生長量より多く切り過ぎていないかを確認しています」


年間生長量はあらかじめ計算してあるから、切った木の材積を算出して、年間生長量との比較によって切り過ぎていないかが確認できる。FSC認証の要件として、こうしたデータによる管理も求められてきた。
そうした本格的な施業を中学生にも求めている。昨年までは実際に認証も取得していたから、雑なことをやって落とされたらどうするんだといったプレッシャーも現実的にあった。同じフィールドで活動する大人たちと同じクオリティの作業が求められるが、それが逆に中学生たちを本気にさせることにつながっている。中学校の部活動として参加しているものの、NPOのメンバーの一員でもあり、森を預かる責任もある。山主さんの期待にも応えなければならない。


一年間かけて穴を掘って、ビオトープ池を造成
平日放課後の活動は学内や学校近くで行っている。取材に訪れた日と同様、理科室をベースに部活が始まる。ここでも、基本は実作業を伴う活動だ。たまたま訪れた日は『地球環境部テスト』による話し合いが中心になったが、地球環境部の活動としては珍しい部類だという。作業がメインになり、活動する上で必要な知識があれば、その都度、勉強するというスタンスだ。
「窓の外に池が見えていますよね。地球環境部の活動で造ったビオトープの池です。池の脇の大きな木があることで、日中、池の半分は木陰になって、半分は日が当たるように造りました。明るい環境を好む生きものもいれば、暗い環境を好む生きものもいますから、同じ池でも違った環境をつくることで、いろんな生きものが暮らせるようになるわけです」
もともとただの草地だったところに、一年間かけて穴を掘って、そこに遮水シートを敷いて、池を造成した。部員一同、泥だらけになって土木作業に勤しんだ。近くには野川公園があり、神代植物公園や井之頭恩賜公園など大きな緑地がいくつもある。これらをつなぐ緑の回廊の一つにするのが、この小さなビオトープの役割だ。
ビオトープづくりを始めるにあたって、専門的なアドバイスをしてくれる人を紹介してもらったところ、神代植物公園植物多様性センターの職員がときどき来て、ポイントを教えてくれることになった。池の水深は、浅いところから深いところへと緩やかに変わっていく。水が多くなると、隣に作ってある田んぼに流れていく。そんなポイントごとのアイデアをもらいながら、一からつくりあげていった。
池ができて、鳥も来ているし、トンボをはじめとする昆虫類もたくさん飛んでくるようになった。


「なかなか水質が安定しないなど、まだまだ課題は多いんですよ。でもそんな課題をみんなで考えていくのがおもしろいかなと思っています。大人の側ではある程度ストーリーもあるんですけど、そこは結構子どもたちが自分たちでこうしたいああしたいと言ってくるので、任せるようにしています。野川公園で捕ってきたエビを入れたり、水の中に生える植物を植えたりと、自分たちで考えて試行錯誤していますね」
放したエビは、鳥のエサになってしまったのか、いつの間にかいなくなってしまったという。とりあえず水質を測ってみようということになったが、何をどう調べたらいいのかもわからない。そんなわけで高校の生物のテキストをベースにした『地球環境部テスト(生態系編)』で基礎的な知識を勉強した。ビオトープを造るのに、水質や遷移の基礎を知っておく必要があるからだ。勉強の成果を生かして注文した水質調査のパックテストが、ちょうど届いたところだった。


ビオトープづくりの作業について、部員たちにも話を聞いた。
「池を造ったんですけど、自然にあるものを自分たちの手で造りあげるのがすごく楽しかったです」
作業の楽しさを口にする人がいる一方で、失敗が印象に残っているという人もいた。
「1学期に田んぼを作って、稲を植えたのが印象的でした。ビオトープに水生植物を植えたり、田んぼを耕したり、今まで本でしか見たことがなかったことだったので、楽しかったです。ただ、残念なことに、収穫の直前に野鳥にやられてしまって…。あっという間に全部食べ尽くされてしまいました」
防鳥網も買ってあって、そろそろ張ろうと思った矢先の出来事だった。自然界の生存競争の激しさを実感した経験だったという。前年は、発泡スチロールの中で稲を育てた。その時は鳥もまったく来なかったから油断していたと反省する。今年はビオトープができて、普段から鳥も訪れていて、ねらわれていたのかもしれないとみている。
「稲のこともそうですけど、1回だけでは簡単には成功できないんだなというのがよくわかりました。どうやって水質を改善していくかなど、いろんな対策を考えながら、実際に取り組んできました。今は、太陽光で発電しながら酸素を送り出す装置をつけて、水質の浄化を図っています。そんなふうに一つずつ、こうしたらどうだろうと考えながらやっているのがおもしろいですね」
そんなふうに話す部員たちの表情からは、自分たち自身で考え、話し合いながら活動をつくりあげていく楽しさを満喫している様子がうかがえた。
3万個の積み木を組み上げてつくってきた、東京駅やアンコールワット
「平日の放課後の活動は、今日みたいにミーティングをしたり、ビオトープの作業や芝生の管理をしたりしています。それと、間伐材の積み木が3万個あるので、その積み木を使ったイベントもたまにやっていて、イベント前には試作を作ったりもしています。上智大学の先生に教えてもらってアンコールワットを積み木でつくるイベントは5年連続の恒例イベントになっています。3万個の積み木で作るアンコールワットはかなり迫力ありますよ」
積み木は、板状のもの、ブロック状のもの、台形状のものの3種類があり、板は3枚重ねるとブロックと同じ厚さになる。これらの部材を組み合わせることで、どんな形もつくりだすことができる。過去には、法隆寺を作ったり、東京駅のエキナカで東京駅舎を作ったりするイベントなどもした。
「東京駅では、ちょうど復元工事が完了した年に、八重洲北口のエキナカで、10日間ほどかけて、通行する人といっしょに積んで東京駅舎を作るという企画を実施しました。通りがかりの子どもたちにも手伝ってもらって完成させました。現実の姿をできるだけ正確に再現するため、いろんな資料を集めてもらいましたが、裏側の写真はいくら探しても見つからなくて。裏は見せなかったんですけど、結局、高さ合わせで積み上げるだけになってしまいました」


歩いて20分ほどのところにある国立天文台でも、竹林整備の作業を手伝っている。
「月曜日の放課後を中心に、一応は年間スケジュールも立てていますが、雨が降ったりすると流れてしまいますから、まあ目安程度です。だいたい月1回・2回のペースで、竹を切って、ばらして並べてという作業をしています」
切った竹は学校に運んできて、ビオトープの仕切りに使っている。冬場は日も短く、20分かけて歩いて行ってもすぐに日が落ちて暗くなってしまうため、夏場メインの作業だ。
春先には、スズメバチの親蜂を捕るトラップを仕掛けたところ、わんさか捕れた。天文台では、一般公開の施設見学や公開観察会も実施しているから、スズメバチは悩みの種になっているようで、喜んでもらえた。
そんな、山仕事だけにとどまらない、文化面や暮らしの面も含めた関わりができるのが中学校の部活としてのおもしろさだと宮村先生は言う。




地球環境部の名称のインパクトと活動の内容に惹かれて
できて2年目の部活ということもあって、地球環境部の現在の部員は、1・2年生中心に18人が在籍している。
「2年生が6人、1年生が10人。3年生も今は受験で参加率が低くなっていますが、2人いて、受験が終わったらまた来たいと話しています。塾や家庭の事情で山には来られない子もいますから、前任校の卒業生も入れると、山での実働は毎回20人くらいです。山仕事をするにはちょっと多いかなという感じですね。切った丸太を運んだりするのに、人が多い方が楽にはなりますが、安全面やチームとしての効率からいうと10人くらいの方がちょうどいいんです」
日曜日の活動は強制してはいない。ただ、山仕事が活動の本筋だという話はしている。事情があって来られないのは構わないけど、でも来なかったら腕は上がらないよというわけだ。普段やっていないことをやる部活だからこそ、1回でも森に来て、1本でも木を切らないとうまくはならない。
部員たちが、それぞれどんな動機で入部しているのか、一言ずつ話を聞いてみた。
「地球環境部という名前のインパクトがすごかったんですね。実際に山に行って木を切るということを聞いていて、テレビでしか見たことがないことだったので俄然、興味がわいてきました」
「私は、奈良の田舎からこっちに越して来て、もともと森が大好きだったんです。他の部活の仮入部にも行きましたが、ここでしかできそうにない課外活動が楽しそうで、入りました」
小学生の頃から庭に花を植えていたという人もいる。
「自然とふれあえる部活があったらいいなと思っていたんです。中学生になって、部活発表のときに『地球環境部』と言われて、何それと思って聞いていたら、森で間伐とかをして社会に貢献してという話だったので、入りたいと思いました」

では、実際に入部して、期待通りの活動はできているのだろうか。
「木を切っているときにノコギリが噛んじゃうとすごく重くなって大変です。でも、ようやく木が倒れたあと、葉っぱがあったところにぽっかりとあいた空が見えて、そこから光が射し込んでくるんですね。そんなときに、すごい達成感が得られます。ただ、思った通りに倒れてくれず、途中で隣の木に引っかかったりすることもあります。その時の面倒くささといったら!!」
現地の活動を通じて徐々に積極的なかかわりができるようになったという人もいる。
「前回森に行きまして、レバーで操作しながらワイヤーロープで引っ張って伐倒方向を決める道具をはじめて使いました。これまでは山に行っても、体力はないしノコギリを使うのも下手なので、木を切り倒すことには全く関与してこなかったんですけど、この道具はレバーを引くだけだったので、自分にもできるかなと思ってやったら、もう楽しくて。最後に木を倒すのが自分だったんですけど、すごく楽しいなと思いました。ただ、扱いに慣れてきたところで、ちょっと失敗もあって、楽しくても、また使い方がわかっても、やっぱり、この活動はまわりを見ることが一番大切で、それを重視しないとやっていけないなと思いました」
森の活動に参加すれば、現地には教えてくれる人がいて、道具も一通りそろっている。
「ノコギリやヘルメットなどの道具類も必要ですし、伐倒方向を制御するためのウィンチベルトやロープを購入すればすぐに万単位のお金がとんでいきます。そんなときに、中学生・高校生を応援してくれる助成金も出してもらっていて、助かっています。今年度は、NPO法人22世紀やま・もり再生ネット、東京都公園協会、日本環境協会藤本倫子こども環境活動助成基金の3つをいただきました。実際、彼らの負担は交通費だけで済んでいますからね」
宮村先生がそう説明する。
道具はほとんど現地の倉庫に保管してあるが、ヘルメットとノコギリは個人に渡していて、自分で持って来させる。自分の道具として渡すことで、刃に詰まった切りカスを取ったり、錆止めを塗ったり、刃の状態を見たりと、毎回活動の前後に手入れもするし大事にもする。道具に対する愛着を持って活動に臨むことにつながる。
「今の子はそういう感覚がなくて、壊れたら買い替えればいいんでしょとか平気で言いますけど、そうじゃねえぞと。自分のノコギリだぞ、雑に使って切れなくなって困るのはお前だぞ、と言っています。なので、一生懸命手入れしていますよ、あいつら」
部として虫などを飼育してみたいという人もいる。山の作業だけでなく、地元の川の外来魚問題についても関わっていきたいという希望もあった。だったら、川の活動をしている人も知っているから、流域つながりで何かできるとおもしろいかもしれないねと話が発展していく。
ビオトープについて教えてくれている神代植物公園の研究員や、竹林整備で関わっている国立天文台、間伐材積み木では建築物の専門家から図面や写真を提供してもらっての活動もある。もちろん、メインフィールドの山に入れば、頼もしき“先輩”たちの存在が部員たちの憧憬の的になる。そんな、多くの人たちに支えられた地球環境部の活動を引き継ぐ存在として、先輩たちのような存在に成長していきたいという思いは、現部員の共通する思いかもしれない。
「地球環境部に入って、最初は何もわからなくて──まあ今もわからないんですけど──、先輩たちにやり方を教えてもらいながら活動してきて、すごく頼りになるなと思ったんですね。もうすぐ後輩が入ってくれば、これどうするの?と聞かれることもあると思うんです。今はまだ知識が乏しくてうまく答えられそうにありませんが、テストに書いてあることくらいはマスターして、軽くやり方を教えられるくらいなりたいなと思っています」

注釈
関連リンク
こうした活動が評価され、環境関連のコンテストでの入選も相次いでいる。