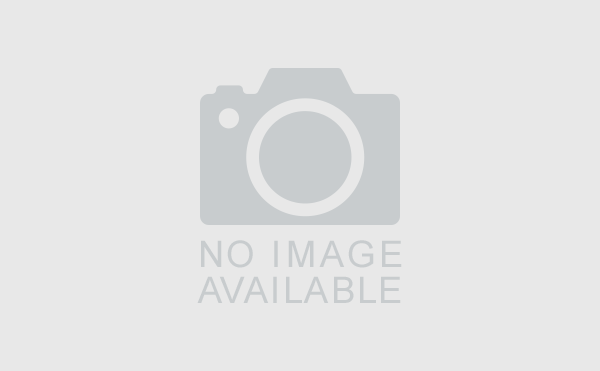かれん と シーナの『エコ質問箱』質問04
2016.05.27
緑のカーテンって、なぜ“カーテン”なの?

先日、学校でゴーヤとヘチマの苗の植え付けをしたの。これから夏に向けて「緑のカーテン」を育てるのよ。

「緑のカーテン」って何?
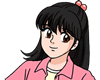
え? シーナは「緑のカーテン」を知らないの? ほら、ゴーヤなんかのツル性植物を壁際に張り出したネットに這わせているのを見たことない?

言われてみると…あったかもしれないなあ。
でも何でそんなことするの?
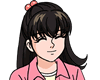
緑のカーテンを育てると、窓からの直射日光を遮ってくれるから、教室の中もだいぶ涼しくなるのよ。

へえ、そんなことをしているんだ。人間の生活って、いろいろと大変なんだね。ぼくの生まれ育った森では必要ないからね。

森に入ると涼しくて気持ちがいいからうらやましいわ。
じゃあ、昨日聞いた先生の話や、去年の上級生たちが育てていたのも見ていたから、今回は私がシーナに教えてあげようかしら。

よっしゃ、頼むよ!
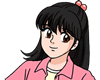
えへん。ではまず、緑のカーテンの特徴について。
日除けに使われるものには、ブラインドや簾もあるけど、これらは日が当たり続けると熱を持っちゃうんだって。
でも緑のカーテンは生きている植物だから、根から吸った水を葉っぱから出して、まわりの気温を下げる効果があるんですって。

蒸散作用だね。

さすが! よく知っているわね。
そうそう、生きている植物じゃないけど、最近よくあるドライミスト装置も細かい霧を吹いて涼しくするんだって。
うちの学校でも運動会の時にはテントを立てて、簡単なミスト装置をつくっているわ。

水滴が蒸発して液体になるときにまわりの熱を吸収するんだ~。
炎天下の校庭は暑いからね!
ところで、緑のカーテンを作るのに適した植物ってあるの?

よくあるのは、ゴーヤよね。ゴーヤは、実を食べる楽しみもあるのよ。
去年の授業では、苦くないゴーヤのケーキや葉っぱの天ぷらなんかも作ったらしいわ。今年も作るのかしら。
それから、うちの学校ではヘチマもいっしょに植えているの。ヘチマは葉っぱも大きくて生長もいいから、学校の校舎を覆うくらいの高くて大きな緑のカーテンを作るのに最適なんだって。

いろんな種類の植物を組み合わせて作っているんだね。
ところで、なんで『カーテン』っていうのかな。カーテンみたいに開け閉めできるわけじゃないんでしょ?

実は、私もそう思ったから、先生に聞いてみたの。

うんうん、そうしたら?

一つは、風にそよいで揺れる様子がカーテンのように見えるかららしいわ。
壁面緑化と言って蔦植物を壁に這わせることもあるらしいんだけど、緑のカーテンの場合は壁や窓の間に隙間をつくって風通しをよくすることが多いらしいの。
裏側から透けて見える光が緑に輝いてきれいなんだって。「壁」って言っちゃうと、ちょっと堅そうだものね。
もうひとつは、カーテンのように自由に開け閉めすることはできないんだけど、実は開け閉めできているんですって。

え~!どういうこと?
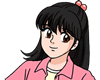
ふふ、なぞなぞみたいでしょ。
緑のカーテンって、夏の暑い期間に葉っぱが影を作って涼しくしてくれるけど、冬になって陽射しを入れたい季節には葉っぱが枯れてなくなるじゃない。
一年を通してみると、緑のカーテンって開け閉めできているんだよっていうことなんだって。

なるほど! 確かに開け閉めしていることになるね。

だから、緑のカーテンとして使うツル性植物は一年性のものが多いらしいんだって。

一年中葉っぱが茂った常緑植物だと、冬の寒い季節も日を遮って、寒々しくなっちゃうよね。
Question
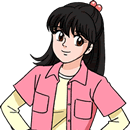
では、ここで読者の皆さんに質問です。
緑のカーテンを生長させるため、ある程度ツルが伸びた段階で、先端部をハサミでチョキンと切り落とすそうなんですが、その理由は?
A1 先端部を切ることで、葉っぱの付け根からたくさんのツルを出すようにするため
A2 先端部を切らないと、栄養分が葉っぱやツルの生長に使われてしまい、実が成らないため
A3 先端部を残しておくと老化を早めてしまい、夏の盛りを過ぎる前に枯れてしまうため

解説

答えは、A1です。
ツルの先端を切り落とすことを「摘心(てきしん)」と言います。これをすることで、脇芽を出して、分岐しながら横方向にも伸びていくので、網状に広がった緑のカーテンができあがるんですって。
摘心しないまま伸ばしちゃうと、ひょろひょろと伸びて、葉っぱがスカスカな、カーテンとしては寂しい状態になってしまうんです。
これ、大事なポイントですよ!
ちなみに、今月のエコアカデミーは、「緑のカーテン」の効果と育て方3つのポイント ということでNPO法人緑のカーテン応援団理事の小堺千紘さんが解説していますので、そちらもぜひご覧くださいね。