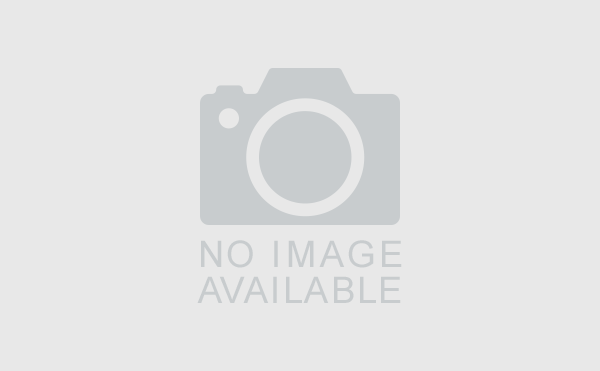かれん と シーナの『エコ質問箱』質問14
2017.03.21
東京23区内に小水力発電機があるって、ほんとう?

ねえねえ、シーナ、小水力発電って知っている?

え、ダムのこと?
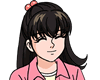
それは水力発電所と言った方がいいわね。「小」とついているように、規模が小さい発電装置のことを言うらしいの。

小さいってどれくらい?

一般的には1千kW以下の発電容量のものを言うんだって。そのうち特に100kW以下のものをマイクロ水力と呼んで区別することもあるそうよ。
田園地帯などに設置されることが多いんだけど、実は東京23区にも設置されているものがあるんだって。知っていた?

へえ、知らないな。どこにあるんだい?
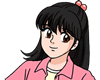
江東区の川にあるの。実はこの間、実際に現地を見に行ったの。発電装置自体は橋のたもとの水面下にあるんだけど、橋の上には発電の仕組みや発電量を表示するモニターが置かれていて、この下で発電しているんだっていうのがよくわかったわ。



江東区は、街の中に河川や運河が縦横に流れていて、“水彩都市”を標榜しているよね。もともと、「江東」という名前は、隅田川の東に位置するという意味で江戸時代の頃から使われていたらしいよ。
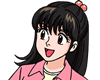
え? 「江」って、隅田川のことなの?

ほら、中国に「長江」とか「揚子江」っていう大河があるでしょ。中国では大きな川(河)のことを指して「江」ということもあるんだって。東京にある大きな川の東に位置するということで「江東」なんだって。
いずれにしても、街の特徴を生かした面白い取り組みだね。
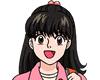
そうなのよ。発電装置のある橋は、横十間川(よこじっけんがわ)にかかる水門橋という橋なんだけど、周辺は親水公園として整備されていて、とても気持ちのよいところなの。今度はシーナもいっしょに行ってみましょうよ。


いいね。ぜひ見てみたいな。ところで、小水力発電って、都内の川にも設置できるんなら、もっといろんなところでエネルギーの有効活用にできそうだよね。。

再生可能エネルギーとしてはこれまで太陽光発電や風力発電が先行してきたけど、小水力発電の可能性も注目されているらしいの。

太陽光や風力と比べてどんな利点や短所があるの?
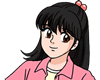
聞き売りになっちゃうけど、天気次第・風任せのソーラーや風力に比べると、水の流れは年間を通じて安定しているから、発電量も安定して、電力会社にも接続しやすい点がまず第一にあるわ。天気や気象条件で変動が大きいと需要と供給のバランスが取れなくなって、調整が難しいらしいのね。それと、装置もコンパクトにできるから設置しやすいんだって。

なるほどね。じゃあ、逆に短所は?

やっぱり設置できるところが限られる点ね。落差や流量がある程度ないと、効率的な発電ができないからね。それと、水の使用にはいろんな利害関係があるから、調整や手続きが大変らしいの。

なるほど、水利権なんかは面倒くさそうだね。それに、落差と流量がないと難しいと言ったけど、場所によって落差も流量も違うだろうから、2つの要素に合わせた機器の開発とか調整も必要になりそうだね。

それも難しい点の一つね。なにより、同じ再生可能エネルギーでも、太陽光発電や風力発電と比べて、小水力発電に対する一般市民の認知度が低いことも問題ね。

そうだね。ぼくも知らなかったからね。

江東区の小水力発電設備も、“水彩都市のシンボル”として、観光や環境学習に活用しながら、小水力発電について普及啓発していく役割を担っているのよね。
読者の皆さんも、機会があればぜひ見に行ってくださいね!
Question

では、ここでクイズです。
江東区の小水力発電で生み出された電力は、何に使われると思う?
1)売電している。
2)橋のライトアップとモニターを表示するための電力として使用する。
3)区役所の庁舎で使う電力をまかなうために使用されている。
さて、どれでしょう?

解説
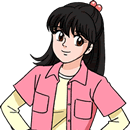
答えは、2)。
夜に橋をライトアップするためのLED照明や、表示モニターを動かすための電力として使われています。
モニターでは、現在の発電量や総発電電力量を表示するほか、環境学習情報や周辺の案内も表示しているんですって。近くに来ることがあれば、ぜひ見てみてくださいね!