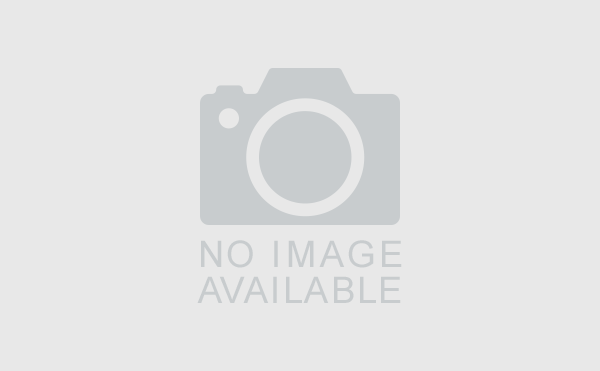かれん と シーナの『エコ質問箱』質問19
2017.09.15
トビハゼの営巣地がごみで埋っているんだって!

ねえ、シーナ、トビハゼって知っている?

ハゼっていうと、魚の仲間かな?
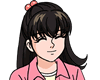
そうそう。河口域などの干潟の泥上を這い回ったり、泥の中に垂直の穴を掘って縄張りを作ったりしているんだって。

干潟の泥を這い回る魚っていうと、ムツゴロウみたいな感じかな?
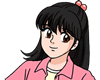
そうね。ただ、ムツゴロウは日本では有明海・八代海周辺だけにいて、トビハゼの方がムツゴロウの半分くらいの大きさしかないんだって。名前の通り、ぴょんぴょん飛び跳ねる小さな魚よ。

ふ~ん。それで、そのトビハゼがどうかしたの?

もともと日本を含む東アジアで普通に見られる魚らしいんだけど、東京湾が生息北限なんだって。

へえ、そうなんだ。じゃあ、東京都に住んでいるぼくらにとっても特別な魚なんだね。
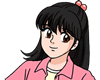
そうなの。ところが、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧に指定されているらしいの。

準絶滅危惧ってどういう意味?

ええと、「現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種」とあるわ。

ということは、まだ大丈夫なのかな?

でも、都道府県別のレッドリストでは、東京都区部や静岡県、三重県などで「絶滅危惧IA類」に分類されているから、都区部のトビハゼはだいぶ危ないんじゃないかな。

絶滅危惧IA類というと、「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」とあるから、もっとも条件の厳しい分類だね。
原因はなんなの?

埋立てによって泥干潟がなくなっているのが最大の問題なんだけど、水質の悪化も原因の一つだったそうね。工場排水などの規制や下水道の整備などによって水質は改善してきて、個体数も回復傾向にあるらしいわ。都区部では、多摩川や荒川など東京湾に注ぎ込む河口域などに生息地が残されているんですって。

河口近くの橋の下には泥干潟地帯があるよね。いつだったか、かれんたちもトンボやカニの観察に行ったんじゃなかったっけ?
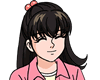
男の子たちが泥の中に手を突っ込んで、こんなに大きなカニをとっていたわ。

へえ、東京にも案外豊かな自然が残っているんだね。

う~ん、そうなんだけど、東京湾のトビハゼにとってもう一つ問題になっていることがあって、それが私たち人間の出すごみだったの。

どういうこと?

川を流れてくるごみが、河口域の泥干潟に寄せてきて、どんどん溜まっているらしいのよ。トビハゼだけじゃないんだけど、泥に穴を掘ろうとしてもごみが被さって邪魔してしまうんだって。

ごみはどこからくるの? 道を歩いている人が投げ捨てているの?

それもあるかもしれないけど、陸地のごみが風で飛ばされたりして、流域全域から流れ着いているのよ。もちろん、河口域でとどまらずに海に流されていくんだけどね。前に話したマイクロプラスチックも、そうして陸から流されてくるプラスチックごみが原因よね。

う~ん、いろんなところに問題が表れてきているんだね。何とかできないのかな?
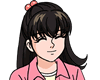
自然環境保全のNPOがごみの清掃活動プロジェクトを始めているらしいわ。私が東京のトビハゼの問題を知ったのも、そのプロジェクトがきっかけだったの。

妙に詳しいと思ったら、そういうことか。
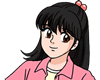
えへ! でも、ごみの清掃活動って、ある意味、対処療法じゃない。根本解決のためには、東京都区部の河口干潟を生息北限にするトビハゼの問題を私たちがきちんと知って、トビハゼの生活に寄り添う気持ちを持つことだと思うの。そうすることで、川を通じて流れ込む都市のごみ問題の解決につながるといいなと思うのね。

そうだね。多くの人に知ってもらいたいし、ぼくもごみを出さない生活を心掛けたいと思うよ。
Question
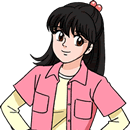
そうね。気を付けましょうね。
さて、それではここでクイズです。
トビハゼは警戒心が強いから、人が近づくとさっと穴に隠れてしまうらしいの。どうやってカウントしているかわかる?
A1 日本野鳥の会の人たちが双眼鏡とカウンターを手に、数えている。
A2 巣穴の数を数えて、トビハゼの個体数を推計している。
A3 上空から赤外線スコープで泥の上・中を問わず個体数がカウントできる

解説

答えは、A2の「巣穴の数を数えている」でした。
干潟にはカニの仲間など泥に穴を掘る動物がたくさん生活しているから、区別して数える必要があるそうです。トビハゼは、口の中に泥をふくんで巣穴の外に吐き出しているから、入り口近くに吐き出した泥の塊があれば、トビハゼの巣穴ということがわかるんですって。

へえ、おもしろいね。ぼくが見てもわかりそうにはないけど…。