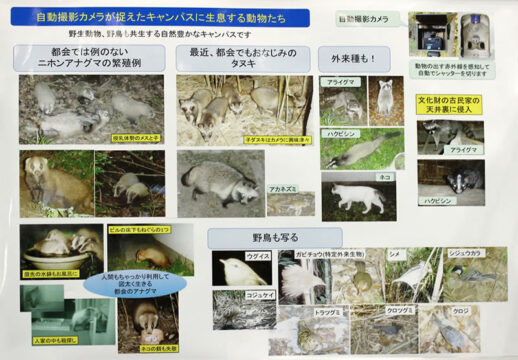【第69回】火山との関わりの中で形成された島の地質と生態をガイドする ──伊豆大島ジオパークのエコツアー(グローバルネイチャークラブ)
2016.02.23
火山島・伊豆大島の2つの港
日本列島が大寒波に見舞われた1月中旬。その数日前に伊豆大島(東京都大島町)を訪ねた。名前のとおり伊豆諸島で最大の大島は、面積約90km2に約8千人が住む。東京・竹芝桟橋からの距離約120km、高速船なら約1時間45分で到着する。伊豆半島付け根の熱海からは46km、わずか45分の船旅だ。主な港は西海岸の元町港だが、天候によっては北東面にある岡田港に着岸する。この日の到着口は、その岡田港だった。濃緑の葉っぱが茂る木々に覆われた崖が迫る、いかにも島っぽい雰囲気の港だ。
「ここ岡田港は、数10万年前の古い火山が波に削られて崖を作っているところです。現在活動中の火山が古い火山の沢を伝って溶岩を海まで流し、人が暮らせる地面を作りました。一方、島の西側は、現在活動中の火山が海まで溶岩を流し、なだらかな斜面を作ったので人がいっぱい住んでいるんです」
伊豆半島の陰に位置している大島は、海況が比較的穏やかなため、船の就航率も他の島々よりも高く、訪れやすい島といえる。定期航路も東京発着の大型船や高速船の他、熱海発着の高速船もあり、一日に複数便が行き来している。
「他の島の場合、一日一便ですから、欠航すると何日か足止めされます。でも、島の暮らしってそんな感じで、その不便なリズムで生活しているのです。私も他の島に行きますが、どの島に行っても『大島は島じゃない』と言われるんです。一日に何便も東京に出入りできるなんて、便利すぎるっていうのですね」
大島の成り立ちと島の人々の暮らしについて説明してくれたのは、この日ガイドを頼んだグローバルネイチャークラブの西谷香奈さん。大島に移り住んで28年。ガイドを始めてから7年、今や年間130~140日はツアーに出ているという。

大島の噴火の歴史が造った景色が一望できる山頂口展望台
港から、三原山登山道路をたどって終着点の三原山頂口までは、車で25分ほど。標高約555mまで一気に上がってきたことになる。駐車場から降りてすぐの展望台からは65年前の噴火でできた最高峰の三原新山(標高758m)をはじめとした外輪山の稜線の連なりが望める。その手前、眼下に広がる平坦な窪地は、所々に草木が生える荒涼とした溶岩地帯。江戸時代に繰り返し起こった大噴火によって山体が吹き飛ばされ形成されたカルデラ地形だ。山頂を望むこの展望台も外輪山の一部に当たるという。
「目の前に広がる窪地は、昭和25~26年の噴火の前までは、火山灰に覆われた、いかにも砂漠という風景が広がっていました。“表砂漠”と呼ばれて、馬やラクダに乗る観光が盛んなところだったのです。軽い砂は風で動いてしまうので、植物の種が定着できず、草の生えないところでした。ところが、噴火によってあふれ出た溶岩流が“表砂漠”の大部分を呑み込み、冷えて固まった溶岩の窪みなどに植物が定着するようになって、やがて草原が広がり、さらに木が生え始めて、徐々に森ができてきているのが今の状況です。このうち一部は、30年前に起きた直近の噴火によって再び焼かれました。低木の森が広がりつつあるところと、焼けたあとの草地を比較して見ることで、火山島・大島を実感してもらえる場所です」
溶岩で覆われた黒い焼け野原の上に一番最初に芽を出すのは、固有種のハチジョウイタドリという草だ。溶岩の隙間に挟まった種が芽を出し、地下に長い根を伸ばしながら生長していく。株が大きくなって、落とした葉っぱが根元に溜まると次第に土を肥やし、他の植物も侵入できるようになって、徐々に草地に覆われていく。
草原の最終段階ではススキが分布を広げていって、次第に背が高くなって全体を覆い尽くすようになると、ひととき景色を独占する。10年ほど前には、ここ一帯も輝く海のようなススキ野原の景観を作っていたが、徐々に低木が入ってきて、年々生長してきている。


ガイドの西谷香奈さん。





「火口のそばに生え始めることができる強い常緑の木は、主に2種類に限られています。ツバキ科のヒサカキと、楕円形の葉っぱのハチジョウイヌツゲという木です。さらにこの後、何百年も噴火しないまま安定した状態が続くと、ドングリが生るようなスダジイなど、より大きくなる木も入ってきます。ただ、たいていはそうなる前にまた焼けてしまい、再びゼロからの回復が始まるのです。そんなことを繰り返しながら今に至っているのが、大島の自然です」
常緑樹のヒサカキやハチジョウイヌツゲが生えてくる前、草原の中でいの一番に生えてくる木は、落葉樹のオオバヤシャブシだ。根っこのコブにはバクテリアが共生していて、空気中の窒素を取り込んで固定してくれるため栄養の乏しいやせた土地でも生育できる。
オオシマザクラも強い木で、30年前の前回の噴火で溶岩が流れたところにも生えてきている。ある1本の桜の木は、人の背丈ほどに生長して、昨年、初めて蕾を出した。その前の年まで、葉っぱだけで生長して、一生懸命光合成をしてため込んだエネルギーがようやく花開こうとしていたわけだ。残念ながら4月になって雪が降り、花が開く前に茶色く変色して枯れてしまったという。これもまた自然界の厳しさなのだろう。

展望台の近くに設置された観測機器。上部についているミラーが離れた山にある観測機器から届くレーザー光線を反射して、その時間差によって島の変化をミリ単位で観測している。この他、GPSや傾斜計、温度計など、次の噴火を予測するためのさまざまな機器により、常時観測している。現在、地下のマグマ溜まりには、前回の噴火直前の約2倍量のマグマが溜まっていることがわかっているという。
「ああ痛い!」と足裏を刺激するゴツゴツ溶岩と、ホイホイ歩ける平滑な溶岩
三原山頂口から火口方面に向かう溶岩地帯の中の遊歩道では、植物の再生の様子とともに、大島の特徴的な溶岩の姿が見られる。
「大島の溶岩は、ガラガラのものと滑らかなものと2種類あります。滑らかな溶岩は、マグマの温度が高いときにできます。そうしてできた溶岩には、植物の種が飛んできても引っ掛かりがないため風で飛ばされて定着できず、芽を出せません。だから、この辺はまだ空き地が多いんですね」
噴火のスピードが速いと、高温の溶岩が噴出するから、広がりが早く流れていく。お菓子づくりが好きな人なら、チョコレートを鍋で熱するとサラサラになるのがわかるでしょうと、西谷さんは説明する。
「もう一つのガラガラ溶岩は、溶岩の温度が低いときにできます。マグマの温度が下がると粘りが出てきて、流れがゆっくりになるので、表面が冷やされて固まってきます。ところが、内部は温度が高いまま流れていこうとするため、固まり始めた表面部分をガシャンガシャンと砕きながら流れて、ガラガラ・ゴツゴツの岩ができるのです。これを裸足で歩くと“アア痛い!”というので『アア溶岩』、さっきの表面が滑らかな溶岩は、裸足でもホイホイ歩けるから『パホイホイ溶岩』と呼びます。

冗談めかして解説するが、アア溶岩もパホイホイ溶岩もハワイ語を語源とする専門用語だ。ただこうした専門用語を覚えてもらうよりも、わかりやすい言葉で印象付けていくことを大事にしているという西谷さんだ。地面を踏みしめながら歩くと、カラカラと音が鳴る。溶岩が流れていたときはもう少し高い音がしたというが、そんなふうに音を感じながら歩くのも、また一味違った溶岩体験になる。
表面が滑らかなパホイホイ溶岩は、ところどころで縄状の模様を形作っている。よく見ると、波のように放射状に広がっているのがわかり、流れていった方向がわかるものもある。すぐ隣には、逆方向へ流れたものもあって、周辺一帯を溶岩流が渦巻いていた当時の様子が何となく思い浮かぶ。
「ここ、わかりますか! 溶岩が盛り上がった先端がパカッと割れて、どくどくどく…と流れてきた跡がすごくわかりやすくなっています。いつも寄っているところなんですけど、この上に登って、お尻を向けて腰を落ち着けてもらって、“あ、お腹すっきりしましたか!?”なんて言ってネタにしています。この周辺はとぐろを巻いたような溶岩など、形を楽しめる場所がいっぱいありますから、1時間くらい遊んでも飽きません」
さらに進むと、細かい黒い粒が砂状に堆積している場所がある。専門家がスコリアと呼んでいる、黒い粒の岩石だ。空高く噴き出したマグマが、空気中で冷やされて固まって、その状態のまま数十cmも降り積もった。この小さい粒も、拡大鏡で覗くと溶岩の発泡した穴が観察できる。




西谷さんが持ってきた拡大鏡で、手のひらに乗せた小さな黒い溶岩粒を観察。
200年かけて再生した樹海の森と、かつては薪炭林として使われた“ちぢれラーメンの森”
火口付近の溶岩地帯から、車に乗って、山腹の森が再生しつつあるエリアに移動する。240年前の噴火で広範囲に焼かれた後、ゼロから再生してきた森だ。地元のガイドが“樹海”と呼んでいる常緑の低木が優占するこの森では、山頂付近の溶岩地帯とはまた違った、緑濃い大島の自然を体感することができる。
「ここの森では、イヌツゲとヒサカキが優占して、そこにサクラがちょっと混ざってきています。江戸時代の1777年に始まった噴火によって、ここ一帯はすべて溶岩に覆われました。そのときゼロから始まった森が240年ほど経って再生してきていますので、そんな森の中をちょっとだけ歩いてみたいと思います。木が生い茂っていますが、実は土はほんのわずかしかなくて、溶岩の上に根を張っている様子がよくわかるところです」
整備された幅の広い遊歩道から、森の中の小道に分け入っていくと、そこはまさに原生林の雰囲気ただよう溶岩の森だ。ほとんどの植物が、ゴツゴツした溶岩の上に乗っかって生長しているだけで、浅くしか根が張れていない。
「このあたり、すごくふかふかでいい土があるような感じなんですけど、すぐ下はゴツゴツの溶岩層です。土は本当にちょっとしかないんですよ。ただ、亀裂があったりすると根を伸ばしていけます。うんと厚い溶岩は割れませんが、ちょっとでもひび割れがあると根っこが入り込んでいって割れ目を広げていきます。そうやって根が入り込んでいくと安定するのですが、表面だけだと、ちょっとしたことで浮いたり倒れたりします」
そう話す目の前では、ちょうど倒れかかって、根っこの裏側を見せているサクラの木が横たわっている。
「このサクラの木は、背が高くなりすぎて、強風か何かで倒れたようです。溶岩の上で横にしか根を張れなかったんでしょうね、タコみたいに四方に根を伸ばしています。根っこの裏から覗くと、どこか悲しそうな表情に見えませんか? 倒れたときに根も引きちぎれたと思いますが、まだ少し残っていて、半身で幹を支えています。相当弱っていますが、それでも何とか生きようとしているところが、独特の雰囲気を醸し出します」



溶岩層の上に根を張る木々。割れ目があったり薄いところがあったりすると根を伸ばして張り出していく。厚いところでは割れずに横に張り出していくだけだから、高く生長すればそれだけ不安定になる。


倒れかけて、たこ足のように張り出す根っこをみせるサクラの木。
歩きながらも、西谷さんの話は止まらない。森の中には、溶岩や植物だけでなく、動物の痕跡も見られる。木の根元から、色鮮やかな赤い小さな球体がボロボロとこぼれ落ちているのを見つけた西谷さんが大きな声をあげる。
「あ、こんなところにガの幼虫のフンがあります! ゴマフボクトウというガの幼虫で、林業の世界では害虫です。木の幹を食べながら入り込んでいって、孔から丸めたフンを掃き出します。きれい好きなんですね。この木はヒサカキですが、材質が赤味を帯びているためフンも赤くなります。イヌツゲは材色が白いので、白いフンになるんですよ。この木は新しいフンが出ていないようですから、季節的にも中でサナギになっていて、夏に出てくるんじゃないですかね。自然の森では爆発的に増えることはなくて、たまにあった!という程度です」


ヒサカキの根元にコロコロと小さな赤い球体がこぼれ落ちている。木の幹に入り込んだゴマフボクトウが孔から吐き出したフンだ。ヒサカキは赤みを帯びた木色をしているため、ゴマフボクトウのフンも赤くなるのだという。
少し歩いた先の木の根元には、鳥の羽が散乱した捕食跡が見つかった。
「これ、食べられていますね。この間までなかったから最近ですよ。キジバトだと思います。この辺で一番多い種ですし、この茶色っぽい羽根は胸の辺りの羽毛じゃないですかね」
さらに進んだ足元には、なかば干からびて変色したミミズが横たわっている。
「うわーこれなんだろう。ちょっと干からびていますけど、ミミズですね。実は、この辺の下の土を調べてみたら、団粒構造になっていることがわかりました。ちゃんとミミズが食べて、吐き出して、泥団子のような土ができているのです。こんなところにもちゃんとミミズがいるんだと、ちょっと感動的でした。その時におもしろかったのは、泥団子の中に細かい溶岩の粒があったんです。溶岩の粒ごと食べて、フンといっしょに出しているんですね。さすが大島のミミズだなと思いましたね」
コースの半ば過ぎになって、火口までのぼっていく道と森の入り口に戻るコースの分岐に差し掛かる。火口まではツアーだと約2時間の行程。今回は、外輪山の麓をまわってもとの入り口まで戻る。

まだ真新しい、キジバトが捕食された現場の痕跡だ。
「この辺に来ると、あまりゴツゴツの溶岩は見られなくなってきます。この少し奥の方に行くと、炭焼き窯の跡があるらしいんですよ。かつて、島の住民は燃料として使う薪や炭を取るため、この辺りの木を切っていたようです。大島は水捌けがよく米が穫れないので、江戸時代には海水を焚いてつくった塩を年貢として納めていましたから、その燃料として薪や炭が大量に使われたのです。
ここのイヌツゲは、ひょろひょろしていて変ですよね。薪炭林として切られたあと、ひこばえした細い木が乱立したようです。イヌツゲはすごく柔らかい木なので、雪の重みでも曲がりますしまわりに細い木が密集しているため、横に太れないでひょろひょろの木に生長したんでしょうね。そんなふうにさまざまな条件が重なって、ちょっと変わったクニャクニャの森ができたようです。“ちぢれラーメンの森”なんて言って紹介しています」


西谷さんが“ちぢれラーメンの森”といって案内している、かつて薪炭材を切っていた、イヌツゲの森。
山が崩れて流れてきた土砂が、植物の回復を促進した
1986年の噴火では、山腹が割れて吹き出してきた溶岩が流れて、民家まで200メートルのところへ迫った。そのときに流れた溶岩が森を焼いて、黒々としたガラガラ・ゴロゴロの溶岩を露出させた場所がある。植物が生えないままだったが、2013年の大雨で土砂崩れが起きると、幅の半分を泥が覆って、植物が一気に芽生え出した。
「今は冬なのでちょっと枯れていますけど、一面緑になって、びっくりしました。黒いところは、先ほど歩いた溶岩地帯と同じ、ゴツゴツガラガラの溶岩です。こちらの草が生えてきているところが、土砂が流れてきたところです。流れてきた土砂が隙間を埋めたのに加えて、養分のある土っぽい成分が流れてきたことで、植生が回復しているのです」
土砂が埋める前から、対岸の森からは蔓が這い伸びて、徐々に緑のじゅうたんが覆いはじめていた。
「蔓植物が木に登るのをやめて、光を求めて開けた溶岩の上に伸びてきていたんですね。この辺で白い花を咲かせているのは、テイカカズラという蔓だし、とりわけ太いのはサルナシという蔓です。ブドウも生えています。蔓同士で光を求めて争っていたんです。でも、土砂を被って生えてきた草の方が回復は早いと思いますよ」




まさに、生きている火山の島・伊豆大島。地球の活動を実感でき、噴火の中で生き抜く動植物の姿が目の当たりにできる“大地の公園”として、日本ジオパークネットワークへの加盟が認定されたのは、2010年9月のことだった。
島では現在、町や観光協会、民間団体、火山研究者などが協力・連携することで、官民一体となってジオパーク※1の保全・活用を図ることを目的に、「伊豆大島ジオパーク推進委員会」を組織している。西谷さんもメンバーの一人として、ジオパークの普及啓発やジオパークガイドの養成などに取り組んでいる。
「大島では、エコツアーを観光の柱に定着させるようと2009年春に活動を開始した、大島ネイチャーガイドクラブ(ONC)という組織が、ジオツアーの活動母体になってきました。今年それを解散して、ジオガイド組織に一本化しようと動き始めています。いろんな組織ができると煩雑化してしまいますし、人材養成も必要なので、ジオガイド養成講座を企画して、つい先日、第1回の講習会を開催したところです。4月末までには形にしたいと協議を進めています」
大島がジオパークに認定されて始まった取り組みを通じて、さまざまな気づきや発見もあった。
「ジオパークって人と人をつなげるのがおもしろいですね。島の産業も、たどっていけばもともと水捌けがいい溶岩地質につながります。例えば、島の主産業の一つに椿がありますが、もともと火山ガスに強いため自然に残った椿の木が、今の油製造や観光につながっています。防災でも、火山のことを知らないと安全な暮らしはできません」
2013年10月の台風26号による豪雨で大規模な土砂災害が発生した大島では、その後も雨のたびに崩壊斜面が削られて、下流の民家にも泥水が流れてくる状況が続いていた。斜面の土壌流失を防ぐため、2014年11月に東京都は発芽力の強いマメ科の草やヤシャブシなどの種子の空中散布を行った。散布された種子には外来種も含まれており、やがて島の自然植生に移行すると想定されているものの、一部の住民からは島内の植生に与える影響を懸念する声も聞かれたという。
2015年3月、ジオパーク推進委員会が中心になって、東京農工大学、環境省、東京都大島支庁土木課の協力を得て、崩壊斜面のモニタリング調査を開始。“ありのままの変化を住民みんなで見守り、考え、納得して暮らすことが大切”と、住民からの参加を募って、1~2か月ごとに雨量やその他気象状況、流出土砂量、植生の回復状態の調査を実施している。
大島では、噴火が今後も数十年周期で起こるだろう。四方を海に囲まれているから津波も来る。大雨が降れば、土砂災害の危険も避けられない。溶岩が流れてできた地面があってやっと人が住んでいられるからこそ、そこに住む人々が土地の特性に合った暮らしをしていくしかないのだろう。火山の島に住むというのはそういうことだと西谷さんは言う。