トップページ > エコアカデミー一覧 > 第74回 水に漂う生き物の情報 ~環境DNAを利用した生物調査~
2017.10.30
第74回水に漂う生き物の情報 ~環境DNAを利用した生物調査~

今藤 夏子(こんどう なつこ)
現在、霞ヶ浦流域・小笠原などで環境DNAによる水生生物や魚類の多様性・生態に関する研究の他、都市域とその近郊の昆虫集団の緑地間移動についての研究なども遂行中。DNA情報をパソコンで眺める研究も興味深いのですが、何といっても生き物を眼で見て感じることのできる野外調査が研究の基本であると感じています。
1.生物調査の難しさ
生き物の調査は、どこで何を調査するかにもよりますが、なかなかに難しいものです。ある場所で調査しても、それが本当に自分の想定している環境の調査対象種を十分に捉えているとは限りません。動物は動きますし、植物にしても探して必ず見つかるものではありません。使用する調査道具や方法、技術や時期によっても見つかる生物は異なります。また、調査者には生物の種類を見分ける熟練した能力が必要です(図1)。そのため、空間的に広く、地点が多くなるほど、また時間的に長期になるほど、質を揃えた調査を行うことは難しくなります。

【図1】魚類調査の一例としての投網。投げる人の技術に結果が大きく左右されてしまいます。写真は初心者。
2.生物調査における強力なツール「環境DNA」
しかし最近、水中の生物調査については、必ずしもその生物の専門家が現地に出向かなくても情報が得られるようになってきました。湖や池から水を汲むだけで手に入る「環境DNA」を分析すれば、そこに生息する生物の種類が分かるのです。
環境DNAは、水などの環境試料から抽出されるDNAの総称です。汲んだ水には、微生物や小さな生物が含まれていますが、眼に見える大きさの水生昆虫や魚はまず入っていません。しかし、その水から抽出される環境DNAには、微生物だけでなく、大型の生物のDNAも分泌物や排泄物、剥がれ落ちた組織片などとして混ざっています。DNAは生物の設計図としての役割があり、DNAを構成する塩基の並び順、すなわち塩基配列は生物の種ごとに違います。そのため、環境DNAの塩基配列を分析すれば、そこに生息する生物を検出できるのです(図2)。
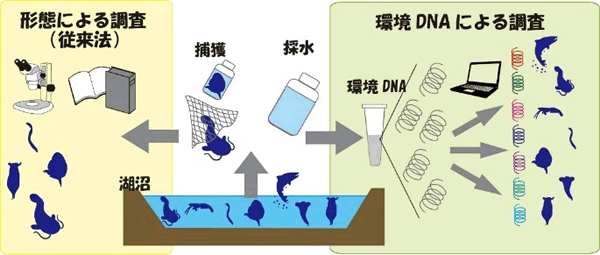
【図2】形態による従来の調査と環境DNAによる調査のイメージ。
3.環境DNAによる生物の検出法
環境DNAによる生物の検出手法は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、ターゲットの生物種のみを検出する方法(リアルタイムPCR法)です。この方法では、厳密な個体数とはいきませんが、おおよその存在量を反映したいわゆる定量性のあるデータが得られます。比較的廉価でデータの扱いも簡便であり、両生類などの希少種の探索にも多く用いられています。
2つ目は、細菌や魚類など生物のグループについて網羅的に検出する方法(メタバーコーティング法)です。微生物やプランクトン、魚類で特によく用いられています。ターゲットを絞らないため、私たちが想定していない種も検出される点も魅力的です。ただし、データの定量性は基本的にはないと考えられています。また、サンプルの調整技術や、得られる膨大な量のデータの取り扱いに高い専門性が必要であることから、リアルタイムPCR法よりは敷居が高い技術といえます。
4.環境DNAによる調査のメリット
環境DNAを使った生物調査の特徴は、なんと言っても調査地での作業の手軽さです。図3は、茨城県桜川において採水した200mlから得られた環境DNAの分析結果です。ある朝ふと思いつき、一人で現地にて水を汲み、研究所に戻ってから環境DNAを抽出し、塩基配列を分析しました【1】。調査地はご覧のとおりの濁った水で、魚類の専門家ではない私がとても一人で魚類調査ができる場所ではありませんが、データを得ることができました。なお、川幅や流量等にもよるのですが、実際の魚類調査で分析する水の量は1L以上が望ましいでしょう。
この他、環境DNAによる調査のメリットとしては、伝統的な調査に比べて検出感度が一般に高いことも挙げられます。そのため、希少種や侵入したばかりで個体数が少ない外来種の調査に有用です。調査地の作業は水を汲むだけですので、専門家である必要はありませんし、調査地の環境が調査によって破壊・改変されたりする心配もありません。塩基配列の情報があれば、調査者には形態で見分けられない生物であっても名前が判明します。環境DNAを利用すれば、生物の専門家に限らず採水ができる人に参加してもらうことで、1日で何十もの地点で精度の高い調査を同時に行うことが可能になります。
「標本」としての環境DNAにも大きな価値があります。きちんと保管しておくことで、将来的に、過去にさかのぼって分析することもできます。生物標本と比較してコンパクト、場所もとりません。

【図3】2017年7月の茨城県桜川における環境DNAによる魚類調査の結果例。岸辺で汲んだコップ一杯、200mlの水から環境DNAを抽出して分析しました。
【1】 魚類種の検出・分析手法は宮らの2015年の論文(英文)を参考
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/2/7/150088
5.環境DNAによる調査の課題
環境DNAによる生物多様性調査の手法には、問題点もあります。
まず、世界的に同意が得られている標準的な手法といったものが確立されていない点です。環境DNAが未だに一般的に利用されていない原因となっています。ただし、細菌類など一部の対象生物については、標準的な分析手法が確立されつつあり、分析業者へ委託できる場合もあります。
メタバーコーディング法では、塩基配列データベースを参照して生物名を検索するのですが、ある塩基配列を検出したとして、そもそもデータが登録されていなければ正体不明とされてしまいます。塩基配列の国際データベース(DDBJなど)ではデータ登録が急速に進んでいますが、まだまだ不足しているのが現状です。リアルタイムPCR法のデータにはある程度の定量性はありますが、個体数までとはいきません。
その他、分析対象の塩基配列が同じ生物は、形態で見分けがつくとしても環境DNAでは区別できません。実際に捕獲した生物なら、元気がない、色模様が違う、といった状態も分かりますが、現在の環境DNAによる解析ではそこまでは分からないのです。
検出感度の高さから、本来はその環境にないDNAが調査地や実験室などで混入してしまうコンタミネーションにも細心の注意が必要です。今後これらの課題が、データの蓄積と技術の革新によって克服されることが期待されます。
6.さいごに
環境DNAを利用した調査技術は、人員や予算を確保するのが大変な定期的・長期的な調査において、特に期待されています。水を汲むという手軽さは何にも代えがたいものです。しかし、DNAを抽出してから先の作業については、技術や費用面で手軽というにはあと一歩、といったところでしょうか。現在、世界中で環境DNAの研究が進められていますので、対象生物ごとの標準的な手法が提示されていくと考えられます。しかし、すぐにでも環境DNAによる調査の導入を検討するのであれば、従来法による調査結果と比較しながら、慎重に各種条件を検討していく必要があるでしょう。一方で、上記「4.」にあげましたように、今すぐ分析しなくても、現在の環境を示す「標本」としての環境DNAを保管しておくという考え方もできそうです。
環境DNAの登場により、通常の調査や生物分類の専門家が今後不要になるのではないか、という声も聞かれますが、決してそうではないと私は考えています。環境DNAだからこそ可能になることもありますが、その特徴をよく理解した上で、互いの調査方法と補い合い、検証し合いながら利用していくことが大切です。
本事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成で実施しております。
オール東京62市区町村共同事業 Copyright(C)2007 公益財団法人特別区協議会( 03-5210-9068 ) All Right Reserved.